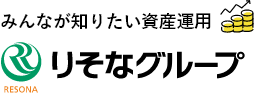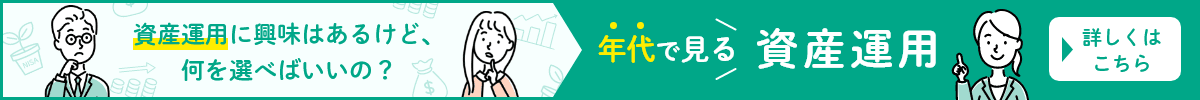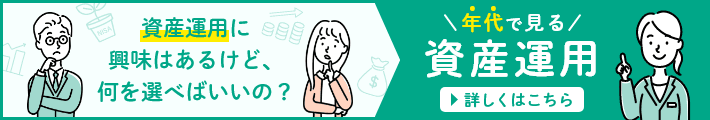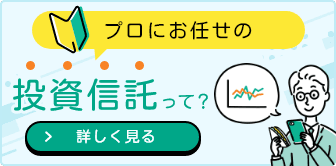投資の種類まとめ!初心者におすすめの投資と押さえておきたいポイント
公開日:2020/07/28
更新日:2025/09/09
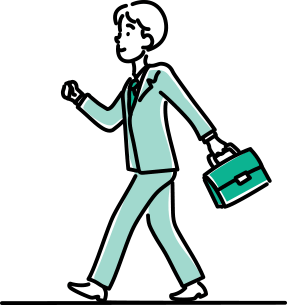
資産形成の手段として投資が注目されていますが、「初心者でどのような投資が向いているのかがわからない」という方も多いのではないでしょうか。
初心者におすすめの投資には、投資信託や外貨預金・個人向け国債などがあります。実際に投資をはじめる際は、目的や目標金額などを明確にしておくことが大切です。
本記事では、代表的な投資の種類や初心者におすすめの投資方法、初心者が最初にやるべきことなどを解説します。あわせて、投資を成功させるポイントや失敗例なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
投資の概要
~種類やはじめ方の前に知っておきたいこと~
投資には、複数の種類があります。まずは投資の基本を理解しましょう。
投資とは?
投資とは利益を見込んで自己資金を投じることです。例えば、利益を期待して投資信託や株式などを購入することが投資にあたります。投資は、銀行の預貯金とは異なり、期待できる利益が確約されておらず、投じたお金(元本)も確保されません。元本を失う“元本割れ”となる可能性もあります。
投資によって得られる2つの収益タイプ
投資で求められる収益には、大きく分けて「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2種類があります。どちらの収益を求めるかに応じて投資の仕方が変わってきますので、それぞれの違いを知っておくことが大切です。
インカムゲイン
資産を「保有」することで得られる収益がインカムゲインです。例えば、投資信託なら分配金、株式では配当金、債券なら利子が該当します。
これらの収益は、支払われる時期が決まっていることが特徴です。インカムゲインを得るためには、その時期に資産を保有している必要があります。
資産を保有し続けると継続した収益を期待できますが、投資信託の分配金や株式の配当金は、業績や運用の成果によって金額が変動するものです。また、業績によって支払われない場合もある点を、押さえておきましょう。
キャピタルゲイン
価値が変動する資産の「売買」で得られる収益がキャピタルゲインです。投資信託や株式、不動産、仮想通貨などの売買で得られる収益が該当します。
例えば、株価が30万円のときに購入した株式を35万円で売却した場合、差額の5万円(※税金や手数料は考慮せず)がキャピタルゲインです。
キャピタルゲインは、インカムゲインよりも利益が大きくなる可能性がある一方、損失も大きくなる可能性があります。
投資初心者が最初にやるべきこと
これから投資をはじめる方は、最初に以下のことを行いましょう。
投資をはじめる目的と目標金額の明確化
まずは、「何のために投資をはじめるのか」「いつまでにどれくらい貯めたいか」といった目的と目標金額を明確にすることが大切です。
例えば、「老後資金として、20年後までに1,000万円貯めたい」「住宅購入のために、10年後までに500万円必要」など、期間も決めておくとよいでしょう。こうした目標設定は、投資を続けるうえでのモチベーション維持にもつながります。
さらに、目的や金額がはっきりすることで、自分に合った投資方法が見えてくるはずです。
投資の知識習得
基本的な知識が欠けていると、誤った選択をして大きな損失を招く恐れがあります。投資をはじめる際は、最低限の知識を身に付けておきましょう。
投資の知識習得には、書籍やインターネット上の記事、動画配信サイト、セミナーなどが挙げられます。これらは初心者向けから上級者向けまで幅広いレベルがあるため、まずは初心者向けから取り組むのがおすすめです。
ただし、情報源によっては内容に偏りがみられることもあるため、複数の方法で情報を比較・精査することが重要です。そのうえで、各媒体で共通して示されている内容は、投資の知識として信頼性が高く、有益であると判断できるでしょう。
投資の種類一覧~代表的な投資12選~
投資と聞くと、投資信託や株式をイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし、ほかにも投資商品は複数あります。商品によって、期待できる利益や損失の度合い、取扱う金融機関は異なるものです。
ここでは代表的な12種類の投資商品を、銀行で取扱いしているものとしていないものに分けて紹介します。
銀行で取扱いをしている投資の種類
銀行で取扱いをしている投資商品には、以下のようなものがあります。
投資信託
投資信託では、「資産運用の専門家」である運用会社が、投資家(お客さま)に代わって運用を行います。たくさんの投資家から集めたお金をもとに運用するので、大きな資産規模となり、複数の対象に分散して投資が可能です。
対象となる投資先には、例えば国内外の株式や債券、不動産などがあり、目標とするリターンやリスクに応じてこれらの組み合わせ方や配分を変えています。なお、投資信託のなかでも株式を組み入れて運用できるものが「株式投資信託」です。
また、不動産の投資信託のことを「REIT(リート)」といいます。これは、投資家から集めた資金でファンドマネージャーが複数の不動産に投資を行い、そこから得られる家賃収入や不動産の売買益を投資家に配当するものです。
特定の投資対象に集中すると、業績や景気によって受ける影響が大きくなる傾向にありますが、投資先を分けることでリスク分散ができます。
投資家が一人で分散投資する場合は、資金のみならず、経済動向や金利、税金といったあらゆる分野の知識が必要です。しかし、投資信託なら、たくさんの投資家がお金を出し合う仕組みであるため、少額から投資(購入)ができます。
外貨預金
外貨預金とは、円ではなく米ドルやユーロなどの外貨で行う預金です。一般的な円預金と同様の仕組みで、預けたお金に対して利息が付与されます。
預入れ時には円から外貨に、引出し時には外貨から円に換金してお金を出し入れするため、為替変動の影響を受けることが特徴です。
例えば、預入れ時よりも払出し時に「円安」になれば利益を得られます。しかし、「円高」になった場合は預入れたお金(円建て)よりも下回り、損失が発生する仕組みです。なお、預入れ時と引出し時には為替手数料が発生します。後述するFXとは異なり、外貨預金は手持ち資金以上の取引ができません。
国債
国債(こくさい)とは、国が資金調達のために発行する債券です。銀行で「個人向け国債」という名称を見たことがある方もいるかもしれません。債券とは「借入証書」のようなもので、利子や返済する期間(償還日)、返済する金額(償還金額)などが決められています。
国債を購入すると、定期的に利子が支払われ、原則、満期(償還日)になれば元本が返却される仕組みです。日本が発行する日本国債のほか、各国政府が発行している外国債券もあります。
銀行で取扱いをしていない投資の種類
ここで紹介する投資商品は、証券会社やFX会社など、種類ごとに取扱いできる会社が決まっています。
株式投資
企業が資金調達のために発行する株式を売買し、その差額利益や配当金を期待する投資方法です。株価は、企業の業績や景気状況、各投資家の売買状況(需要と供給)などの影響を受けて常に変動しています。
株式の現物取引では、自分が投資した金額以上の損はしません。余裕資金で行うことや、少額の投資とすることでリスクの低減が可能です。そのほか、株式を売らずに保持すると、配当や株主優待などのインカムゲインも期待できます。
FX(外国為替証拠金取引)
FXとは「Foreign Exchange」の略で、外貨を売買してその差益を得る投資手法です。外貨の為替差益によって収益を得る投資方法には、先に紹介した外貨預金もあります。
FXでは、「レバレッジ」という手持ちの資金を超えた金額で取引できる仕組みが利用可能です。レバレッジをかけることで、担保となる資金(取引保証金)の何倍もの金額を取引できます。これにより、少ない資金で大きな投資が可能です。
ただし、思惑と逆の方向に為替が動いた場合には、損失が大きくなる恐れもあるため、注意を要します。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上でやりとりされる通貨のことで、公的な発行主体や管理者がいないのが特徴です。
「仮想通貨」という名称を、聞いたことがあるかもしれませんが、2020年5月1日に改正資金決済法と改正金融商品取引法が施行され、「仮想通貨」という呼称から、「暗号資産」に切り替えられました。
暗号資産は、短期間で価値が何倍にもなる可能性がある一方で、需要の増減や市場の変動によって価格が大きく下落するハイリスク・ハイリターンな商品です。
また、取引所の廃止やハッキングなどによって引出せなくなる可能性もあります。2020年の法改正によって、不正行為などに対して法規制が行われました。しかし、預金保険機構のような補償があるわけではないため、注意が必要です。
ETF(上場投資信託)
ETFとは、「Exchange Traded Funds」の略で、日本語に訳すと上場投資信託です。ETFは、先に紹介したような投資信託のうち、証券取引所に上場しているものを指します。株式と同様に証券取引所を通じて売買取引できることが特徴です。なお、ETFは上場しているもののみが対象であるため、一般的な投資信託と比較すると商品数や種類が少ないという特徴もあります。
不動産投資
不動産投資は、利益を得ることを期待して土地やアパートなどに投資する方法です。例えば、物件価値の上昇を期待して不動産を購入し、価値が上がったときに売却して利益を得ることや、購入した不動産を人に貸して家賃収入を得ることもできます。
ただし、不動産購入資金が大きくなる傾向にあるため、初心者にはおすすめしにくい投資方法です。
個人向け社債
社債(しゃさい)とは、企業が投資家から資金を募る際に発行する有価証券です。先に紹介した国債のように、債券上に償還日や利払日、利率(クーポンレート)などが明記されています。
企業が投資家から資金を募る目的で発行する有価証券には株式もありますが、株式と異なるのは発行した企業に返済義務を課す点です。
金(きん)
金は、世界共通の価値で扱われている投資資産です。金の取引は米ドルで行われ、日本国内での金価格は米ドルの為替相場の変化に応じて上下します。金は世界情勢の変化に強いことが特長です。そのため、「有事の金」とも呼ばれ、株安などが起きると、安全資産として金を買う人が増えるといわれています。
なお、埋蔵量に限りがあるため、金を買う人が増えて価値が上がる場合はあっても、歴史上、無価値になったことはありません。
先物・オプション
先物・オプション取引は、主に株式や債券、通貨、金利などの原資産から派生した商品で、まとめてデリバティブ(派生商品)といわれることがあります。先物取引とオプション取引の主な違いは、以下のとおりです。
横スクロールできます。
| 先物取引 | 株式や債券などの商品を、事前に決めた期日・価格での売買を約束する取引手法 |
|---|---|
| オプション取引 | 事前に決めた期日・価格での「原資産の買付け、あるいは売付けのオプション(権利)」を売買する取引手法 |
どちらも、まだ価格の決まっていない未来の株式や債券、コモディティなどを取引するものです。相場の見通しに沿って価格が動けば大きな利益が期待できますが、見通しが外れた場合の損失も大きくなりやすい特徴があります。
このように、先物取引やオプション取引はハイリスク・ハイリターンとなるため、初心者に適した投資ではありません。
MMF・MRF
MMFとMRFは、どちらも株式を一切組み入れず、国債や社債などを中心に運用する公社債投資信託の一種です。
横スクロールできます。
| MMF |
|
|---|---|
| MRF |
|
どちらも元本保証はされていませんが、元本割れのリスクが低く、1円以上1円単位で購入できるなど、初心者にもはじめやすい特徴があります。ただし、日本銀行のマイナス金利政策の導入によって、現在は事実上、運用が難しい状況となっている点には注意が必要です。
初心者におすすめの投資方法3選
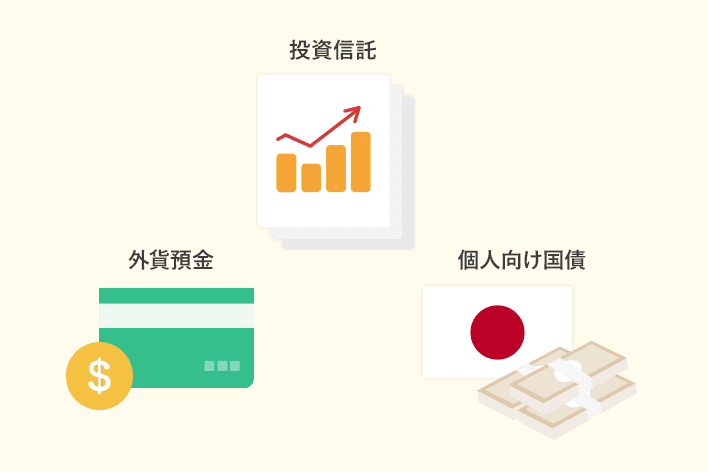
ここからは、投資初心者におすすめの、少額投資が可能で、比較的リスクが低いと考えられる投資方法を紹介します。
投資信託
普段から仕事で忙しく、市場の動きを把握するのが難しい方や、資産を分散したい方には、投資信託をおすすめします。なぜなら、「資産運用の専門家」が社会や経済の情勢を見ながら投資対象や売買のタイミングを見極めて運用してくれるからです。
国内外の株式・債券・不動産などに「分散投資」する仕組みであるため、少額から分散投資できる点もポイントです。投資の知識が浅くても安心して任せることができます。
外貨預金
初心者には、商品の仕組みが銀行預金とほぼ変わらない外貨預金もおすすめです。ただし、外貨預金は円安になれば大きな利益を期待できる一方で、円高になると元本割れのリスクもあります。そのため、今後必要となる資金を外貨預金に回すのは避け、余裕資金だけで行うようにしてください。
また、前述したように預入れ時と引出し時には為替手数料がかかります。例えば、預入れ時と引出し時の為替レートがまったく同じだったとしても、為替手数料を含めるとマイナスになってしまう可能性があるため、注意が必要です。
手数料は、取引する通貨や金融機関によっても異なります。外貨預金をはじめる前にきちんと確認しておきましょう。
個人向け国債
「手軽で堅実にはじめられる投資がいい」という方には、額面1万円から購入できる個人向け国債がおすすめです。個人向け国債は、満期3年(固定金利)、5年(固定金利)、10年(変動金利)の3タイプから選択できます。タイプによって金利の設定方法は異なりますが、どのタイプでも年2回利子を受取ることが可能です。
初心者が投資を成功させるために
覚えておきたいポイント
ここでは、初心者が投資をはじめる際のポイントを4つ解説します。
投資のリスクとリターンの関係について理解しておく
投資におけるリスクは「危険」や「損」を意味するのではなく、「価格の振れ幅」を示します。投資商品の価格は日々変動しますが、その変動幅がリスクの大きさを示すと覚えておきましょう。一方、リターンは投資で得られる利益のことです。
なお、投資のリスクとリターンは比例関係にあるといわれており、リスクが小さいほどリターンも小さく、リスクが大きいほどリターンも大きくなります。
例えば、外貨預金や金投資は「ミドルリスク・ミドルリターン」、株式投資や投資信託(株式型)は「ハイリスク・ハイリターン」の投資商品です。
余裕資金でスタートさせる
無理にお金を投資に回すと、日常生活に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。投資は、当面の間使う予定のない余裕資金で行いましょう。
また、想定外の出費に備え、収入がなくても数ヵ月生活できる程度の生活費を確保しておくと安心です。
少額からはじめる
初心者が投資をスタートさせる際は、「期待通りに値動きするかどうかわからないリスク」を考えたうえで、少額からはじめることが大切です。少額投資なら、運用資金が少ないため、購入時の価格より下がった場合でも大きな損失を抑えることができます。
また、少額ではじめるためには、積立投資がおすすめです。投資には「タイミングを見計らって投資信託などを少しだけ購入する方法」「定期的に一定額ずつ購入していく方法(積立投資)」があります。少額でもコツコツと積立投資を長期で続けていれば、目先の値動きに惑わされることなく安定的に資産運用ができるでしょう。
特に若い方の場合、結婚資金や住宅資金、転職など、ライフステージの変化に応じてお金が必要な場面が出てくる可能性もあります。そのため、「お金が必要なときにすぐに使える」という点を考慮することも大切です。投資と貯蓄のバランスを考慮した資産形成を行っていれば、急にお金が必要となった場面でもスムーズに対応できます。
資産の分散をする
投資のリスクを低減させるためには、「資産・銘柄」「地域」「時間」の3つの分散がポイントです。
- 資産や銘柄の分散
- 例えば、株式や債券など、値動きが異なる複数の資産や銘柄でポートフォリオを組むことです。経済動向の変化による値下がりリスクの分散ができます。
- 地域の分散
- 例えば、日本や外国の株式、外国なら先進国や新興国などと、異なる地域の投資商品を組み合わせることです。地域ごとの経済状況変化で生じる価格変動リスクを分散できます。
- 時間の分散
- 投資するタイミング(時間)を分散させることです。例えば、同じ投資信託を毎月決まった金額分だけ購入するなど、少額かつ定期、定額で投資を行うことにより、時間の分散ができます。投資信託は、経済動向によって毎営業日基準価額が変動するのが特徴です。
そのため、タイミングによっては、高い基準価額で投資するときと低い基準価額となるときがあります。しかし、すべてをならすと投資価格が平準化されるため、結果的に1回当たりの投資価格を抑え、価格変動リスクを軽減する効果があるのです。
これら3つの「分散」を意識して投資を実践すれば、資産運用におけるリスクを軽減しやすくなります。
投資初心者におすすめの制度もあわせて紹介
投資をはじめる際には、非課税特典のあるNISAやiDeCoといった制度をあわせて利用するのがおすすめです。それぞれの制度の違いを知り、投資目的にあった制度を選びましょう。
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)
NISAは「少額投資非課税制度」といい、投資(投資信託や株式の購入)から得られた利益が、非課税で受取れる制度です。
- ※通常、投資をして分配金や売買益などの利益を得ると20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかります。
NISAには少額からの積立てで利用できる「つみたて投資枠」と、自分のタイミングで投資信託等が購入でき、対象商品も幅広い「成長投資枠」があります。それぞれの枠は併用可能です。違いは以下のとおりです。
横スクロールできます。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 購入方法 | 一括・積立 | 積立のみ |
| 非課税保有限度額 (生涯での投資可能額) |
1,800万円
|
|
| 1年間の投資可能額 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税の対象期間 | 無期限 | |
| 投資対象商品※ | 一定の基準を満たした投資信託 つみたて投資枠より商品数は多い |
一定の基準を満たした投資信託 長期の積立・分散投資に適した投資信託 |
- ※投資対象商品はりそなグループ各社で取扱いのあるものを記載しています。
成長投資枠とつみたて投資枠の併用ができるため、手元資金に余裕のある場合は一括投資と積立投資を組み合わせて制度を利用できます。
また、2024年の制度改正により、非課税保有限度(総枠)は簿価残高方式で管理することとなりました。つまり、NISAで運用している投資信託等を売却すると翌年以降、枠の再利用ができます。NISAは2024年の制度改正により格段に柔軟性が高くなったため、さまざまな目的で利用ができます。
NISAを利用する場合には、NISAを取扱っている金融機関で別途NISA口座の開設が必須です。また、NISA口座はすべての金融機関で一人1口座しか開設ができません。つまり、A証券でNISA口座を開設した場合、B銀行やC証券では口座を開設できないということです。
ただし、1年に1回金融機関の変更ができます。NISAの口座開設や金融機関の変更は、税務署への書類提出もあり時間がかかるため、早めに手続きしておくとよいでしょう。
- ※りそなグループでは、株式の購入など、株式投資の取扱いはありません。
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月決まった掛け金を拠出・運用し、原則60歳以降に老齢給付金を受取れる私的年金制度です。公的年金の不足を補う目的でできた私的年金制度であることから、以下のような税制メリットもあります。
掛金は全額所得控除になる
1年間に拠出した合計金額を所得から控除できるため、課税所得が少なくなり所得税と住民税が軽減されます。掛金は会社員・自営業者・主婦など職業や企業年金等の加入状況等によって、それぞれ上限が決められています。
運用益が非課税になる
運用期間中に得られる分配金や売買益などは非課税です。
- ※通常の投資では利益に対して20.315%(復興特別所得税を含む)かかります
受取時に公的年金等控除・退職所得控除が適用される
分割で受取る場合は公的年金等控除、一時金で受取る場合には退職所得控除が適用され、所得税を軽減する効果があります。また、iDeCoでは加入時、運用時、給付時に手数料がかかるため、注意が必要です。支払いのタイミングや金額は、金融機関によって異なるため、確認しましょう。
NISAもiDeCoも、それぞれすべての金融機関で一人1口座と決められています。金融機関の変更はできますが、複数の金融機関での口座を開設することはできないため、金融機関選びが重要です。
投資初心者にありがちな3つの失敗例
ここからは、投資初心者が陥りやすい失敗例を紹介しますので、参考にしてください。
他者の意見を鵜呑みにして購入する
投資をはじめる前に知識の習得は必要ですが、SNSやインフルエンサーなど、人の情報を鵜呑みにして投資をするのは注意が必要です。
これらの情報はすべてが正しいとは限らず、なかには自身の利益を目的として情報発信をするユーザーも少なくありません。
また、金融機関や証券会社の情報は、あくまで参考程度にとらえ、最終的な判断は自己責任で行うことが大切です。
リターンを期待して投資にお金を回しすぎてしまう
お金を早く増やしたい気持ちが大きくなり、生活費を投資に回してしまう方もいます。しかし、生活費や近い将来使い道が決まっているお金まで投資に回してしまうと、想定外の出費があった場合に対応できなくなる可能性があります。
「投資に回すお金」と「投資に回さないお金」は明確に区別しましょう。
日々の値動きが気になり売買を繰り返す
投資初心者の場合、日々の値動きがどうしても気になり、売買を繰り返す傾向があります。例えば、以下のような方は注意が必要です。
- 投資先の価格が下落すると不安になってすぐに売却してしまう
- 投資予定の商品価格が上昇したので急いで購入してしまった
一般的に、投資商品の価格は日々変動しています。そのため、長期的な視点で構え、じっくりと投資に取り組むことが大切です。
コツコツ資産を増やすなら
「ほったらかし投資」も一つの選択肢
コツコツと長期的な資産増加を狙うなら、ほったらかし投資も選択肢の一つです。ほったらかし投資とは、事前に運用の方針や環境を整えておき、投資開始後は基本的に放置して資産が増えるのを期待する投資方法を指します。
例えば、NISAのつみたて投資枠で行う積立投資やiDeCo、不動産クラウドファンディング、ロボアドバイザーなどが該当します。運用に手間がかからず、少額からはじめられるものが多いため、初心者向きです。
ただし、当然元本割れのリスクはあります。完全に放置してしまうのではなく、定期的に運用状況を確認することも大切です。
まとめ
投資は、利益を見込んで自己資金を投じることです。銀行の預貯金のように利益は確約されておらず、投資方法で期待できる利益や損失の度合いが異なります。
投資初心者には、投資信託・外貨預金・個人向け国債のほか、税制優遇を受けられるNISA、iDeCoといった制度の利用がおすすめです。なお、投資の成功率を上げるためにも、以下のポイントを守りましょう。
- 投資の知識習得に努める
- リスクとリターンの関係を理解する
- 日々の値動きに左右されず長期的に取り組む など
りそなは、確かな運用知識と手厚いサポートで、初心者の方にも安心して投資をご利用いただけます。投資をはじめてみようと思われている方は、ぜひ、りそなにご相談ください。
4問で運用方法・商品を
サクッと診断
お金をためたい
本記事は2025年9月9日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。
運用はプロにお任せ!
NISAご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。
- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。
- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。