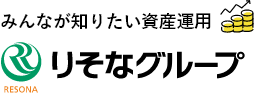サラリーマンの平均年収はいくら?年代別の金額や収入アップの5つの方法
公開日:2019/11/19
更新日:2025/03/10

「自分の年収は平均と比べてどうなのだろう?」と気になる人は多いでしょう。人生の中で、結婚やマイホーム購入、子育て、老後の準備など、大きなライフイベントを迎えるたびにまとまった費用が必要になります。
サラリーマンの平均年収や貯金額を知ることで、自分の収入や貯蓄の現状を客観的に把握でき、将来に向けた計画を立てる手助けになります。
この記事では、サラリーマンの平均年収を「全体」「男女別」「年代別」「業種別」にわけて紹介します。また、各ライフイベントにかかる費用や平均貯金額、収入を増やすための具体的な方法についてもご紹介します。
30~40代のサラリーマンにおすすめの資産運用も併せて紹介しますので、今後のライフプランを考える際にお役立てください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
サラリーマンの平均年収|全体・男女別・年代別・業種別
年収・手取り額・貯金額などは、いずれも勤務先の企業や業種、肩書、性別、勤務年数などによる違いが大きいです。ここでは、国税庁が公表している「令和5年分 民間給与実態統計調査」を参考に、いくつかの観点で平均年収を紹介します。
サラリーマンの全体・男女別平均年収
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、令和5年分のサラリーマンの全体および男女別の平均年収は以下のとおりです。
横スクロールできます。
| 性別 | 平均年収 | 平均手取り額(概算) |
|---|---|---|
| 全体 | 約460万円 | 約368万円 |
| 男性 | 約569万円 | 約455万2,000円 |
| 女性 | 約316万円 | 約252万8,000円 |
出典:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」平均給料・手当および平均賞与
平均年収の右の欄の金額は平均手取り額の概算です。一般的な目安ですが、給料から社会保険料・所得税・住民税が控除されるため、手取り額は平均年収の8割として計算しています。
男性と女性では、平均年収に約1.8倍の差があります。あくまでも一般論ですが、女性の平均年収には、産休や育児といった社会的要因が影響していると考えられます。
サラリーマンの年代別平均年収
続いて、年代別の平均年収を見てみましょう。同調査によれば、年代別の1人当たり平均年収は以下のとおりです。ここでも同様に、手取り額は平均年収の8割ほどとして計算しています。
55歳までは年齢を重ねるにつれ上昇する傾向にあり、55~59歳の平均年収が最も高いことがわかります。
- <年代別平均年収・平均手取り額>
-
年齢 平均年収 平均手取り額(概算) 20~24歳 約267万円 約213万6,000円 25~29歳 約394万円 約315万2,000円 30~34歳 約431万円 約344万8,000円 35~39歳 約466万円 約372万8,000円 40~44歳 約501万円 約400万8,000円 45~49歳 約521万円 約416万8,000円 50~54歳 約540万円 約432万円 55~59歳 約545万円 約436万円 60~64歳 約445万円 約356万円 - 出典:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」年齢階層別の平均給与
収入をもっと上げるには
どんな方法がある?
サラリーマンの業種別平均年収
最後に、業種別に平均年収を確認してみましょう。同じく、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、サラリーマンの業種別平均年収は以下のとおりです。平均手取り額の概算は、平均年収の8割として計算しています。
横スクロールできます。
| 業種 | 平均年収 | 平均手取り額(概算) |
|---|---|---|
| 建設業 | 約548万円 | 約438万4,000円 |
| 製造業 | 約533万円 | 約426万4,000円 |
| 卸売業・小売業 | 約387万円 | 約309万6,000円 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 約264万円 | 約211万2,000円 |
| 金融業・保険業 | 約652万円 | 約521万6,000円 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 約469万円 | 約375万2,000円 |
| 運輸業・郵便業 | 約473万円 | 約378万4,000円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 約775万円 | 約620万円 |
| 情報通信業 | 約649万円 | 約519万2,000円 |
| 学術研究・教育など | 約551万円 | 約440万8,000円 |
| 医療・福祉 | 約404万円 | 約323万2,000円 |
| 複合サービス事業 | 約535万円 | 約428万円 |
| サービス業 | 約378万円 | 約302万4,000円 |
| 農林水産・鉱業 | 約333万円 | 約266万4,000円 |
- 出典:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」業種別の平均給与
この集計では、業種によって平均年収にばらつきがあります。最も高い「電気・ガス・熱供給・水道業」の平均年収と、最も低い「宿泊業・飲食サービス業」の平均年収では、約511万円の差があります。
30代・40代のライフイベントでかかる金額
30代、40代に想定されるライフイベントの種類と、それにかかる費用についても確認しましょう。将来必要になる資金の目安を知れば、目標をもって貯金できます。
30代、40代のライフイベントでは、結婚や出産の可能性を考慮し、結婚費用や住宅資金、教育資金の用意が必要です。
また、マイホームを購入した場合には、年月の経過により住宅の老朽化にともなう修繕費など、まとまった費用が必要になる可能性があります。さらに、老後の生活費や介護費用も忘れてはなりません。
ここでは、30代、40代の主なライフイベントと、それにかかる平均費用の例を紹介します。
| 結婚費用 | 約344万円(挙式、披露宴・ウエディングパーティーにかかる費用総額)※1 |
|---|---|
| 教育資金 | 子ども1人当たり約987万円(高校まで公立、大学のみ国立の場合にかかる学習費用総額)※2 |
| 住宅購入費 | マンション:約5,245万円 中古マンション:約3,037万円 土地付き注文住宅:約4,903万円 注文住宅:約3,863万円 建売住宅:約3,603万円 中古戸建て:約2,536万円 (2023年度における住宅の全国平均購入価格)※3 |
| 老後の生活費 | 1ヵ月当たり約25万円(65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支・消費支出)※4 |
| 介護費用 | 1ヵ月当たり約20万円(介護サービスの受給者1人当たり費用額)※5 |
| 緊急資金 | 約75~300万円(1ヵ月の生活費が25万円と想定し、生活費の3ヵ月~1年分を確保する)※6 |
- ※1株式会社リクルート「ゼクシィ 結婚トレンド調査2024 調べ」
- ※2文部科学省「家計負担の現状と教育投資の水準」大学卒業までにかかる費用
- ※3住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」
- ※4総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」
- ※5厚生労働省「令和5年度 介護給付費等実態調査の概況」
- ※6日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「主なライフイベントにかかる費用の目安」
結婚費用にはブライダルローンなどの目的別ローン、教育資金なら教育ローン、住宅取得資金なら住宅ローンの利用が考えられます。
しかし30代、40代でローンの返済をしながら貯金をするのは、簡単なことではありません。子どもが独立して教育費の負担がなくなってから、老後の資金をためようと考えるケースも想定されます。
仮に老後に向けて資金をためようとしても、病気やケガで働けなくなったり、急なリストラにあったりと、予想外にお金が必要になる可能性も考慮しなければなりません。思っていた以上にお金をためるのに時間がかかる可能性もあるため、資産形成の準備はできる限り早くからはじめることが大切です。
また、厚生労働省が発表した「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」によれば、2022年の1世帯当たり世帯主の年代別平均貯蓄額と、年代別平均借入金額は以下のとおりでした。
比較すると、住宅ローンや教育ローンの負担がかかる世代では、借入額が貯蓄額をはるかに超えることがうかがえます。
- <年代別平均貯蓄額・平均借入額>
-
年代 平均貯蓄額 平均借入額 29歳以下 約245万1,000円 約717万8,000円 30~39歳 約925万8,000円 約1,248万4,000円 40~49歳 約287万8,000円 約1,211万4,000円 50~59歳 約970万4,000円 約544万9,000円
それぞれの平均値は上表のとおりですが、実際は世帯ごとに内容が大きく異なります。自分自身の収入額や貯蓄額と照らし合わせて、必要があれば支出の見直しを図りましょう。
サラリーマンの平均年収推移と今後の展望
30代や40代で迎えるライフイベントでは、まとまった資金が必要になるとわかりました。無事にライフイベントを迎えるためにも、今後の年収にどのような変化が考えられるのか把握しておくことが重要です。
ここでは、サラリーマンにおける平均年収の推移などを紹介します。その結果から、今後予想される変化などについて考えていきましょう。
平均年収はピーク時よりも減少している
厚生労働省「令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-」 によれば、日本の平均年収のピークは1990年代であることがわかります。ピーク時と比較すると、2018年の平均年収は約40万円減少しているのです。
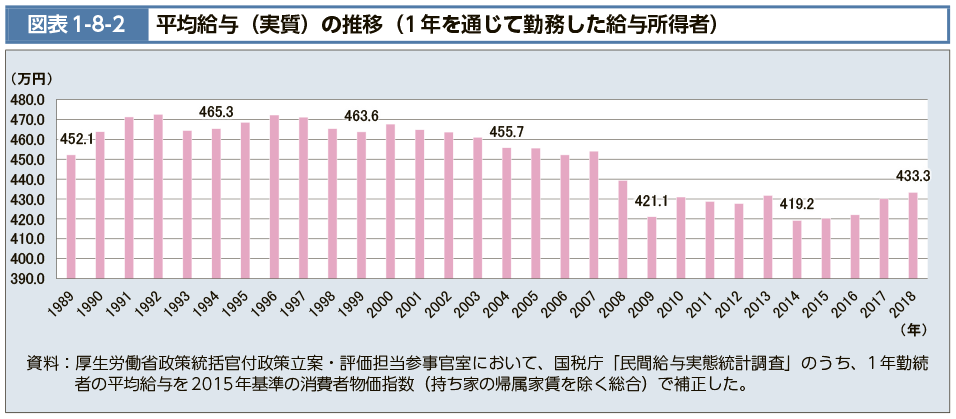
出典:厚生労働省「平均給与(実質)の推移(1年を通じて勤務した給与所得者)|令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-」
その原因の一つとして、雇用形態の変化が挙げられます。平均年収のピークを迎える前後に起こったバブル崩壊により、雇用抑制などの対策が講じられました。その後、正社員よりも非正規雇用者を増やしたことで、低所得層が増加したと考えられます。
また、バブル崩壊後の経済成長率は低下し、雇用形態の多様化なども見受けられました。“成長”よりも“安定”が定着し、現状の年収額が低い人は、今後も大きな変化を得られることなく時間が過ぎていく可能性が高まっています。
生涯支出は増加傾向
厚生労働省「令和5年簡易生命表」によれば、平均寿命は過去と比較して延びていることがわかります。寿命が延びるということは、その分の生活費が必要ということです。生涯支出が増大することを理解しておかなければなりません。
横スクロールできます。
| 平均寿命 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1960年 | 65.32歳 | 70.19歳 |
| 1980年 | 73.35歳 | 78.76歳 |
| 2000年 | 77.72歳 | 84.60歳 |
| 2023年 | 81.09歳 | 87.14歳 |
参考:厚生労働省「令和5年簡易生命表」
しかし、前述したように、平均年収は減少傾向にあります。年収と支出に生じるギャップを解消しなければ、将来的に生活の維持が困難になるかもしれません。また、事故や病気など、予期せぬトラブルによって急に働けなくなる可能性も考えられます。時間に余裕があるとは考えず、万が一の状況に備えられるような対処が必要です。
サラリーマンが収入を増やす方法5選
平均年収の減少や生涯支出の増加を考慮すると、生活を維持する対策の一つとして、資産の増加が有効と考えられます。
ここでは、サラリーマンが資産を増やす方法を紹介しますので、自身に適した方法を確認しましょう。
昇進を目指す
現在の職場で資産を増やすためには、昇進を目指す努力をして年収を増やす方法が有効です。現在よりも高い役職になれば、基本給のアップだけでなく、役職手当も期待できます。毎月の収入が増えることで、貯金に回す金額を増やすことも可能です。
しかし、企業ごとに昇進の基準は異なるため、自身の意思だけではどうにもならない要素でもあります。また、年功序列の傾向が強い企業の場合は、能力が正しく評価されない可能性があることも考慮しなければなりません。
資格手当を活用する
資格手当は、企業から給与に追加して支給される手当の一つで、特定の資格を取得することで支給されるものです。
資格手当の支給有無は、企業によっても異なりますが、支給される手当が増えれば給与総額が増えるため、収入を増やすための有効な手段といえます。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、資格手当を支給している企業の割合は50.8%と過半数です。ただし、一般的に手当の対象となる資格は業務・職務に関係のあるものに限られます。
まずは自身の会社の制度を確認し、対象となる資格を把握することから始めてみましょう。業務に関連した資格を取得すれば、スキルアップと資格手当による収入増加の両方を実現できます。
副業や兼業をする
副業や兼業は、すき間時間や休日を活用し収入を増やす手段として注目されています。副業を認めている企業もありますが、独自のルールや制限が設けられている可能性もあるため、まずは勤務先の規定を確認することが大切です。
副業を行う際には、確定申告や住民税の申告が必要な場合があることも考慮して、税金の対策も整えておきましょう。
年収の高い職場への転職を検討する
現在の職場で年収を上げるのが難しい場合には、転職を検討するのも有効です。以前までは「転職すると不利になるのでは」と、不安になる人もいたかもしれません。現在では、新たな目標に挑戦するステップととらえる傾向もあるため、ネガティブな印象ばかりではないと考えられます。
しかし、転職活動をはじめて、すぐに転職先が決まるという保証はありません。そのため、転職先が決まるまでは、生活が不安定になることを考慮する必要があります。
資産管理の知識を深める
十分な年収を得ている人でも、すぐ使ってしまい貯金がない人もいます。つまり、年収アップを目指しても、ためようと思う気持ちや適切な資産管理の方法を理解していなければ、資産を増やせるとは限りません。
着実に資産を増やしたい場合は、年収が増加したとしても余裕があるとは考えず、支出の見直しや貯金を行いましょう。これまで、どのようなものにどれだけ支出していたのかを把握することは、自身が目指す理想的な資産管理の第一歩になります。
サラリーマンが貯金上手になるためのポイント3つ

サラリーマンは比較的毎月の収入が安定しているため、計画を立てればしっかりと貯金を増やすことが可能です。
しかし、毎日の食費を節約したり、特売品を購入したりするなど、細かい節約を意識していても「知らないうちにお金がなくなり貯金にまわせるお金がない」といったことがありませんか?そうならないためにも、まずは今すぐできる収支の見直しから取り組んでみましょう。
保険の見直し
生命保険や傷害保険など、重複した保障がないかを見直しましょう。保険は加入した当時のままになっていたり、知り合いから勧められて付き合いで加入したりするケースもあるからです。
まずは、加入している保険を「死亡保障」「年金保険」「がん保険」「傷害保険」のように分類し、現状の保障と支払い金額を確認してみてください。
また、保障金額は年齢や家族構成によっても異なるため、定期的に見直すことが大切です。見直しに不安がある場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
住宅ローンの借換え
住宅ローンの金利水準は、これまでと比べて下がっています。そのため、世帯によっては現在適用されている住宅ローン金利よりも、他の金融機関の住宅ローン金利が低くなっていることもあり得るのです。その場合は、借換えを検討することで支出を大幅に削減することもできます。
借換えをする際は、「金利差が1%以上ある」「残高が1,000万円以上ある」「返済期間が10年以上残っている」などを目安にしましょう。
りそなグループのように、土・日・祝日でも相談ができる銀行もあるので、一度借換えのシミュレーションをしてもらうのがおすすめです。毎月の支払い金額や、総返済金額を減らせるかなど、具体的な金額がわかります。
家計の支出の計算
毎日つけるのが面倒な家計簿ですが、毎月の収支を把握するのには最適な方法です。家計簿で毎月の貯金額を支出に入れれば、計画的な貯金が実現できます。給与天引きの保険料のように毎月の支出に決まった貯金額を組込み、貯金専用の口座を作って入金する方法もあります。
「あまったら貯金にまわそう」と思っても、貯金の習慣がついていない人の場合、ある分だけ使ってしまうことが想定されるため、「あまらないから貯金できなかった」となりかねません。
そのため、はじめから貯金を支出として見込んでしまい、そのお金はないつもりで別口座に入金すると、少しずつでもお金がたまっていきます。
このような方法で貯金にまわす、お金を作る人が貯金上手といえるのです。無理をせずコツコツとお金をため、貯金分を少しずつ増やしましょう。
サラリーマンが資産運用でお金を増やすには?
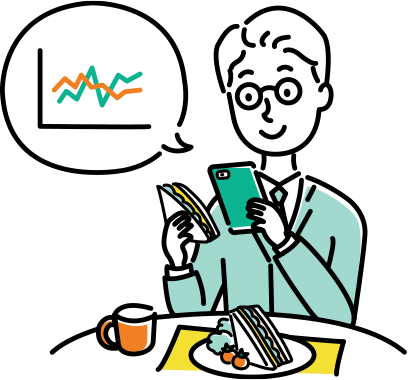
人生にはあらゆるライフイベントがあり、そこには当然のようにお金がかかります。長い将来を考えると、できるだけ若いうちから「お金をためる・増やす」ことを意識したいものです。
しかし、「金融機関に預けても低金利だから、貯金してもあまりお金が増えない」と不満に思う方がいるかもしれません。
また「お金を増やす」方法として考えられる資産運用も、専門知識がないという理由でなかなか手を出しにくいと感じることも考えられます。資産運用商品にはリスクがありますが、「NISAを活用した積立投資信託」ならリスクを軽減しながら資産運用が可能です。
それでは、サラリーマンにおすすめの資産形成方法として「積立投資信託」と「NISA」を詳しく紹介します。「お金を増やしたい」と考える方はぜひ参考にしてください。
積立投資信託
積立投資信託なら、毎月定期的に決まった金額で金融商品を購入し、資産形成を図ることが可能です。少額の資金を長期間、分散投資することでリスクを軽減できるおすすめの運用方法です。
長期的に投資金額を増やしていくため、短期間では大きなメリットを得られません。しかし、長期運用による複利効果(運用で得た利益をふたたび投資することで得られる効果)により、次第に利益が積み重なっていくことが期待できます。
給与から無理のない金額で貯蓄できるため、リスクを抑えながら資産運用したいと考えるサラリーマンに適した商品です。
もっと詳しく知りたい方は、次の記事もぜひご覧ください。
NISA
運用益が非課税になる「NISA」は、積立投資信託と同じく、長期分散投資が可能で、リスクを軽減して運用ができるおすすめの制度です。
NISAを利用した積立投資信託は少額から可能で、分散投資による長期間での資産形成ができます。NISAを利用することで、投資信託から得られる利益が非課税で受取れるというメリットがあります。
まとまった資金がある方は、NISAの成長投資枠を利用した投資信託での運用もおすすめですが、運用が初めての方や、毎月無理なく少額から投資して資産を増やしていきたい方はNISAを利用した積立投資信託がおすすめです。
NISAは非課税期間が無期限で、NISAで運用している投資信託を売却すると、翌年以降非課税投資枠が復活するため、ご自身のライフステージに合わせて、一生涯利用できる制度といえます。売却タイミングは自由のため、子どもの学費や住宅購入、老後資金など目的に見合った資産形成ができます。
iDeCo
iDeCoは任意で加入する私的年金制度で、毎月積み立てる金額や運用方法などは加入者自身で決めることが可能です。この制度が生まれた背景には、景気の悪化や少子高齢化などがあります。従来のような退職金による保障では、人生100年時代を支えることが難しくなったと考えられるでしょう。
国民年金保険料を支払っていない人や農業者年金に加入している人など、加入できないケースもありますが、原則として20歳から64歳の人であれば加入できます。運用益の非課税、掛け金が全額所得控除になるなど、メリットの多い資産運用です。
これまでは、企業型DCの規約により、iDeCoに加入できない方もいました。しかし、2022年10月からは、企業型DCの定めに関係なく、原則iDeCoへの加入も可能です。
ただし、「積立投資信託」「NISA」「iDeCo」ともに、金融商品へ投資することに変わりありません。運用状況によっては値下がりで元本割れしてしまうこともあります。メリットとデメリットをよく理解したうえで、賢く活用することが大切です。
まとめ
サラリーマン全体の平均年収は約460万円で、そこから税金や社会保険料などを差引いた平均手取り額の概算は約368万円です。30代から40代へと年を重ねていくにつれ、収入は上昇していく傾向にあります。
しかし、結婚や出産、マイホーム購入、子どもの教育費など、ライフステージに合わせて出費が増えることを考慮しなければなりません。生活を維持する対策の一つとして、積極的に収入を増やすことも大切です。サラリーマンが収入を増やすには、昇進や資格手当の活用、副業などの方法があります。
また、お金を増やす方法の一つとして資産運用もあります。サラリーマンは毎月の安定した収入が見込めるため、計画的に収入や支出をコントロールして資産運用することが可能です。
ライフイベントにはまとまったお金が必要ですが、いきなり大金をためることはできません。無理をせずに、毎月一定額の投資信託をコツコツと積立てながら運用していく積立投資信託や、NISAを活用するのもおすすめです。
住宅資金の相談から保険に関わる相談、家計の見直しなど、自分では整理しにくかった内容も、専門スタッフがあなたのライフスタイルに合わせて一緒に考えます。
積立投資についても
詳しく見てみましょう!
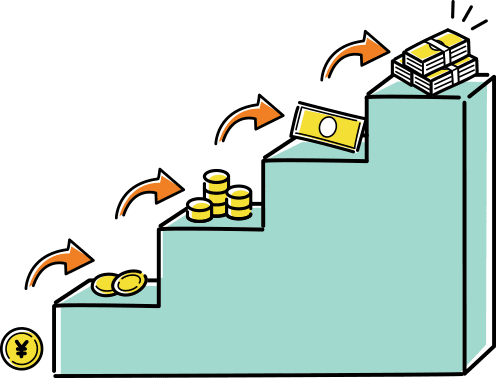
- こちらもおすすめ:
本記事は2025年3月10日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場や市場環境または制度の改正などを保証する情報ではありません。
NISAご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。
- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。
- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。