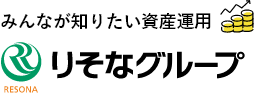公的年金の繰下げ受給で年金を増やす!繰下げ受給のメリットと注意点
公開日:2022/01/28
更新日:2025/08/15
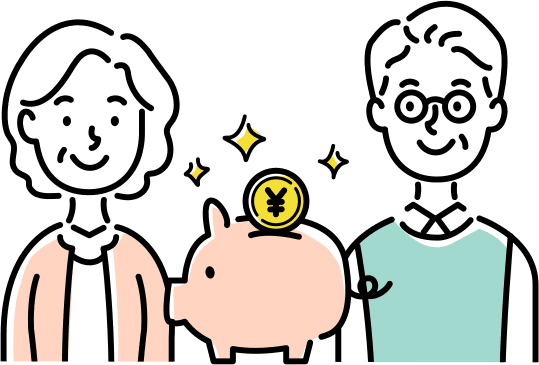
老後資金の柱となる公的年金の受給額は、基本的には現役時代の加入実績で金額が決まります。そのため、そこから大きく増やすことは難しいのではと感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、年金の受取り開始を本来の65歳からさらに遅らせる「繰下げ受給」を選択すれば、最大84%も年金額を増やすことが可能です。
このように繰下げ受給は、年金を増やすための有力な選択肢といえそうです。ただし、注意すべき点もあります。今回は、公的年金の繰下げ受給の基本やメリット、注意点、繰下げ受給を検討する際に重要となるポイントを解説。併せて、公的年金以外の老後に備えるための方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
公的年金繰下げ受給とは
まずは、繰下げ受給の対象となる年金、繰下げた場合の年金の増加率、手続きなど基本的なポイントをみてみましょう。
繰下げ受給できる年金の種類
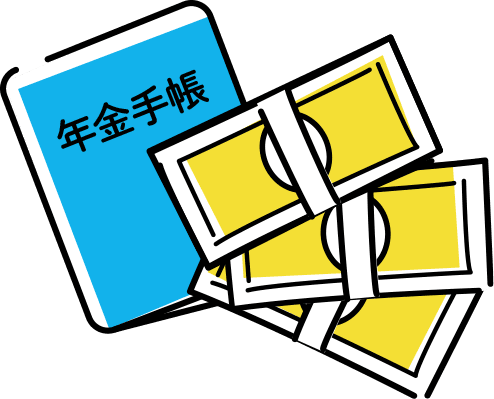
繰下げ受給の対象となるのは、原則として65歳から受取ることができる老齢年金のみ。遺族年金や障害年金は対象外です。
会社員や公務員の場合、老齢年金は加入期間に応じて決まる「老齢基礎年金」と、加入期間とその間の給与水準に応じて決まる「老齢厚生年金」の2階建てとなり、そのいずれか、もしくは両方を繰下げることができます。
なお、性別、生年月日によっては、「特別支給の老齢厚生年金」を受取れる人(※)がいますが、この部分は繰下げ受給の対象外です。
- ※男性では昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの方、女性では昭和41年(1966年)4月2日以降生まれの方には「特別支給の老齢厚生年金」はありません。
繰下げ受給した場合の年金増額率、手続き
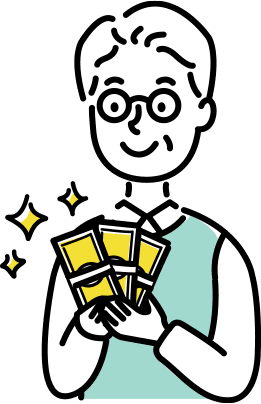
繰下げ受給の増額率(66~75歳)
| 請求時の年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4%~16.1% |
| 67歳 | 16.8%~24.5% |
| 68歳 | 25.2%~32.9% |
| 69歳 | 33.6%~41.3% |
| 70歳 | 42%~49.7% |
| 71歳 | 50.4%~58.1% |
| 72歳 | 58.8%~66.5% |
| 73歳 | 67.2%~74.9% |
| 74歳 | 75.6%~83.3% |
| 75歳 | 84% |
年金を繰下げ受給すると、本来の受給年齢である65歳から1ヵ月繰下げるごとに0.7%ずつ増額率が加算されます。例えば、70歳まで5年間繰下げると、42%の増加(=5年×12ヵ月×0.7%)です。なお、2022年4月からは最大75歳まで繰下げ可能となり、その場合は84%も増加します(※1)。
- ※11952年(昭和27年)4月2日以降生まれの人が対象
厚生労働省「令和7年度の年金額改定について」に記載された夫婦2人の標準的な年金額(※2)を参照すると、繰下げ受給を行った場合の年金額は概ね以下の通りです。
65歳から受取り(原則通り):23万2784円
70歳から受取り(5年繰下げ):33万553円
75歳から受取り(10年繰下げ):42万8322円
出典:「令和7年度の年金額改定について」(厚生労働省)(2025年7月23日に利用)
- ※2男性の平均的な収入[平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円]で40年間就業した場合に受取る老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)の給付水準
- ※あくまでも増加額をイメージするための試算であり、実際にはそれぞれの事情を考慮して算出されます。
年金の繰下げ受給を希望する場合、請求手続きをしなければ自動的に繰下げとなり、年金の受給を開始したい時に請求を行う仕組みとなっています。
繰下げ受給のメリット
~年金を大きく増やすことができる~
繰下げ受給のメリットは、やはり年金を大幅に増やすことが可能という点。さらには、増額となった年金を一生涯受取れる点も重要なポイントです。
前述した通り、公的年金の受給開始を75歳まで10年間先延ばしすることで、年金額を84%も増やすことができます。老後のための蓄えがある程度ある場合や、65歳以降も働いて収入がある場合などは、繰下げ受給を選択することで、「長生きによる老後資金の枯渇リスク」への不安を軽減することが可能です。
繰下げ受給の4つの注意点
ここからは、公的年金の繰下げ受給を行う際の注意点について解説します。
年金の増加率ほど手取りは増えない可能性がある
公的年金は、公的年金等控除が適用された後の金額が、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。所得税は所得が多くなるほど、多くなった分に対して高い税率が適用される仕組み(超過累進課税)です。
また、国民健康保険(75歳以上は後期高齢者医療保険)や介護保険の保険料は所得に応じて上がり、70歳以上が医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合も所得に応じて上がる制度となっています。
このため、税金や社会保険を考慮した場合、繰下げ受給により受取る年金額が増えても、負担も増えるため、増加率ほど手取りは増えないかもしれません。
加給年金が受取れなくなる
加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳になったときに、所定の条件を満たした場合に老齢厚生年金に上乗せされる形で受取れる年金のことです。老齢厚生年金における「家族手当」と考えると理解しやすいかもしれません。
加給年金を受取る条件としては、「厚生年金に20年以上加入していること」「条件を満たす配偶者もしくは18歳未満の子どもがいること」などが挙げられます。繰下げ受給の待機中は、この加給年金も受取ることはできないため注意が必要です。
遺族年金・障害年金は増額の対象外
前項の「繰下げ受給の基本」でも述べたとおり、遺族年金や障害年金は増額の対象外です。65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、遺族年金・障害年金を受取る権利がある場合、繰下げ受給の申請はできない点に注意しましょう。
また、亡くなった人が繰下げ受給によって増額された老齢厚生年金を受取っていた場合でも、その増額分は遺族厚生年金には引き継がれません。そのため、「繰下げ受給によって、自分の死後に配偶者が受取る遺族年金を増やせる」と誤解しないようにしてください。
在職老齢年金制度で減った分の額は増額されない
在職老齢年金制度とは、働きながら年金を受取る際、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超えた場合、老齢厚生年金の一部もしくは全額が減らされる制度のことです。
65歳以降も働く場合、賃金の額が高いと、老齢厚生年金を繰下げ受給しても、本来の年金全額を増やすことはできません。在職老齢年金制度により、減額後の老齢厚生年金が繰下げ受給の増額計算の対象となるためです。
したがって、65歳以降も高い賃金で働く場合は、在職老齢年金制度も留意しながら繰下げ受給を検討しましょう。
繰下げ受給の損得にこだわるべきではない
繰下げ受給は、長生きすればするほど受取額の総額が増えるため得になります。計算上は、65歳で原則通り受取った場合と比較すると、70歳まで繰下げた場合には81歳以降、75歳まで繰下げた場合には86歳以降受給額の合計が上回り、繰下げのほうが得となります。
逆に、繰下げ受給の開始後まもなく亡くなるようなケースでは、生涯における年金受給額という点で損となり、「もっと早く受取っておけばよかった」と後悔することにもなりかねません。
ただし、自身が何歳まで生きるのかはわからないだけに、このような損得の計算にこだわるのはあまり得策とはいえません。
また、前述の通り税金や社会保険も考慮する必要があるため、繰下げ受給の損得を厳密に計算することは困難です。
公的年金の最大のメリットは、一生涯にわたって受取れる安心感。老後の蓄えを取り崩していく場合、長生きによる枯渇リスクがありますが、繰下げ受給を選択すれば、増額された年金を一生涯受取れます。
今後は繰下げ受給が増加する可能性も
すでに65歳までの雇用確保が法律上、企業に義務付けられていますが、2021年度からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。今後は65歳以降も働くケースが増加するとみられます。65歳以降も働いて収入がある場合、その期間は年金を受取らずに足りない分はそれまでの蓄えを取り崩し、完全リタイア後に繰下げ受給をすることは有力な選択肢となりそうです。
65歳で仕事を辞める場合でも、しばらくの間はそれまでに築いた資産を運用しながら取り崩して生活費に充て、その後、繰下げ受給をすることも考えられます。
現状では、繰下げ受給を選択する人は多くありませんが、65歳以降も働くケースが増えれば、繰下げ受給も増加する可能性がありそうです。
繰下げ受給をすべきか悩むときの判断ポイント
繰下げ受給をすべきか悩む場合は、「自身の健康状態」と「今後の収入」という2つのポイントに注目してみましょう。
例えば、健康寿命を意識して元気なうちに受給をはじめる、もしくは健康に不安があるため受給をはじめる、というのも選択肢の一つといえます。逆に、「健康にはまだ自信があるから繰下げ受給をしよう」と考える方もいるはずです。
また、健康状態を踏まえる場合は、現在生じている医療費を考慮して判断することも大切です。65歳時点で医療費が継続的に生じている場合、繰下げ受給によって自己負担割合が増えてしまう可能性があります。
今後の収入を軸に検討する際は、65歳を超えても働く場合、賃金と老齢厚生年金の合計額をチェックし、前述した在職老齢年金制度の対象となるかどうか調べる必要があります。また、年金に頼らなくても生活できるほどの収入がある場合は、繰下げ受給を検討するのがおすすめです。
公的年金以外で老後に備えるための方法
年金の受給開始までまだ時間がある方や、年金以外で老後の資金が不足しないように備えておきたい方は、公的年金以外でも備えておくことがおすすめです。ここでは、公的年金以外で老後に備えるための方法を紹介します。
私的年金制度の活用
私的年金制度を利用することで、公的年金以外の年金を受取ることができます。私的年金制度として挙げられるのは、主に以下の3つです。
- 国民年金基金
- 付加年金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
国民年金基金は、自営業者などの第1号被保険者が加入できる年金制度で、基本となる終身年金に確定年金などを任意で上乗せして加入できる制度です。
付加年金は、国民年金基金と同様、第1号被保険者が国民年金保険料に付加保険料を加算して納付することで、老齢基礎年金への加算が受けられます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は国が設けた任意の私的年金制度で、掛金の運用の成果に応じて年金を受取ることが可能です。掛金の運用方法は加入者が決めます。
これらの制度を公的年金にプラスして活用することで、よりしっかり老後に備えることができます。
資産運用の活用
年金受給までの期間や資金に余裕がある場合は、資産運用をして老後の資金を確保するのも手段の一つといえます。
資産運用にはいくつかの種類がありますが、税制上の優遇措置が受けられることからNISA(少額投資非課税制度)が特におすすめです。
2024年1月から開始された新NISA制度の特徴は、口座開設期間の恒久化や非課税保有期間の無期限化などです。何年運用したとしても利益が非課税となるため、より長期的な資産運用に適しています。
まとめ
公的年金を繰下げ受給すれば、最大84%も年金額を増やすことができるため、今後、老後に備える有力な選択肢になりそうです。
ただし、繰下げ受給を検討する際は、税金や社会保険料、65歳以降の収入額や加給年金の有無も考慮する必要があります。また、繰下げ受給は長生きすればするほど得といえますが、そもそも自身が何歳まで生きるのかわからないため、厳密に損得を計算することは困難です。
公的年金は、生涯にわたって受取れるため、繰下げ受給の選択により増額された年金を一生涯受取れることは安心につながります。
このため、年金の繰下げ受給は、長生きした場合の資産の枯渇リスクへの対策として活用するのが1つの考え方といえます。
年金を繰下げる場合、年金を受取るまでの間、働くことで収入を得る、あるいは手持ちの資金をある程度取り崩すことを想定して、自助努力による老後への備えをしておくことが重要です。定年後、完全リタイアまでの間は、「NISA」等の税制優遇の制度をうまく活用した資産形成などを検討してみましょう。
りそなでは、60代以降の年金や退職金などのお金のセカンドライフや、老後を見据えた資産運用に悩む方からの相談を受け付けています。「年金・退職金についてアドバイスが欲しい」「今から老後に備えて何ができるのか考えたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
資産運用について相談する
本記事は2025年8月15日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。
NISAご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。
- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。
- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。