今後のiDeCo法改正のトピックを予習!制度が改悪されるって本当?
公開日:2022/11/07
更新日:2025/07/09
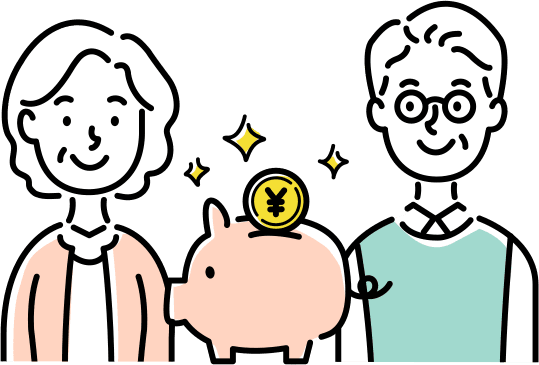
iDeCo(個人型確定拠出年金)は制度が導入されて以来、何度か制度改正されています。iDeCoに加入されている方だけでなく、これから加入を検討されている方にとってもiDeCoの今後の制度改正の予定は気になるのではないでしょうか。
また、iDeCoが「改悪される」と話題になっていることに対し、実際のところはどうなのか知りたい方もいるかもしれません。
しかし、iDeCoの加入者全員が改正の影響を受けるものではなく、そもそも自分がその対象なのかどうかを知ることが必要です。
本記事では、iDeCoの制度の目的と今後予定されている制度改正の内容・考え方について解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
iDeCoは次に何が
変わるの?

iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に、任意で加入できる私的年金の一つです。加入の申込みから掛金の拠出、運用商品選びまで自分で行い、その運用成果を一時金や年金として受取ることができます。
iDeCoでは拠出する掛金、運用益、そして給付金受取りの3つに対して優遇税制が設けられています。これは、iDeCoが多くの国民がより豊かな老後生活を送るための資産形成方法の一つとして位置づけられており、個々人による私的年金づくりをサポートするのが目的だからです。
老後生活が長期化するなか、政府はiDeCoをより使いやすい制度にするための取組みとして、これまでにも何度か制度改正を行っています。2024年12月には「令和7年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。そこで、今回は「令和7年度税制改正の大綱」におけるiDeCoの改正内容を解説します。
①iDeCo掛金上限額の
引上げ
勤務先における企業年金の有無や企業年金の形態の違いに関わらず、継続的かつ平等に資産を形成できる環境整備のため、iDeCoの掛金上限額が引上げられます。
第1号被保険者(自営業者など)の上限額は、iDeCoと国民年金基金の掛金を合わせ月額7万5,000円が上限となり、現行の月額6万8,000円から7,000円の増加です。
第2号被保険者(会社員・公務員など)は、企業年金等の有無に関わらず月額6万2,000円が上限となります。ただし、企業型DCや確定給付企業年金等に加入している場合は、それらの掛金との合計で月額6万2,000円までとなるため、注意しましょう。
第3号被保険者(専業主婦(夫)など)は、現行の月額2万3,000円から変更はありません。
掛金は全額所得控除の対象※のため、掛金額が増えることで、税制優遇が拡大します。また、より多くの運用益も期待でき、より税負担を軽くすることが可能です。
掛金額は一度決めたら変更できないということはなく、加入後も年に一度変更することができます。最初は少額でスタートし、途中から掛金額を増やすことも可能ですし、拠出が難しくなった場合は減額したり、積み立てをストップしたりすることも可能です。手元資金やライフプランによって、柔軟な拠出を検討しましょう。
- ※課税所得のある方のみ
②iDeCo加入可能年齢の
引上げ
高年齢者の雇用について、70歳までの就業機会を確保するよう制度改正された現状をふまえ、iDeCoへの加入可能年齢が引上げされます。
現行でiDeCoに加入できる年齢は以下のとおりです。
- ①第1号被保険者(自営業者等):60歳未満
- ②第2号被保険者(公務員・会社員等):65歳未満
- ③第3号被保険者(専業主婦(夫)):60歳未満
- ④国民年金任意加入被保険者:65歳未満
- ※①~③は国民年金被保険者であることが前提
これが、今回の制度改正によって①~④の全てが70歳未満まで引上げられる予定です。ちなみに、受給開始年齢は令和4年4月に75歳までに引上げされています。
今回の制度改正で、60歳以上70歳未満の現行のiDeCoに加入できない方のうち、以下の方が月額6万2,000円を上限として新たにiDeCoに拠出できるようになる予定です
- iDeCoの加入者または運用指図者であった方
- 私的年金の資産をiDeCoに移換できる方
- 上記いずれかを満たし、老齢基礎年金およびiDeCoの老齢給付金を受給していない方
加入可能年齢引上げにより資産形成期間が延長され、複利効果がはたらき運用益のアップも見込めます。すでにiDeCoに加入している方も加入期間を延長できるため、ライフプランに合わせてより柔軟な運用が期待できます。
本当に改悪?
③退職所得控除に関する
ルールの変更
令和7年度税制改正の大綱では、iDeCoにおける資産形成効果がアップする一方で、「改悪となる」という声も耳にします。これは、退職所得控除に関するルール変更があったためです。ここでは、その理由とポイントを解説します。
退職所得控除の仕組みとは
前述したように、iDeCoを一時金で受取る場合は退職所得控除が適用されます。以下の計算式で退職所得控除額の算出が可能です。
| 勤続年数20年以下の場合 | 40万円 × 勤続年数
|
|---|---|
| 勤続年数20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
iDeCoを一時金で受取る場合、上の計算式の「勤続年数」の部分は「加入年数」を当てはめます。
退職所得控除額は、勤続年数またはiDeCoの加入年数が長いほど多くなる仕組みです。所得から上記の控除額を差し引いた金額を元に課税退職所得が算出されます。
退職所得控除の増加、課税対象となる退職所得の減少となり、納税額の軽減につながります。
「5年ルール」から
「10年ルール」へ
一方、退職金とiDeCoの一時金の両方を受取る場合、退職所得控除の計算が上記式のとおりにならない場合があります。なぜなら、それぞれの受取り時期が一定期間空いていなければ、あとからの受取りとなる退職金(またはiDeCoの一時金)の退職所得控除を計算する際、本来の退職所得控除額より少なくなってしまうというルールがあるからです。
例えば、先にiDeCoの一時金を受取る場合、その後の退職金受取りが5年以上あとであれば退職所得控除枠をフルに活用できます。しかし、5年未満の場合は退職金を受取るときの控除額が減額されてしまうのです。これが、通称「5年ルール」です。
令和7年度税制改正の大綱では、この「5年ルール」が「10年ルール」に変更されます。
例えば、iDeCoの一時金を60歳で、退職金を65歳で受取るというパターンの場合、従来はそれぞれの受取り時に退職金控除枠をフルで活用できました。しかし10年ルールでは、iDeCoの一時金を60歳で受取った場合、退職金の受取りを70歳以降にしなければ、控除額が小さくなる可能性が高まるということです。退職金を70歳で受取るというのはなかなか現実的とは言えません。このように、税負担の増加が懸念されることから「改悪」と話題になっています。
本当に改悪なのか?
一方で、この改正は加入者全員に影響があるという訳ではありません。この改正に関係するのは、これまで「5年ルール」の対象になっていたケースで、先に「iDeCo」、次いで「退職金」の順に受取る場合です。そのため、両者の受取り対象年齢等を鑑みると、以下①②のいずれかに当てはまる方は、本改正の影響を受けないと言えます。
- ①iDeCoの一時金と退職金を同一年内に受取る方、または「退職金→iDeCo」の順番で受取る方
- ②iDeCoの一時金+退職金の合計が退職金控除の枠に収まる方
- ①iDeCoの一時金と退職金を同一年内に受取る方、または「退職金→iDeCo」の順番で受取る方
例えば60歳の定年退職時に退職金を受取り、同一年内にiDeCoの一時金も受取る方など、同一年内に双方の受取りをする方は、5年ルールや10年ルールに関係なく、そもそもiDeCoの一時金と退職金を合算して退職金控除枠を計算する必要があります。また先述の通り、本制度改正は受取りの順番が「iDeCo→退職金」の場合の話であるため、退職金を先に受取る予定の方には今回の制度改正の影響はありません。
ただし、退職金所得控除の制度上、受取りの順番を「退職金→iDeCo」とする場合でそれぞれに控除を適用させたい場合には、双方の受取りの間に20年以上期間を空ける必要がありますので、ご注意ください。
- ②iDeCoの一時金+退職金の合計が退職金控除の枠に収まる方
2つ目に関しては、それぞれを受取る期間がどれだけ空いているかにかかわらず、「退職金+iDeCo一時金の合計額」が退職所得控除の枠内であれば課税されません。例えば、38年間勤務した人は退職所得控除額が2,060万円(800万円+70万円×(38年-20年))となります。つまりこの例の場合では、退職金とiDeCo一時金の合計額が2,060万円までであれば全額控除の対象です。ちなみに、運営管理機関連絡協議会が公表している「確定拠出年金統計資料」によると、2024年3月末時点における60~69歳のiDeCo平均資産額は一人あたり約337万円でした。もしiDeCoの一時金が337万円だった場合、退職金額が1,723万円以内であれば、非課税ということです。もし控除枠を上回った場合でも、実際に課税されるのはその分だけとなるため、わずかな超過では税負担が急激に増えることはありません。退職金の金額は、勤務先によっても異なりますが、iDeCoと合算しても枠内に収まる可能性もあります。心配な方は、ご自身の場合で確認してみてください。
では、上記2点を確認した結果、課税が懸念される場合はどうすればよいのでしょうか。
例えば、60歳でiDeCoの一時金を受取るケースのほかに、60歳以降も働き続けてiDeCoの掛金拠出を続ける方法もあります。結局課税されるのであれば、65歳で退職金とiDeCoを一緒に受取るほうが、勤務期間が伸びることにより退職所得控除枠が増え、結果的に税制メリットが増すというケースも想定されます※。
ご自身の状況に合わせて、iDeCoの受取り時期や方法についてしっかりと計画することが大切です。
- ※詳細な税負担額は、税理士にご確認いただく必要がございます。
まとめ
令和7年度税制改正の大綱では、掛金の上限額が引上げられ、iDeCoに加入できる年齢も70歳未満まで拡大される予定です。退職所得控除に関する「5年ルール」が「10年ルール」に変更されることで、「税額負担が重くなる可能性がある」という側面のみがピックアップされ、大きな話題となりました。しかし、まずはご自身への影響はあるか、自分のケースと照らし合わせて確認することが大切です。
また、そもそも退職金制度やiDeCoの目的は、税軽減ではなく「老後の所得確保」であるということを忘れてはいけません。
iDeCoの受取り方は一時金だけでなく、運用しながら年金で受け取ることも可能です。
今一度本来の目的に立ち、あらためて老後の働き方や資産運用の方法、資金の受取り方などを検討してみてはいかがでしょうか。
りそなのiDeCoでは
- 運営管理機関手数料がだれでも0円
- 全国の窓口、コールセンターでプロに運用相談可能!
- 豊富な運用商品ラインアップであなたに合った商品が見つかる
- りそなのDC(iDeCo/企業型確定拠出年金)の利用者は約60万人超!実績豊富で安心!
など、運用初心者でも安心してiDeCoをスタートできる特徴があります。
将来のために、iDeCoでかしこく資産形成をはじめてみませんか。
- ※当記事は2025年7月現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。





