付加年金とは?月々400円で年金が増える?特長と留意点
公開日:2022/11/29
更新日:2025/08/22

「付加年金とはどのような制度なのか」「自分も加入したほうが良いのかよく分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
近年、将来の年金だけでは老後の生活に不安を感じる方が増える中で、「少しでも年金額を増やしたい」と考える方に注目されているのが「付加年金」です。
これは国民年金の加入者が、月額400円という少額の保険料を上乗せすることで、老後に受取る年金額を効率的に増やせる制度です。
受給開始から数年で納付した保険料の元が取れる仕組みとなっており、少ない保険料で将来の年金額を効率よく増やせるため、費用対効果に優れた資産形成手段として注目されています。
とはいえ、似た制度として「国民年金基金」もあり、違いや選び方に悩む方も少なくありません。
本記事では、付加年金の概要と国民年金基金との違い、付加年金のメリット・デメリットを中心に解説します。将来の年金額を増やす選択肢の一つとして、参考にしてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。
現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。
- ※りそなグループが監修しています
付加年金とは?加入するといくらもらえる?
まずは、付加年金とはどのような制度なのか、保険料や加入条件を確認しましょう。
付加年金とは
付加年金は、通常の国民年金に保険料を上乗せして納付することで、将来の年金額を増やせる制度です。
具体的な将来追加される年金額と、付加保険料の金額は以下のとおりです。
- 通常の年金に追加する保険料(付加保険料)……月400円
- 付加保険料を支払った場合に将来追加される年金額(年額)……200円×付加保険料を納めた月数
令和7年度の国民年金保険料は月1万7,510円なので、付加年金に加入すると月1万7,910円を支払うことになります。
付加年金の加入条件
付加年金に加入できるのは、「国民年金第1号被保険者」と「任意加入被保険者」限られます。つまり、対象となるのは自営業やフリーランスなど雇用されていない方や、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方などです。
また、国民年金に「上乗せ」する制度であるため、土台となる国民年金の納付を免除されている方は利用できません。また、「国民年金基金」との併用ができない点にも注意が必要です。
付加年金と国民年金基金の違い
付加年金と国民年金基金は、どちらも老後の年金額を増やす制度です。
国民年金基金は付加年金同様、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者などが対象ですが、付加年金と同時に利用することはできません。
両制度のおもな違いは以下表のとおりです。
| 付加年金 | 国民年金基金 | |
|---|---|---|
| 特長 | 2年以上受取るともとが取れる | 1口目は終身年金 2口目以降は自由にプランを選択可能 |
| 月の保険料/掛金 | 400円 | 加入時の年齢や性別、商品プランにより異なる ※上限6万8,000円 |
| 年間受給額 | 200円×保険料納付月数 | 口数やプラン、掛金による |
| 受給時期 | 原則、65歳以降 | 60歳または65歳以降 |
| 受給方法 | 年金形式 ※公的年金に上乗せ |
年金形式 |
| 控除の種類 | 社会保険料控除 | 社会保険料控除 |
付加年金の保険料は月400円と固定であり、将来は「200円×納付月数」の金額が年金に上乗せされます。一方、国民年金基金は加入時の年齢や性別、選択する商品によって掛金や年金額が異なるのが特徴です。
なお、国民年金基金は原則、中途解約ができません。また、国民年金第1号被保険者でなくなるなどで加入資格を失うと、脱退となる点に注意が必要です。
付加年金の3つのメリット
付加年金は、少額な保険料にもかかわらず、老後資金を効率よく増やせるため、コストパフォーマンスに優れます。将来の年金額を増やしたい方は検討するとよいでしょう。
ここでは、付加年金に加入することで得られる3つの具体的なメリットを解説します。
2年間受給すると納付した保険料のもとが取れる
付加年金は、短期間で支払額以上の年金を受取れるのが特長です。
仮に付加年金保険料を30歳から59歳までの30年間支払うと、支払う金額の合計は14万4,000円です。それに対し、1年間に受取れる年金額は7万2,000円となるため、受給が2年を超えると支払額を上回り、長生きするほど受取総額が増えていきます。
老齢基礎年金を繰下げると付加年金も同率で増額される
老齢基礎年金を繰下げると、1ヵ月ごとに年金額が0.7%増額されます。この増額は付加年金にも同じ割合で適用されるため、老後資金をさらに厚くすることが可能です。
ただし、繰上げ受給の場合は1ヵ月につき0.4%減額される点には注意しましょう。
保険料の全額が所得控除の対象となる
付加年金保険料は「社会保険料控除」の対象となり、全額を所得から差し引くことが可能です。所得税や住民税の負担を軽減しながら、老後資金を準備することができます。
付加年金のデメリット
付加年金はお得な制度ですが、以下の点に注意が必要です。
- 物価スライドがない
- 受給期間が短いと負担の方が上回ることもある
具体的に見ていきましょう。
物価スライドがない
通常の年金は、物価の変動に合わせて受取る金額が変わる仕組みになっています。しかし付加年金にはその仕組みがなく、定額です。受取るときにインフレで今よりも物価が上がっていたら、実質的な価値は目減りしてしまいます。
受給期間が短いと負担の方が上回ることもある
付加年金で元が取れるのは、受給開始から2年後です。65歳から年金を受取りはじめるとして、67歳までに亡くなってしまった場合は、支払った金額のほうが高くなります。
付加年金制度を利用するには

付加年金制度を利用する場合は、お住まいの市区町村役場の国民年金を担当している窓口もしくは年金事務所で申し出れば手続きができます。付加年金保険料は、自宅に届く納付書を使って銀行やコンビニなどで支払うこともできますし、口座振替やクレジットカード払いにも対応しています。
年金額を増やすならiDeCo(イデコ)の活用も!
老後資金を効率よく増やす手段として、iDeCo(イデコ)の活用も一案です。税制優遇を受けながら年金を増やせるため、付加年金と併せて検討してみてください。
iDeCoとは
iDeCoは、毎月の掛金を自分自身で運用しながら積立てていき、原則60歳以降に受取るしくみです。積立金額や運用方法、受取り方法などを自分で決めることができるため、自身のリスク許容度に応じて資産形成できる点で付加年金と異なります。
また、付加年金は将来の受給額が確定していますが、iDeCoは定額ではありません。自分で金融商品を選び運用するため、その結果によって受給額が変わります。さらにiDeCoは掛金が全額所得控除となり、運用益は非課税です。
- ※所得税・住民税の軽減効果は、ご本人の課税所得・掛金額により異なります。第3号被保険者など課税所得がゼロの方の場合、所得税・住民税の軽減効果はありませんので、ご注意ください。
付加年金とiDeCoを併用するときの注意点
付加年金とiDeCoは併用が可能です。併用する場合は、iDeCoの掛金と付加年金の保険料を合計して、月6万8,000円が上限に設定されています。
そのため、付加年金に加入すると、iDeCoの掛金上限が付加年金保険料の400円分減額される点に注意しましょう。
なお、iDeCoでは掛金を1,000円単位で設定するため、上限は月6万7,600円ではなく、月6万7,000円です。
まとめ
付加年金は、国民年金に上乗せして年金額を増やせる制度の一つです。
2年を超えて受給すると納付した保険料を上回るため、コストパフォーマンスに優れます。一方で、インフレに弱いなどのデメリットもあるため、メリット・デメリットを踏まえて検討するようにしましょう。
老後資金を準備する方法としては、iDeCoの活用も有効です。りそなのiDeCoなら、運営管理機関手数料や受取時手数料が無料であるため、コストを抑えながら将来に向けてつみたてることが可能です。ことが可能です。
運用益が非課税、掛金が所得控除の対象になるなど税制優遇もあるため、効率よく資産形成が期待できます。
資産形成がはじめてで不安のある場合は、運用を専門家に任せる「おまかせ運用タイプ」をぜひご検討ください。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)オンラインでかんたん!
相談しながら
- ※当記事は2025年8月22日現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値などは将来にわたって保証されるものではありません。







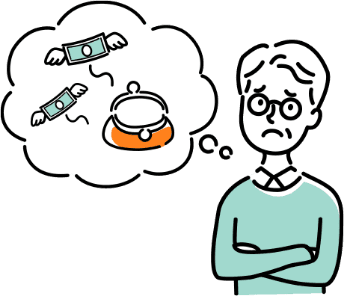
最後に、お客さまにご質問です。