終活とは?いつからはじめる?具体的なやり方・注意点
公開日:2020/03/30
更新日:2025/03/24
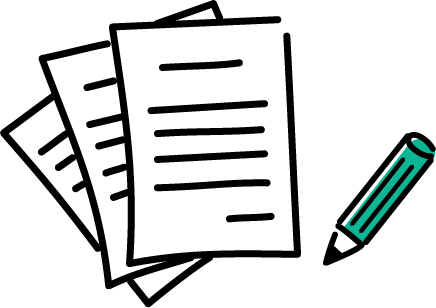
老後を迎える前に終活の必要性を感じているものの、「いつから何をはじめれば良いのか分からない」「何から手を付けるべきか迷う」と悩む方もいるのではないでしょうか。
終活は、いつからでもはじめることができます。財産の整理や遺言書の作成、お墓や葬儀の準備など、やるべきことは多岐にわたりますが、無理をせずできることからはじめるのが大切です。
この記事では、終活で行うべき具体的な内容や、スムーズに進めるための方法について詳しく解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。
現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。
- ※りそなグループが監修しています
終活の意味・
注目される背景とは
終活とは、人生の後半戦を楽しみ、自分の望む最期を迎えられるように元気なうちから準備をすることです。年齢を重ねるにつれ、老後の生き方や人生の締めくくり方を考えるようになる人も少なくありません。
また遺された人に、「精神的かつ金銭的な負担をかけたくない」という気持ちからも終活は注目されてきています。
終活が注目される背景にあるのは、少子高齢化や核家族化といった社会的な変化です。家族構成の変化により、人生の最終段階における準備を自ら進めることの重要性が高まっています。
また、終活は「最期(死)」に焦点を当てるだけでなく、「生きる」ことを前向きに考えるための活動でもあります。
誰しもが抱える老後の不安を解消し、自分の死についてポジティブに考えられ、より良い老後を過ごすことができるため、今では多くの人が終活を考えはじめています。
終活を行う3つのメリット
終活には複数のメリットがありますが、ここでは、主なメリットを3つ紹介します。
自分や遺される家族の不安が
払拭される
終活をすることで、自分で身の回りのことができなくなった場合でも、周りの人に考えや感謝の気持ちを伝えることができます。そのため、体力や気力が低下する前に終活を済ませておくことがおすすめです。
家族など周囲の人も事前に考えを知ることで、万が一の際でも慌てずに済むので大きな安心につながります。
故人の意思や情報がまったくない状態では、相続時の情報収集や煩雑な手続に追われ、争いごとに発展するかもしれません。そのため、終活は、家族にとっても不安や負担の軽減につながるというメリットがあります。
残された人生が充実し
前向きになる
終活で自分の考え方などを整理することで、残りの人生が前向きになる可能性が高まる点は、メリットです。
終末期や死後の希望をはっきりさせ、不安を小さくすることで、残された人生にエネルギーを注げるのではないでしょうか。
生活環境やお金に関することなど、自分の考え方を再認識できるため、残りの人生ステージにおける希望や理想なども考えられるようになります。
例えば、残りの人生で挑戦しておきたい趣味や、会っておきたい人に会うなど、人生でやり残したことの実現に向け、行動を起こすきっかけになりそうです。
気持ちや考えの整理に加え、不用品を生前整理するのもおすすめです。あらゆる物事が整理されることで、気持ちの面でも物質面でも終活前よりも快適に過ごせるようになるかもしれません。
遺産相続など家族間のトラブルを防げる
死後、遺産相続などの金銭トラブルが起こりやすく、仲の良かった家族でも関係がこじれてしまうケースは少なくありません。自分の死後に家族がいがみ合う状況は、誰もが避けたいものです。
そのため、財産の分配や相続方法をあらかじめ明確にしておくことが大切です。終活を通じて財産の分配などを整理しておけば、家族間のトラブルをある程度防ぐことができます。
終活はいつからはじめるのがベスト?

終活をはじめる時期は、老後に限られたものではなく、いつでもはじめることは可能です。例えば、次のようなタイミングで取りかかるケースがあります。
一般的に多い終活をはじめる
タイミング
終活をはじめるタイミングとして多いのが、人生の節目や身近な出来事を経験したときです。
定年を迎えると時間的な余裕が生まれるため、終活に取組みやすい時期といえます。
また、配偶者や友人など身近な人の死を経験した際には、自分の死後の手続について考えはじめるきっかけになることが少なくありません。
同様に、大病を患ったときや身近な人が病気になった際には、自分や家族の将来を考え、終活をはじめる動機となることがあります。
終活は気力や体力があるうちにはじめるのがベスト
考えたくないことですが、死は老いや病気に関係なく突然訪れることもあります。そのため、終活開始は年齢で考えるのではなく、思い立った時がベストなタイミングといえます。早ければ早いほど、気持ちに余裕をもって数ある選択肢から適した選択が可能です。
また、終活に「早すぎる」ということはありません。最近では、20代や30代といった若い世代でも終活をはじめる人がいます。
終活を進めるなかでは、財産分与の方法を明確にするなど、手間のかかる手続は避けられません。スムーズに進めるためには、気力や体力が十分にあるうちから準備を整えることが重要です。早めの行動が、自分の希望に沿った終活を可能にします。
終活は何をする?必要な準備と具体的なやり方
終活を行う場合、どのようにやっていけばいいか確認しておきましょう。
生前整理・財産整理
まずは、身辺や財産などの「生前整理」を行いましょう。資金使途や時期に応じてお金を色分けし、複数の金融機関に分かれている口座を集約します。「流動性」「安全性」「収益性」という、お金の3つの色分けをしておくと管理しやすくなります。
- 流動性:日常で使うお金など、いつでも引出せるようにしておくお金
- 安全性:使う予定が決まっていて元本が減ると困るお金
- 収益性:将来使うが、当面は使う時期がないお金
銀行が提供している資産承継信託などを利用すれば、「自分の将来にかかるお金」「家族に残したいお金」などを分けて管理できます。判断能力が落ちても、設定した条件で家族が代理で引出せるため、安心です。
さらに、財産以外の整理も重要です。不用品を処分しておくことで、遺された家族の遺品整理にかかる負担を軽減できます。
また、人間関係の整理も進めましょう。連絡を取りたい人や、今後もかかわりたい人を明確にしておくことで、終活をより充実したものにできます。
エンディングノートの作成
エンディングノートとは、家族や友人に対し、自分が万が一のときのために伝えておきたいことを書留めておくノートです。
決まった形式の書き方はなく、市販されているエンディングノートでも、自分で購入した一般的なノートに記載してもかまいません。書く内容は自由で、おおむね以下のようなものがあります。
- 自分史
- 財産一覧
- 葬儀やお墓の希望
- 家族や知人の連絡先、自分との関係
- 遺言書の有無
- 大切な人へのメッセージなど
自分の死後のことはもちろん、生前のことを記載しておくのもおすすめです。例えば、身体能力や判断能力に不安が生じた場合の介護に関する希望や、終末期医療に対する考えなども書き加えておくと安心です。
エンディングノートは、一度作成したら終わりではありません。希望が変わることや、家族構成や経済状況が変化する場合もあるため、定期的に内容を見直すことが大切です。
また、エンディングノートは自分の希望や情報を整理するためのものであり、法的効力はありません。
財産分与に関する事項や遺言執行者、祭祀承継者の指定などの希望を実行してもらうには、法的効力を持つ遺言書を作成する必要があります。これらを理解したうえで、エンディングノートを上手に活用しましょう。
遺言書の作成
相続争いを避けるためには遺言を作成しておくことも方法の一つです。遺言の方法には、次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で氏名・日付・遺言内容全てを書き、署名、押印して作成する。
添付する財産目録については、自書でなくてもよいとされているが、その場合は各頁に署名押印を要する。自ら保管してもよいが、自筆証書遺言保管制度を利用して遺言者本人が遺言保管所に遺言書の保管の申請をすることもできる。 - 公正証書遺言:公証人および証人(2名以上)の前で遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が筆記、各人が署名、押印して作成
- 秘密証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成封印し、封印された遺言書の封紙に公証人および証人(2名以上)が署名、押印
3種類のなかでは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がよく使われます。ただし、どのタイプの遺言書でも、記載する項目や形式が法律で決められており、条件を満たさないものは法的な拘束力がありません。その点は注意が必要です。
公正証書遺言は、費用が必要ですが公証人立ち会いのため、記入ミスによる無効の可能性を低くすることができます。遺言書を準備しておく主なメリットは、以下の3つです。
- 財産を自分の希望する人に渡すことができる
- 相続人同士での争いごとの防止につながる
- 財産名義変更の書類手続の手間が省ける
一方で、遺言書作成における注意したいポイントもあります。例えば、「遺留分の考慮」「遺言執行者の指定」といったものです。
遺留分は、子や配偶者などの法定相続人が最低限保証される遺産の取り分です。
遺言書によって特定の法定相続人が全ての遺産を相続するような事態となると、いくら被相続人の意思であったとしてもトラブルに発展しかねません。
そこで遺留分を侵害しないようにすることで、相続のトラブルリスクを避けることができます。
遺言の手続を行う遺言執行者は、受遺者や相続人でもかまいませんが、士業や信託銀行などの専門家に託しておくと安心です。
例えば、りそなでは遺言書の作成から執行までサポートしてくれるサービスを取扱っているため、一度相談してみてはいかがでしょうか。
お墓の準備
万が一に備えてお墓のことを考えておくと、費用や手間の面で家族の負担軽減につながります。主に考えておきたい内容は、以下の通りです。
- お墓を承継するのか
- 相続人はいるけど承継する家族がいない場合、改葬して新しいお墓を用意するのか
- 墓じまいをして永代供養のお墓をさがすのかなど
お墓の話は、縁起が悪いと感じる人もいるかもしれません。しかし、病気や介護状態の時に、お墓の話を積極的にしたいと思う人は少ないはずです。そのため、できるかぎり自分が元気なうちから検討しておくのがおすすめです。
お墓は、一人のものではなく代々の親族にも影響するため、自分のお墓に対する意思を事前に家族に伝えておくことが大切です。
葬儀の準備
鎌倉新書が行った「第3回お葬式に関する全国調査」によると、家族の葬儀で困ったこととして多かったのは、「心付けやお布施の額」が24%、「葬儀の手順」は15%、「通夜や告別式の接待の仕方や手順」が14%でした。生前に遺影の写真を用意したり、エンディングノートで希望を伝えておいたりすれば、万が一の際に家族も助かるでしょう。
葬儀にかかる費用の相場は、飲食費や返礼品を合わせて200万円前後です。加えて、死後整理では未払家賃の支払や不要な家財処分の費用が発生する可能性もあります。遺産分割が終わるまで、故人の口座から引出すのが難しくなる可能性があることも念頭に置いておきましょう。
実は2018年7月に民法(相続関係)が改正され、2019年7月以降は相続人間での遺産分割前でも最大150万円までは故人の預金を払戻すことが可能となっています。しかし、それでも払戻し請求のために銀行に提出する資料の収集等で時間がかかることが想定され、直ちに払戻しを受けるのが困難なことも考えられます。
このようなリスクを避ける方法の一つが「資産承継信託」です。あらかじめ受取人を指定しておくことで、本人の死亡後すぐに資金を受取ることができるため、速やかに葬儀費用にあてられます。
デジタルの終活も重要
デジタルの終活とは、SNSや画像など、インターネット上に蓄積されたデータを事前に整理しておくことです。
スマートフォンやパソコンに保存されているデータは「デジタル遺品」と呼ばれ、電話帳や写真、動画、メモなどのオフラインデータから、SNSアカウントやブログといったオンラインデータまで幅広く含まれます。
また、銀行口座アプリや株式等の証券口座、電子マネーなど、相続に関連するデータは「デジタル遺産」と呼ばれ、こちらも整理が必要です。
デジタルの終活を行わないと、自分の死後に家族がサービスやアプリを解約できず困る可能性があります。そのため、生前にIDやパスワード、SNSのアカウントなどを整理しておくことが大切です。
さらに、不要なデータの放置は情報流出のリスクを高めることから、デジタルの終活は個人情報を守るためにも必要な取組といえます。
おひとりさまの終活のポイント
おひとりさまの場合、自分の死後に備えて、血縁者以外が諸手続を行えるよう事前に手配しておくことが求められます。専門家への相談を通じて、必要な手続を進めましょう。
周囲にすぐに頼れる人がいない場合には、高齢者等終身サポート事業者を利用するのも一つの方法です。また、最近ではおひとりさまの終活をサポートするサービスも提供されています。これらを活用することで、より安心しておひとりさまの終活を進めることが期待できます。
終活をスムーズに進める
ための注意点
ここでは、終活をスムーズに進めるために知っておきたいポイントを2つ紹介します。
焦らず自分のペースで行う
終活には「いつまでにしなければならない」というルールはありません。無理をして急ぐと、ストレスになり健康に影響することもあります。そのため、少しずつ進めていくことが大切です。
また、短期間で終活を進めようとすると、自分の意に反した選択をしてしまうこともあるため、時間をかけてじっくり取組むようにしましょう。
家族や専門家の手を借りる
終活を進める際は、家族にも情報を共有し、必要に応じて手を借りることが大切です。そうすることで、家族とのコミュニケーションが深まり、後々のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
また、遺言書の作成や相続に関する問題については専門家に相談するのが重要です。疑問を解決できるだけでなく、条件を満たさないことで無効となるリスクを防ぐことができます。
終活に関するセミナーに参加するのも一つの方法です。家族以外から公平な意見を聞くことで、より適切な判断ができるようになるでしょう。相続税が気になる場合には、税理士等の専門家に相談するのも効果的です。
相続について考える際には、まず相続税の簡易シミュレーションを行ってみるとよいでしょう。基礎控除額や法定相続割合、遺留分といった基本的な情報を把握できます。
まとめ
終活は、元気なうちからはじめるのが理想的です。思い立ったときが最適なタイミングといえるでしょう。具体的には、生前整理やエンディングノートの作成、遺言書の準備、墓や葬儀の手配などが終活の主な内容です。
終活をスムーズに進めるには、焦らず自分のペースで取組むことが大切です。また、家族や専門家に相談することで、安心して進められる環境を整えましょう。
りそなでは、遺言書の作成から執行についても丁寧にサポートを受けることが可能です。終活が気になっている人は、まずは一度店頭で相談してみてはいかがでしょうか。
本記事は2025年3月24日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等または制度の改正等を保証する情報ではありません。





