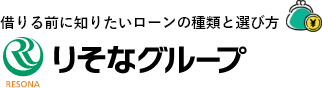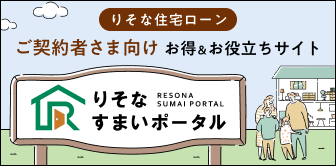防災グッズと災害補償|災害時の備えに本当に必要なものとは
公開日:2019/09/19
更新日:2025/09/25
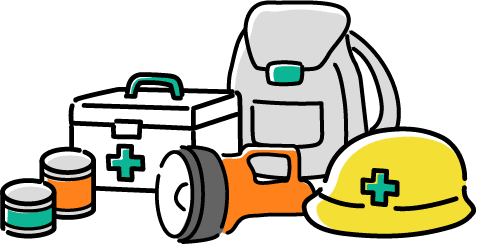
防災グッズを準備しておこうと思っていても、「本当に必要なものが何なのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
防災グッズを用意する際は、まず飲料水や非常食などの準備が必要です。家族構成によっても揃えるべき防災グッズは異なるため、確認したうえで準備しましょう。
本記事では、防災グッズに必要なものや備蓄しておくべき水や食料の種類や量について解説します。また、防災グッズ以外に必要な確認項目や、災害補償についても紹介しますので参考にしてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
災害の備えで用意すべき防災グッズはどんなもの?
最初に準備しておきたいのは、非常用持出品です。必要なものを確認し、自宅にないものがあれば購入しておきましょう。
非常用持出品とは?
避難時に自宅からまず持ち出すべきものを「非常持出品」と呼びます。
非常用持出品は、災害発生時にすぐ持ち出せるようにリュックのような両手が使えて持ちやすいバッグに詰め、寝る場所の近くや玄関先に置いておきましょう。
また、非常時に1人が持ち出せる量は限られています。各個人が持ち運べる分量は10kg~15kg※が目安ですので、必需品を中心に準備し、リュックが複数個になる場合には、「誰が何を持ち出すか」について家族で担当を決めておきましょう。
- ※横須賀市「非常用持ち出し品・非常用備蓄品の準備」
持ち出し袋に入れておきたい防災グッズ
災害時に最低限必要なものは主に以下のものです。持ち出し袋に入れておきましょう。
| 【必需品】 |
|
|---|---|
| 【安全・情報】 |
|
【快適・便利】余裕があれば加えたいもの
- ライター、マッチなど
- めがね(ないと困る場合)
- 笛(居場所を知らせることができる)
- 筆記用具(紙、ボールペン、油性マジックなど)
- 万能ナイフ
- ビニール袋
- ビニールシート
- 毛抜き(とげ抜き、ピンセットとして使える)
- くし、ブラシ、鏡
- ゴム(避難時に髪を洗えない場合に、髪の毛をくくると不快感が薄れます)
家族構成によって異なる防災グッズ
家族の人数や性別、乳幼児や高齢者がいるかどうかによって、非常用持出品の種類や量は変わります。家族構成や状況に合わせて、次に紹介するものを防災グッズに加えましょう。
| 女性がいる場合 |
|
|---|---|
| 乳幼児がいる場合 |
|
| 高齢者がいる場合 |
|
ペットがいる場合の防災グッズ
ペットがいる場合は、避難先でペット同行が可能か、事前に自治体へ確認することが大切です。避難所への同行可能な場合は、以下を非常用持出品として用意しておきましょう。
- ペットフード、水、療法食などの特別食を最低5日分(7日以上が望ましい)
- 常備薬
- キャリーケース など
また、避難所への同行をスムーズに行えるように、「平時からケージに慣れさせる」「基本的なしつけを身につけさせる」など、ペットと飼い主双方のストレスを軽減するための準備も重要です。
避難所では、動物が苦手な方や動物アレルギーの方への配慮も忘れてはいけません。鳴き声や排せつ物でのトラブル防止のためにも日頃のしつけが災害時の備えにつながります。
ペットが迷子になる可能性も考慮して、ペットの写真、ワクチン記録、マイクロチップ情報の保管、避難ルートの下見なども忘れずに行っておきましょう。
防災グッズで用意すべき水・食料の量や種類とは?
避難生活を送るうえで必要となる水や食料などの物品を「非常用備蓄品」と呼びます。大災害が起こると、ガス、水道、電気、通信が止まる可能性があるため、ライフラインがなくても自力で過ごせるように、非常用備蓄品を普段から準備しておきましょう。
用意すべき食料の量はどのくらい?
大規模災害が起こった直後の3日間は、人命救助が優先されます。そのため、この3日間は公的支援を期待できない可能性が高いと考え、「3日分×家族の人数」※を目安として、水や食料品などの備蓄をするのが理想です。ただし、大規模災害発生時には、「1週間分」※の備蓄が望ましいとされています。
- ※首相官邸「防災の手引き」
飲料水は1人につき何リットル用意すればいい?
水は、人間の生命維持に欠かせないものです。人間が生命を維持するために必要な飲み水は、成人の場合で1日2~2.5リットルといわれています。災害の備えとしては、これに少し余裕をもたせた3リットルを1日あたりの備蓄量※と見積もっておきましょう。
理想は3日分の備蓄ですから、1人あたり「1日3リットル×3日分」で9リットル※が目安です。しっかりと家族の人数分の備蓄を心がけましょう。なお、飲料水も大災害時には1週間分の備蓄※が望ましいとされています。
- ※首相官邸「防災の手引き」
災害の備えで水を用意する際の注意点
飲料水だけでなく、断水時の対策として、トイレなどに使う生活用水のことも考えておかなければなりません。
トイレ、洗濯、掃除に使う水は飲料水とは違い新鮮である必要はないため、普段お風呂に入ったあとの残り湯をそのまま浴槽にためておくのもおすすめです。ためた生活用水は、火災発生時の消火用にも使えます。
災害時に自治体の救護体制が整うと、各拠点で給水を受けられますので、ふたのできるポリ容器を数個、各家庭で用意しておきましょう。
災害の備えで食料を用意するときのポイント
災害時にライフラインが止まると、調理ができなくなる可能性があるため、調理が不要なアルファ米やレトルトご飯、缶詰や、そのまま食べられるチーズやかまぼこ、栄養補助食品、お菓子を備蓄しておくのもおすすめです。
避難場所で配給される食料品は、食べやすいおにぎりやパンなどの炭水化物が中心となることが多くなります。しかし、健康状態を維持するためには、災害時でも栄養のバランスを考えることも大切です。魚や野菜の缶詰、冷凍食品など、タンパク質や食物繊維を摂取できるよう最低限揃えておきましょう。
電気やガスが止まることを想定し、カセットコンロやラップ、アルミホイル、缶切りやハサミとしても使えるマルチツールも用意しておくとより安心です。
備蓄ルールとローリングストック
家族の人数によっては非常用備蓄品の量が多くなることが考えられます。たとえば、5人家族の場合では「1日3食×3日分×5人分」※となり、45食分もの食料品の買い置きが必要です。飲料水であれば「1人3リットル×3日分×5人分」※で45リットルが必要で、2リットル入りのペットボトルなら23本程度です。
- ※首相官邸「防災の手引き」
これらをまとめて購入するのは費用がかかるうえ、ストック場所や賞味期限の問題もあります。このような問題を解消するのが「ローリングストック」です。ローリングストックとは、普段から食べている食材や加工品のなかで備蓄できそうなものを少し多めに買い、食べた分だけ買い足していく方法です。
この方法だと、常に一定量の食材を備蓄でき、消費と購入を繰り返すため鮮度も保つことができます。ローリングストックは、食料品だけでなくトイレットペーパーや乾電池、常備薬、ビニール袋、カセットコンロ用のガスボンベなどほかの備蓄品にも応用できるので、非常時に備えて日用品もストックしておきましょう。
防災グッズ以外にも確認を!
災害が起こる前にチェックしておきたいこと
一人ひとりが自分の身の安全を守れるよう、家のなかの安全対策も忘れずに。
自宅内の家具・小物の移動
まず、自宅内の家具、小物の配置を確認しましょう。枕元には懐中電灯やスリッパを置いておくことで、就寝中に災害が起こってもスムーズに避難しやすくなります。また、枕元にかけ時計や額縁がある場合は、揺れが起こったときに頭上に落ちないよう、落ちても安全な場所へ移動させておくと安心です。
タンス・本棚・食器棚では重いものを下に、軽いものを上に入れるようにすると重心が下に移動し、災害時の転倒防止につながります。
家具の置き方
避難経路がふさがれないように、大きな家具は出入りの少ない部屋にまとめて置いたり、出入口から離れたところに置いたりしましょう。ベッド上への転倒防止のため、寝室には家具を置かないのが理想です。どうしても置きたい場合は、家具をしっかり固定してください。
避難経路、避難場所の確認
豪雨、津波、火山噴火など、災害の種類によって安全な避難場所が変わってきます。防災マップやハザードマップは、自治体や国土交通省のホームページから入手できますので、居住している環境に応じて起こりうる災害をイメージし、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。
安否確認方法
災害は、家族が揃っているときに発生するとは限りません。学校、職場、買い物時など、家族が別々の場所にいるときに災害が発生した場合を想定し、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板の使い方、集合場所を家族で事前に話し合っておきましょう。
いざというときのための災害補償「地震保険」と「火災保険」とは
不運にも被災してしまい、自宅が全焼・全壊してしまったら…、あなたはどうしますか?リフォームでまかなえる程度か、新しく建築・購入しないといけないレベルか、被災状況に応じて考えることになると思いますが、いずれにしても莫大な費用がかかることが予想されます。まだ住宅ローンが残っている場合は、新しく建てる自宅分とあわせて、二重で住宅ローンをかかえることになる可能性もあります。
このような災害補償を受けられる保険として活用できるのが地震保険や火災保険です。しかし、これらの保険だけではすべての損害をカバーできない場合があります。万が一のときの不安を解消するためにも、前もって確認してから申込みしましょう。
【地震保険】地震や噴火、津波などによる損害をカバー
地震保険は、地震(地震による火災を含む)や噴火、津波による建物や家財の損害を補償する保険です。例えば、自宅の焼失や損壊、埋没または流失などの被害が補償されます。
火災保険では、地震が原因で発生した火災や損壊は補償対象外となるため、地震による火災に備えるためには地震保険への加入が不可欠です。ただし、地震保険は単体では加入できないため、火災保険とともに契約する必要があります。
地震保険による補償範囲は、居住用建物と家財です。これらが被災すると、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で認定が行われ、それぞれに保険金額の100%・60%・30%・5%が保険金として支払われます。
なお、地震保険の保険金額は、火災保険金額の30~50%の範囲内で設定するため、完全な再建費用をカバーできない場合があります。東日本大震災や熊本地震のような大規模災害では、多くの家屋が倒壊し、住宅ローンと新居購入費用の二重負担に苦しむ被災者が続出しました。
【火災保険】火災・風災・落雷・水災などによる損害をカバー
火災保険は、火災をはじめとする災害から建物や家財を守る保険です。一般的に、火災のほかにも雪災やひょう災といった自然災害や、ガス爆発などによる破裂も補償の対象です。
しかし、地震や噴火、津波による火災は火災保険では補償されません。そのため、いざというときの災害補償としては、地震保険と火災保険をセットで加入することが重要です。
まとめ
地震や台風、豪雨などの自然災害がいつ起こるかわからない現代において、防災グッズ、火災保険や地震保険への加入は重要な備えです。事前準備をしっかりとして、大切な自宅や家財の災害リスクに備えましょう。
火災保険や地震保険への加入を検討されている方は、どこで申込みをすればいいか迷ってしまうかもしれません。そんな時は、物件の不動産屋、信用度の高い大手銀行の窓口でご相談してみてはいかがでしょうか。
窓口相談では、一人ひとりの異なる状況に合わせて具体的にアドバイスをしてもらえるので、より一層の安心につながるでしょう。
また、金融機関のなかには被災時のローン返済をサポートするサービスを提供しているところもあります。例えば、りそなの「自然災害サポートオプション」では住宅ローン対象の建物が所定の自然災害に罹災した際、住宅ローン返済額の一部の払戻し、または残高の一部免除を受けることが可能です。
「自然災害サポートオプション」は、りそなの住宅ローンの契約時だけでなく途中加入もできます。防災グッズ準備や保険での備えとともに、ぜひ加入を検討されてはいかがでしょうか。
※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ
本記事は2025年9月25日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。