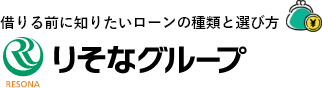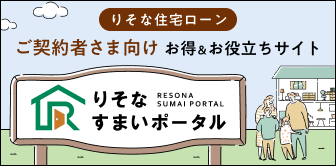【2025年版】住宅ローン控除(減税)とは?仕組みと改正ポイント・計算方法
公開日:2019/09/19
更新日:2025/12/23
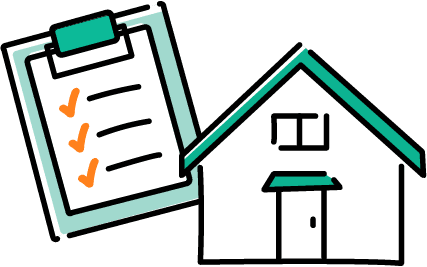
住宅ローン控除(減税)の概要や要件、具体的な控除額を知りたい人もいるのではないでしょうか。
住宅ローン控除(減税)とは、一定条件を満たすと、13年間または10年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる制度です。適用されるための要件や控除額は、住宅の種類や申請者の所得などによって異なります。
この記事では、住宅ローン控除(減税)の概要および2025年改正のポイント、適用を受けるための要件、具体的な控除額、住宅ローン控除(減税)の手続き方法と手続きを忘れた場合の対処法を解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
住宅ローン控除(減税)
とは
住宅ローン控除(減税)とは、償還(返済)期間10年以上の割賦償還方式により返済する住宅ローンがある場合に一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる制度です。
所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除が行われます。控除により税金の還付を受けられますが、自分が納めた税額以上に戻ってくることはありません。
この制度は、「住宅ローン控除」あるいは「住宅ローン減税」と一般的に呼ばれますが、正式な名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除は適宜改正が行われているため、これから住宅の購入と住宅ローンの利用を検討している場合は、最新の情報を確認しておきましょう。
【2025年】住宅ローン控除(減税)制度の改正ポイント

2025年の税制改正では、基本的に2024年に改正された住宅ローン控除(減税)の内容を引き継ぐ形で改正されました。それぞれの改正点について説明します。
省エネ基準を満たさない住宅は原則、控除適用外に
2024年の改正時から、新築住宅のうち省エネ基準を満たさないものが控除適用外となりました。借入れの対象となる住宅が、2024年1月以降に建築確認を受けた新築の場合、エネルギー消費量や断熱性能などの省エネ基準を満たした住宅でなければ、住宅ローン控除は引き続き適用されません。
地球温暖化などの課題解決に向け、国は住宅においても省エネルギー対策を強化しています。その一環で2022年に建築物省エネ法が改正され、2025年4月からはすべての住宅に対して省エネ基準適合が原則義務付けられています。
省エネ基準を満たさない住宅でも、以下のいずれかに該当する場合は「借入限度額2,000万円・控除期間10年間」の住宅ローン控除(減税)が適用されます。
- 2023年中に建築確認を受けている場合
- 2024年6月30日までに工事が完了した場合
新築・買取再販の借入限度額の
引下げ
2024年の改正で新築および買取再販住宅において500万~1,000万円ほど縮小された借入額上限が、2025年改正でもそのまま維持されます。買取再販住宅とは、不動産会社が一度取得した中古住宅を、リフォームしてから販売する住宅のことです。縮小額は以下のように、住宅の種類によって異なります。
- 【住宅の種類ごとの縮小額】
-
横スクロールできます。
住宅の種類 借入限度額 縮小額 2022・2023年 2024・2025年 長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 500万円 ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円 1,000万円 省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円 1,000万円 その他の住宅 3,000万円 0円(適用外) 3,000万円
実際に住宅ローンを借入れする際は、上表中の借入限度額を超えてしまう場合もあるかもしれません。その場合、住宅ローン控除(減税)の対象となるのは表中の借入限度額までとなり、上限を超えた部分は住宅ローン控除(減税)の対象外です。
なお、中古住宅に関しては借入限度額が改正されておらず、長期優良住宅ほか省エネ基準適合住宅では3,000万円、その他住宅では2,000万円が上限です。
子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額の縮小が見送りに
2024年改正に引き続き、2025年の改正でも子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の縮小が見送られました。子育て世帯に対する支援強化や急激な住宅価格の上昇を背景に、子育て世帯および若者夫婦世帯に関しては、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」を除き、先述した借入限度額の縮小がされません。
2025年の入居でも、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の場合、それぞれ上表にある2023年までの借入限度額が維持されます。
なお、子育て世帯とは19歳未満の子どもがいる世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のうちいずれかが40歳未満の世帯です。
新築住宅の床面積要件の緩和措置における建築確認期限の延長
新築住宅における床面積要件も、2024年に引き続き緩和措置が継続されます。それに伴い、建築確認の期限が1年延長されることになりました。
この緩和措置とは、床面積が50平方メートル以上の住宅が住宅ローン控除(減税)の対象となっているところ、合計所得金額1,000万円以下の人が新築住宅の購入をする場合には、床面積要件を40平方メートル以上に緩和するというものです。
この緩和措置では、建築確認を2024年12月31日までに受けたものが対象となっていましたが、建築確認を2025年12月31日までに受けたものへと変更されました。
- 【改正内容を含む主な要件】
-
- 自らが居住するための住宅であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上あること。2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅に関しては、合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上であること
- 住宅ローンを借りた人の合計所得金額が2,000万円以下であること。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は合計所得金額1,000万円以下であること
- 住宅ローンの割賦償還方式による返済期間が10年以上であること
- 引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居したこと
贈与税の非課税措置の延長
住宅ローン控除(減税)ではありませんが、2024年の税制改正では、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の適用期限が、2026年12月31日までに延長されました。この制度により、一定要件を満たす住宅を取得するための資金を直系尊属(親や祖父母)から援助してもらう場合に、一定額までの贈与税が非課税となります。非課税限度額は、取得する住宅の種類に応じて金額が異なり、以下のとおりです。
- 耐震・省エネ・バリアフリーなどの住宅:1,000万円
- その他の住宅:500万円
【2025年】住宅ローン控除(減税)の要件
住宅ローン控除(減税)が適用されるためには、一定条件を満たさなくてはいけません。その条件の内容は、取得する住宅が新築か中古か、増改築のようなリフォームかで異なります。
2025年以降、新たに住宅ローン控除(減税)の適用を受ける場合の、それぞれの適用条件を見ていきましょう。
共通の要件
取得する住宅の種類にかかわらず、次の条件を満たすことが必要です。
- 1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日または工事の完了から6ヵ月以内に居住し、引き続き居住していること
- 2.特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
※ただし、合計所得金額1,000万円以下で、2025年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合は、住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満 - 4.対象となる住宅に対して割賦償還方式による返済期間が10年以上にわたるローンがあること
- 5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
- 6.省エネ基準に適合していることを示す証明書として「建設住宅性能評価書」または「住宅省エネルギー性能証明書」の交付を受けていること(2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合)
なお、売買契約書と登記簿上では、算出方法の違いによって床面積が異なる場合があります。床面積は登記簿に記載された数字で判断されるため、住宅ローン控除を利用する際には注意しましょう。
新築住宅の場合
購入する住宅が新築住宅である場合、共通条件を満たしたうえで、省エネ水準基準を満たすことが必要です。省エネ水準基準を満たさない「その他の住宅」に該当する場合は「2023年12月31日までに建築確認を受けている」または「2024年6月30日までに建築されたものである」という要件を満たしている必要があります。
また、新築住宅の場合、住宅の種類によって控除(減税)の対象となる借入限度額が異なります。各住宅の特徴は以下のとおりです。
- 長期優良住宅:長期間良好な状態で住み続けられるための措置がされている住宅。着工前に所管行政庁へ申請することが必要です。
- 低炭素住宅:二酸化炭素の排出を抑える仕組みのある住宅。着工前に所管行政庁(都道府県、市または区)による認定を受けることが必要です。
- ZEH水準省エネ住宅:高い断熱性能と高効率な設備を活用し、室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現させる住宅。ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指す住宅を示します。
- 省エネ基準適合住宅:日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上の性能を持っている住宅。
- その他の住宅:上の基準を満たさない住宅。
買取再販の場合
買取再販住宅では、新築住宅の適用条件以外に、以下の条件も満たさなければなりません。
- 1.宅地建物取引業者から住宅を取得していること
- 2.宅地建物取引業者が住宅を取得し、リフォームを行い再度販売するまでが2年以内であること
- 3.取得時点で、新築日から10年経過した住宅であること
- 4.建物価格に対し、リフォームの工事費用が20%以上を占めること
- 5.大規模修繕や耐震基準に適合するための工事、バリアフリー改修、省エネ改修など、対象となる工事が行われていること
買取再販住宅で住宅ローン控除の適用を受ける際には、工事内容やリフォーム費用に関する細かい条件があります。買取再販住宅の購入を検討する場合は、住宅ローン控除の条件を満たした物件なのかを販売業者へ事前に確認しましょう。
中古住宅の場合
中古住宅では、建築された時期や耐震基準の適合の有無によって、住宅ローン控除(減税)の対象となるかが決まります。共通の要件に加え、以下のうちいずれかの条件をクリアする必要があります。
- 1.1982年1月1日以降に建築された住宅であること
- 2.現行の耐震基準に適合していること
1981年以前に建築された中古住宅については、耐震基準を示すために耐震基準適合証明書などが必要です。
リフォーム・増築の場合
リフォームや増築では、新築住宅の適用条件以外に、以下のうちいずれかの工事に該当することも条件とされています。
- 1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり・屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
- 2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う修繕・模様替えの工事
- 3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
- 5.バリアフリー改修工事
- 6.省エネ改修工事
なお、これらの工事費用の額は100万円を超えなければなりません。一つの工事にかかった金額で判断されるため、改修工事を2回に分けて行った場合には注意が必要です。
リフォームや増築に関する条件は複雑であり、新築住宅や中古住宅の購入時と比較して注意すべきポイントが多くあります。自宅のリフォームに際して、住宅ローン控除の利用を検討する場合は、専門家への早め相談がおすすめです。
住宅ローン控除(減税)の対象となるローン等の条件チェックも忘れずに

住宅ローン控除では、先ほど紹介した以外にも、ローンに関しての適用条件があります。すべての条件を満たす必要があるため、きちんと確認しておきましょう。
控除対象となる
住宅ローンの条件
住宅ローン控除を受ける場合は、合計所得金額が2,000万円以下であること、割賦償還方式による返済期間が10年以上であること以外に、以下の条件を満たす必要があります。
- 自己居住用の住宅とその敷地を取得するための借入れで、一体として借入れられていること
- 借入れは以下6つのいずれかからであること
- 1.銀行
- 2.農協・信用金庫・信用組合
- 3.住宅金融支援機構
- 4.地方公共団体
- 5.各種公務員共済組合
- 6.勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上であること)
ただし、親族や知人などの個人、自身が役員となっている企業や親族の会社からの借入金は対象にはなりません。
他の特例との関係も
要チェック
ここまでの条件を満たしていても、他の特例との兼ね合いで、住宅ローン控除が適用できないケースもあります。例えば、住宅にまつわる所得税控除には、特定居住用財産の買換え特例や3,000万円特別控除がありますが、これらが適用された場合には原則として住宅ローン控除は利用できません。
そもそも、住宅ローン控除は課税されるべき所得税がなければ利用できないものです。住宅にかかる税制度は条件や手続き方法が複雑なため、不明な点は税理士などの専門家に確認してみましょう。
住宅ローン控除(減税)で一体いくら税金が戻ってくるの?
実際に、住宅ローン控除が適用されると、どれくらいの税金が軽減できるのでしょうか。ここでは、具体的な控除額を紹介します。
住宅ごとの最大控除額
住宅ローン控除での最大控除額は、住宅の性能や適用年により異なります。
横スクロールできます。
| 住宅の種類 | 居住開始年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 合計 | ||||||
| 新築住宅・買取再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 2024年 | 4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円) | 0.70% | 13年 | 31.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯35万円) | 409.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯455万円) |
| 2025年 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.万円 | ||||
| ZEH水準省エネ住宅 | 2024年 | 3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯4,500万円) | 24.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯31.5万円) | 318.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯409.5万円) | |||
| 2025年 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 | ||||
| 省エネ基準適合住宅 | 2024年 | 3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯4,000万円) | 21万円(子育て世帯・若者夫婦世帯28万円) | 273万円(子育て世帯・若者夫婦世帯364万円) | |||
| 2025年 | 3,000万円 | 273万円 | |||||
| その他の住宅 | 2024年~2025年 | 住宅ローン控除は適用されません | |||||
| 既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 2022年~2025年 | 3,000万円 | 0.70% | 10年 | 21万円 | 210万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | ||||
| リフォーム | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | ||||
一見複雑そうですが、ご自身が購入する住宅の種類や入居時期がわかれば、計算自体はシンプルです。また、最大控除額の合計はあくまでも目安であり、通常は毎年ローン残高が減っていくため、控除額も年々変化します。
これから住宅ローンの利用を検討する方は、まずは金融機関のホームページから借入れシミュレーションを行い、各年末の残高状況を調べてみましょう。
なお、住宅ローン控除は、本来払うべき所得税から直接引くことができる税額控除です。住宅ローン控除可能額より本来の所得税額が少ない場合は、控除可能額のすべてを利用できません。
残額部分は翌年の住民税から控除されますが、住民税からの控除額にも最高9.75万円と上限があります。住宅ローン控除では、所得税・住民税の上限を超える控除が受けられないことを理解しておきましょう。
住宅ローン控除(減税)
の計算方法
住宅ローン控除では、以下2つのうちいずれか低い金額が、所得税や住民税から毎年控除されます。
- 年末時点の住宅ローン残高(※)×0.7%
- ※住宅の取得等の対価の額または費用の額(注)のほうが少ない場合は、その取得等の対価の額または費用の額
注:所定の補助金や贈与等の金額が控除される場合があります。詳しくは管轄の税務署までお問合せください。
- 1年間の最大控除
例えば、長期優良住宅や低炭素住宅の新築で2024年入居の場合、1年間の最大控除額は以下の計算式のとおり31.5万円です。
長期優良住宅・低炭素住宅の最大控除額:4,500万円×0.7%=31.5万円
しかし仮に、年末時点での住宅ローン残高が4,000万円とすると、残高から計算した控除額の上限は4,000万×0.7%=28万円になります。31.5万円よりも金額が低いため、控除を実際に受けられるのは28万円までです。
いくら戻るか調べるならシミュレーションを行う
控除可能額の考え方を理解したうえで、所得税や住民税の納税額を当てはめると、実際の控除額が見えてきます。
一例を挙げて計算してみましょう。計算に用いる条件は以下とします。
- 長期優良住宅の新築に2025年入居
- 年末時点の住宅ローン残高:3,000万円
- 住宅の取得金額:3,500万円
- 本来納めるべき所得税:7万円
- 翌年の住民税:16万円
ステップ1:
年間の控除可能額を計算する
まずは、控除可能な金額を年間で求めましょう。新築の長期優良住宅や低炭素住宅で2025年に入居する場合、最大控除額は次のとおりです。
借入限度額4,500万円×控除率0.7%=31.5万円
一方で、住宅ローン残高を基準とした場合には、以下の式で算出できます。
年末時点の住宅ローン残高3,000万円×控除率0.7%=21万円
つまり、31.5万円よりも低い21万円が、実際に控除可能な金額です。
ステップ2:
戻ってくる所得税額・住民税額
(上限9.75万円)を確認する
次に、控除(減税)される所得税と住民税の金額を見てみましょう。本来納めるべき所得税7万円よりも、控除額21万円のほうが大きいため、所得税の納付は不要です。そして、所得税から控除しきれなかった残りの14万円分は、翌年の住民税から控除されます。
しかし、住民税からの控除額は最高9.75万円と決まっているため、所得税と住民税を合わせて実際に控除される金額は次のとおりです。
所得税7万円+住民税9.75万円=合計16.75万円
同じように、2年目以降も計算できるため、気になる方は試算してみましょう。
住宅ローン控除(減税)の手続き方法
住宅ローン控除(減税)の適用を受けるには、条件を満たしたうえで、確定申告や年末調整を行わなければなりません。ここでは、1年目と2年目以降の手続き方法や、注意点を見ていきましょう。
1年目の場合
住宅ローン控除(減税)の適用を受ける1年目には、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1年分の所得や税金について、毎年2月16日~3月15日に税務署に申告し、税金の過不足を確認・清算するための手続きです。
住宅ローン控除(減税)の1年目は、入居した年の翌年2月16日~3月15日の申告期間中、住んでいる地域を管轄する税務署で手続き可能です。書類一式を用意すれば、税務署への持参や郵送でできるほか、インターネットでも申告できます。
2025年度以降に新築住宅(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)に入居する場合、確定申告の際にそれぞれの性能を満たすことを示す書類の提出が必要です。
申告書に次の必要書類を添付し、納税地の所轄税務署長へと提出しましょう。
- 確定申告時の必要書類
-
横スクロールできます。
書類 入手先 確定申告書 国税庁ホームページや最寄りの税務署 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁ホームページや最寄りの税務署 住宅ローンの借入残高証明書 借入れした金融機関 勤務先の源泉徴収票 勤務先 土地建物の登記簿謄本 法務局の窓口またはオンライン申請システム 建築請負契約書または売買契約書のコピー 工務店や不動産会社 ※2022年入居の方までは確定申告で必要ですが、2023年以降入居の方は提出不要です。 マイナンバーカード(本人確認書類) 市区町村役場 住宅性能を示す書類 工務店や不動産会社
書類は、税務署やローンを借入れした金融機関、不動産会社、法務局などから入手しましょう。確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、指定の用紙をもとに、ご自身で記入して作成する必要があります。
なお、住宅ローン控除(減税)を受けるためだけに申告する場合には、居住した年の翌年1月1日以降であれば、1回目の申告は2月16日を待たずにできます。
2年目以降の場合
住宅ローン控除(減税)の手続きは毎年行う必要がありますが、確定申告は毎年する必要がありません。会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に、住宅ローン控除(減税)の手続きが可能です。金融機関の残高証明書や、年末調整の時期に税務署から届く書類などの必要書類を、勤務先へ提出しましょう。
ただし、フリーランスや個人事業主など源泉徴収制度の対象とならない人は、1年目と同様に確定申告が必要です。住宅ローン控除(減税)の適用を受けるために必要な書類を申告書に添付し、税務署へ提出しましょう。
なお、2年目以降の確定申告では1年目と比べて必要書類が少なくなります。申告書に添付が必要な書類は以下の2点です。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 金融機関の借入金の年末残高等証明書
住宅ローン控除(減税)の申告を忘れた場合の対処法
住宅ローン控除(減税)の適用を一度受けたとしても、2年目以降も自動的に控除されるわけではありません。しかし、手続きをうっかりして忘れてしまう可能性はあります。
確定申告や年末調整の手続きを万が一忘れた場合は、状況に応じて対処しましょう。
まだ確定申告をしていない場合は「還付申告」をする
年末調整の際に、住宅ローン控除(減税)の手続きを忘れた会社員の方など、確定申告をしていない場合、還付申告で税金の還付を受けられる可能性があります。気づいた時期に応じて以下の対処を取りましょう。
- 確定申告期限内(2月16日~3月15日)の場合…確定申告期限内に還付申告しましょう。
- 確定申告期限(2月16日~3月15日)を過ぎた場合…確定申告対象年の翌年1月1日~5年以内に還付申告可能です。
確定申告時に住宅ローン控除(減税)を忘れた場合は「更正の請求」をする
確定申告をしたものの、その際に住宅ローン控除(減税)の申告を忘れた場合には、気づいた時期に応じて以下の対処を取りましょう。
- 確定申告期限内(2月16日~3月15日)の場合…確定申告期限内にあらためて申告書を作成し直し、再度申告しましょう。
- 確定申告期限(2月16日~3月15日)を過ぎた場合…法定申告期限(翌年3月15日※)から5年以内に「更正の請求」を行いましょう。
- ※申告期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
まとめ
住宅ローン控除(減税)は、年末時の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税の控除が受けられる制度です。住宅ローン控除(減税)を利用できれば、住宅ローンの負担は大きく軽減されます。
2025年の改正では、2024年に改正された子育て世帯や若者夫婦世帯に対する支援維持や、それ以外の世帯に対する借入限度額の縮小、省エネ基準に適合していない新築住宅への住宅ローン控除(減税)不適用などの内容が維持されています。
しかし、住宅ローン控除(減税)は制度改正によって毎年変わる可能性がある、最新情報の確認が必要です。
とはいえ、住宅ローン控除(減税)を受けるための条件や控除額の計算方法は、複雑でわかりづらいものです。また、住宅ローンの手続きや必要書類、審査のスケジュールなど不安なこともあるかもしれません。
りそななら、住宅ローンや住宅ローン控除(減税)に関する不明点を相談することができます。土・日・祝日や平日17時以降も相談できる店舗を用意しており、りそなの口座をお持ちでない方でも気軽に相談が可能です。ぜひ、一度相談してみてはいかがでしょうか。
具体的な税制に関する手続き方法については、税理士法上、ご案内いたしかねますので、お近くの税務署にお問合せください。
本記事は2025年12月23日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。