国民年金を未納するとどうなる?
「納付しない」リスクと「納付できない」ときの対処法
公開日:2022/11/29
更新日:2025/08/22

老後の生活を支える国民年金制度については、ネガティブなニュースが少なくありません。「本当にもらえるの?もらえる金額が少なくなるのでは?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
国民年金保険料の納付は日本に居住する20歳以上60歳未満の国民の義務です。将来の年金に不安があるからと保険料を納めなかった場合、催告状などが届き最終的に財産を差し押さえられる可能性もあります。経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、保険料納付の免除や猶予を申請しましょう。
この記事では、国民年金制度の仕組みを解説したうえで、保険料未納のリスクや、どうしても保険料を納付できない場合の対処法を解説します。
国民年金制度を正しく知って、老後も安心して生活するための資金準備について考えてみませんか。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
年金の仕組み
国は、長い期間にわたって財政のバランスがとれるように公的年金制度(国民年金と厚生年金)を運営していかなければなりません。公的年金制度には、「賦課方式」と「積立方式」の2つの財政方式があります。賦課方式とは、現役世代の加入者が支払う保険料をその時の高齢者給付に充てる「仕送り」のような方式です。一方で、積立方式は、将来自分に給付される年金を積み立てていく方式です。日本の公的年金制度は、賦課方式が採用されています。
それぞれにメリット・デメリットがあり、賦課方式では、年金受給者と加入者世代の比率によって保険料が決まるため、年金受給者の数が増えると、現役世代の保険料負担が増えることや年金給付額を削減する必要が生じることがデメリットです。しかし、インフレや給与水準の変化に対応しやすい、つまり、経済変動の影響を受けにくいというメリットがあります。積立方式はその逆で、少子高齢化など人口変動の影響は受けにくいものの、インフレによる価値の目減りや運用環境の悪化によって、将来の自分の年金額が左右されることがデメリットです。
年金は本当にもらえるの?どのくらい?
年金はどれくらいもらえるのでしょうか。今後の見通しを知るために、財政検証(2024年)を見てみましょう。公的年金制度の財政検証とは、厚生労働省が5年ごとに行うもので、公的年金の給付水準や年金の財源について調査し、公的年金制度の今後の見通しを投影するものです。
財政検証では、公的年金の給付水準を示す指標として、現役時代の収入に対する年金額の比率である「所得代替率」をもとに検証し、公的年金制度が健全に持続できるよう調整を行います。
2024年度の所得代替率は、モデル年金月額22.6万円(夫婦2 人の基礎年金13.4万円と1人分の厚生年金9.2万円)を現役時代の男性の手取り平均月収入37万円で割ると61.2%です。少子高齢化、つまり現役世代の減少と高齢世代の増加がさらに進むと、現在の所得代替率が低下することが予測されます。
将来の所得代替率は50.4%程度まで低下するケースも想定される一方で、共働き世帯や定年後の就労といった働き方の変化、制度改正、年金財源の運用成果などにより所得代替率の現状維持をめざす動きも見られます。
年金未納が引起こす3つのリスク
自営業など厚生年金に加入していない第1号被保険者の方は、自分で国民年金保険料を納付する必要があります。会社員(第2号被保険者)の方が退職などで第1号被保険者になった場合には、速やかに国民年金への変更手続きを行いましょう。転職先が決まっている場合でも、空白月がある場合には手続きが必要です。
もし国民年金保険料を納付せず、未納となってしまった場合、どのような影響が出るのでしょうか。ここでは、年金未納が引き起こす3つのリスクを解説します。
年金の受給要件を満たせなくなる可能性がある
国民年金には、基礎年金として日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度として「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」という3つの種類があります。受給するためにはそれぞれの受給要件を満たしていなければなりません。
| 種別 | 受給要件 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上 |
| 障害基礎年金 |
以下のすべてを満たした場合
|
| 遺族基礎年金 |
以下のいずれかを満たした者が死亡したとき
※1および2について、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年に保険料の未納がなければよい ※3および4について、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間ならびに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ある方に限る |
2024年(令和7年)4月分からの年金額は、20歳から59歳までの40年間納付した場合(満額)の老齢基礎年金は、年額83万1,700円(月額6万9,308円)です。
障害基礎年金は、障害等級2級の場合に年額83万1,700円、1級の場合には1.25倍の103万9,625円で、18歳到達年度末(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は「子の加算額」が付きます。
遺族基礎年金は、年額83万1,700円で、障害基礎年金と同様、該当する子どもがいる時もしくは子が受取るときには「子の加算」が支給されます。
老齢基礎年金に注目しがちですが、障害基礎年金や遺族基礎年金受給の可能性を考えると、保険料は納めておくべきと言えるでしょう。
将来受取る年金額が減る
国民年金の受給額は、保険料納付済み月数によって決まります。例えば、老齢基礎年金に40年間加入した場合、受取ることができる年金額は以下の計算で求めることが可能です。
老齢基礎年金=831,700円×(保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7))÷480ヵ月
上記のように、納付している月数が増えると年金額は満額に近づきます。
納付している月数が減ると、受け取ることができる年金額も減ってしまうため、継続して納付し続けることが重要なのです。
延滞金が発生する・財産を差押えられる可能性がある
国民年金保険料の納付は国民の義務です。そのため、保険料を滞納し続けると催告状や督促状が届き、最終的に財産が差押さえられる可能性があります。
また、督促状で指定した期限よりあとに保険料を納付する場合は延滞金が発生するため、納付すべき金額が増えてしまいます。期限内に納付できるよう、備えておきましょう。
国民保険料の納付状況を確認する方法
国民年金の納付状況は、日本年金機構の「ねんきんネット」や誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」で確認できます。未納となっているものがないか、定期的に確認しておきましょう。
なお、年金に関する相談は、最寄りの年金事務所(要予約)やねんきんダイヤルで受け付けています。年金についてわからないこと、困っていることがあれば相談してみましょう。
どうしても国民年金保険料を納付できない場合の対処法
経済的な理由で、どうしても国民年金保険料を納付できない場合は、免除・猶予制度を活用しましょう。ここでは、制度の概要を解説します。
免除・猶予制度を利用する
老齢基礎年金を受給できるのは、「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間を合計して10年以上」ある人です。つまり、保険料を9年間納めていたとしても、将来老齢基礎年金は1円ももらえません。ただし、加入期間には保険料を納めた月だけでなく、「免除」や「猶予」の期間を含めることができます。
免除とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が少なく、経済的に保険料を納めることが困難な場合などに申請することで、保険料納付が免除される制度です。免除される金額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階があります。免除期間は、老齢基礎年金の受給資格の算定期間に含まれますが、受給額は全額納付した場合に比べて低額になります。障害基礎年金や遺族基礎年金についても同様に、免除期間は算定期間に含まれます。
猶予制度は、保険料納付が難しい場合に申請できる制度という点では免除制度と同じですが、あくまでも猶予であるため、追納する(後で納付する)ことが前提です。そのため、猶予期間は受給資格期間には算入されますが、将来の年金額に反映されません。また、所得の判定が本人・配偶者の前年所得であること、50歳未満と限定されている点も免除制度とは異なります。
学生の場合、在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を活用できます。学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金額の計算の対象となる期間には含まれません。
保険料の納付が難しい場合は、未納(何も手続きをしない)のまま放置せず、免除や猶予の申請をしておきましょう。
資金に余裕ができたら年金未納分を追納する
免除や猶予、学生納付特例を受けていたとしても、10年以内であれば保険料を「追納」することで、年金額を増やすこともできます。追納するかどうかは任意です。また、追納した分も社会保険料控除の対象です。
将来の年金額を増やすためにも、資金に余裕ができたら免除・猶予期間分を追納するのがおすすめです。
また、免除や猶予期間を含めても加入期間が10年に満たない場合や、納付月数が40年未満で年金が満額支給されない場合は、60~65歳未満(条件を満たせば70歳未満)の間に追加で保険料を納めて年金額を増やすことができます。これを「任意加入制度」といいます。
国民年金の受給額を増やすには?
条件を満たせば、将来の年金額を増やすこともできます。経済的に余裕があれば、制度利用を検討しましょう。
付加年金(第1号被保険者限定)
第1号被保険者(自営業者など)の年金を増やす方法として、毎月の国民年金保険料に付加保険料400円を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金に「付加年金」が上乗せされます。
付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。月々の保険料負担額が少ないため、対象の方は付加保険料の納付を検討してみましょう。
付加年金についてより詳しく知りたい方は、下記関連記事もご覧ください。
関連記事:付加年金とは?月々400円で年金が増える?特長と留意点
繰下げ受給
年金を「繰下げ受給」する方法もあります。繰下げ受給とは年金を受け取る年齢を遅らせることで、65歳から受け取るのではなく、66歳以降に1ヵ月単位で受給開始時期を選択できる制度です。最長75歳まで繰下げることができます。
年金の増額率は、「65歳に達した月から繰下げ月の前月までの月数×0.7%」です。たとえば70歳までの5年間(60ヵ月)繰下げた場合は、42%、75歳まで10年間(120ヵ月)繰下げると84%も増えます。
ただし、寿命によっては受取る年金の総額が結果的に少なくなってしまう可能性があるので、受取開始までの生活費を確保できているか、健康状態に不安はないかなどを考慮して受取時期を検討しましょう。
老後に向けて考えたい年金以外の対策方法

老後の生活を豊かにするために、今からできることは2つあります。
1つは、老後資金をご自身で準備することです。自分で拠出した掛金を自分自身で運用し、将来に備えるiDeCo(個人型確定拠出年金)のほか、第1号被保険者(自営業者など)であれば、国民年金に上乗せする公的な年金制度として、国民年金基金があり、税制優遇を受けながら老後の資産を積み立てられる制度です。
-
iDeCo(個人型確定拠出年金)
確定拠出型(毎月一定額の掛金を拠出、受給額は運用実績によって異なります。)- 1掛金は全額、所得控除の対象です。
- 2自分で運用できます。運用益は非課税です。
- 3受取時は退職所得控除もしくは公的年金等控除の対象です。
-
国民年金基金
確定給付型(将来の受給額があらかじめ確定しています。)- 1終身年金が基本ですので、生涯にわたって受取ることができます。
- 2掛金は全額、所得控除の対象です。
- 3受取時は公的年金等控除の対象です。
もう1つは老後の収入を確保すること、つまり老後も働き続けることです。老後の働き方は、雇用される働き方だけでなく、個人事業などで収入を得るという選択肢もあります。
公的年金だけでは老後に満足のいく暮らしはできないかもしれませんが、一生涯受取れる収入として確保しておきたいものです。保険料はきちんと納めたうえ、プラスアルファで自分自身でも資産形成や老後対策をし、老後貧困にならないように今から準備をしておきましょう。
まとめ
国民年金保険料を納めない場合、年金が受取れない、年金の受給額が減るといったリスクが発生します。毎月確実に保険料を納められるよう、準備しておきましょう。
年金保険料の納付が滞った場合には、督促状などが届きます。督促状に定められた期限内に保険料を納付しなければ延滞金が発生するため、すみやかに保険料を納付しましょう。また、年金保険料を納めるのが難しい場合は、そのまま放置せず、免除や猶予を申請してください。
老後に備えるなら、iDeCoや国民年金基金なども活用するのがおすすめです。それぞれ特徴が異なるため、自分に合ったものを選択しましょう。
オンラインでかんたん!
相談しながら
- ※当記事は2025年8月22日現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。







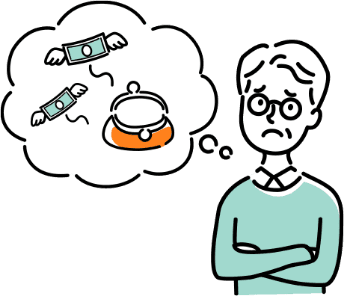
最後に、お客さまにご質問です。