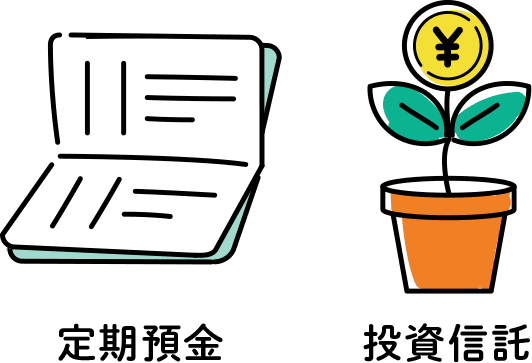- ※りそなグループが監修しています
確定拠出年金と運用商品の関係は?
まず、なぜ運用商品についての理解が必要なのか、確定拠出年金の仕組みをおさらいしましょう。次の3つのステップから成り立っています。
- (1)iDeCoは加入者自身が、企業型は会社が、掛金を専用口座に拠出する。
- (2)専用口座に積立てた年金資産を運用商品で運用する。
- (3)年金資産を60歳以降に受け取る。
確定拠出年金では、どのような資産運用をするかによって将来受給できる金額に差がでます。ですから、運用商品やその選び方を理解することが必要になります。主に「定期預金」と「投資信託」で運用を行うのが一般的です。さらに詳しく説明しましょう。
運用商品の選択は個人の自由
確定拠出年金は、個人が自らの責任で運用商品を自由に選ぶことができます。選択した運用商品によって運用成績も異なります。
商品は各運営管理機関が厳選し、本数も限られているため、選びやすいです。
運用商品の種類
では、運用商品の種類を説明していきます。
元本確保型
確定拠出年金には、定期預金や保険といった元本確保型の商品があります。
投資信託のように元本割れするリスクはありません。そのため、運用することに不安を感じる方にとっては、選びやすいとも言えるでしょう。
ただし、低金利が継続すると運用益は期待できません。また、iDeCoは毎月管理手数料がかかるので、手数料分、掛金元本を下回る可能性があります。
定期預金
まず、定期預金について説明します。
- 基本的な性質
- 基本的には、約束の期日(満期日)までお金を預け、その日を迎えたら預入時に約束した利息(約定利率)を受け取る仕組みの金融商品です。一般的には、半年~5年の期間が設定されているものが多くなっています。
また、満期になると、元本と利息の合計額を新たな元本として、満期日時点の金利で同じ期間自動的に預け入れを繰り返していくのも特徴です。
- 定期預金の注意点
-
定期預金を利用する際に知っておくべき注意点は、次の2つです。
- (1)期日より前に解約すると、預金利率が約定利率より下がります。(確定拠出年金の資産は原則60歳まで引き出せませんが、解約してその資金で他の商品を購入することができます。)
- (2)銀行などの金融機関には、経営破たんした場合に保障される元本は1,000万円まで(ペイオフ制度)という規定があります。すでに多額の資金を預けている金融機関で、新たにiDeCoでも定期預金を利用する場合は注意が必要です。
保険
保険には、「生命保険」や「損害保険」などがあり、満期を迎えると、元本と利息以外に、商品によっては配当金が支払われるものもあります。保険という商品の特性上、中途解約(スイッチング)時に、「解約控除」等が差し引かれ、払い戻し金額が元本を下回る場合があります
元本確保型以外の商品
元本確保型以外の商品として「投資信託」があります。
投資信託
投資信託は、投資家から集めたお金を元手に、ファンドマネジャーが複数の国内外の株式や債券などで運用する運用商品のことです。
投資信託の価格(基準価額)は市場環境によって変動します。投資信託の購入後に、基準価額が上昇して利益がでることもあれば、基準価額が下落して、元本を下回る可能性もあります。
- 投資信託のチェックポイント
-
投資信託を利用する際には、その内容を理解することが重要になります。特に、次の5つの点に注目しましょう。
- (1)投資対象とは
投資信託の投資対象として代表的なものは、国内外株式・国内外債券・国内外REITなどです。 - (2)バランスか単一か
株式、債券、REIT等の複数の資産に一定割合ずつバランスを取りながら運用する投資信託もあれば、国内株式のみなど、単一の資産で運用する投資信託もあります。 - (3)パッシブ運用かアクティブ運用か
「パッシブ運用」とは市場指数(ベンチマーク)に連動することを目標とする運用手法のことです。「アクティブ運用」とは専門家の分析や情報収集に基づき業種配分や銘柄選択などを行うことで、市場指数を上回ることを目標とする運用手法のことです。 - (4)信託報酬とは
投資信託で資金を運用するのにかかる手数料のことです。この手数料は直接支払うのではなく、投資信託全体の中から信託報酬が差引されます。基準価額は信託報酬控除後に算出されます。運用資産が大きくなるほど信託報酬の負担も増えます。信託報酬は、運用会社・投資対象などによって差があります。
信託報酬の低い商品を選ぶのも、運用成果を上げるためのポイントになります。 - (5)運営管理手数料とは
確定拠出年金口座の管理にかかる手数料です。(企業型の場合は規約によりますが会社負担のケースが多いです。)金融機関によって差があるため、具体的にいくらかかるのかを確認しておきましょう。
- (1)投資対象とは
運用商品選びのポイントについて
元本確保型は元本が確保され安心な反面、低利でインフレリスクに対応できません。また、iDeCoのように毎月の口座管理手数料がかかる場合は、手数料で掛金元本を下回ることがあります。投資信託は運用益が期待できる反面、元本割れのリスクがあります。
それぞれの商品ごとのリスクとリターンを理解して商品を選び、リスクとリターンを分散する分散投資を心がけるべきです。
運用商品ごとのリスクとリターンを理解する
投資信託の商品を選ぶ時には、リスクとリターンを考慮することが必要です。
投資信託がどの資産(株式か債券か)や地域(国内か海外か)を投資対象とするかによって、リターンやリスクが異なります。
一般的に、債券よりも株式、国内よりも海外、といった資産の方が、高いリターンが期待できる反面、価格変動リスク(上昇・下落)も大きくなる傾向があります。
分散投資を心がける
株式や債券、国内と海外などの資産は、リスク・リターンの特性が異なります。
つまり、ある資産の価格が上がっている時に、別の資産は下がっているといったことが起こります。
そのため、分散して投資することで、ある投資対象の資産で損失が出た場合でも、別の投資対象の資産で出た利益とある程度相殺し合い、損失を抑えることができるかもしれません。また、資産の組み合せ方によってはリスクを抑えリターンの水準を高めることもできます。
運用商品の見直し方法
市場環境は絶えず変化していきます。環境が変化すれば、当然運用にも影響が及びます。また、どの程度リスクを受け入れられるか(リスク許容度)は人それぞれですし、年齢や運用期間によって変化します。
iDeCoでは、運用商品は一度決めたら終わりではなく、必要に応じて見直すことができます。
見直しには「配分の変更」と「スイッチング」という2つの方法があります。
配分の変更
毎月の掛金で買付ける商品の比率を変更することを、配分の変更といいます。配分の変更には手数料はかかりません。
スイッチング
現在所有している運用商品を売却・解約し、他の運用商品に買い換えることをいいます。例えば、運用成績がよく、高い利益を出せている商品でも、いつどこで値下がりするか分かりません。そういう場合に、利益があがっている商品を売却・解約して、元本確保型の商品を購入するといった方法をとることもできます。
また、各商品の運用成績によって、当初考えた資産配分と異なった状態になることがあります。資産の割合が増えている商品を売却し、減っている商品を購入して、もとのバランスに戻すことをリバランスといいますが、これもスイッチングの一つです。
スイッチング自体に手数料などはかかりません。しかし一部の信託財産留保額(売却時のコスト)が設定している投資信託を売却する際には、売却金額から信託財産留保額が引かれるので注意が必要です。
積極的な情報収集が
大事です
確定拠出年金においては、積み立てた年金資産をどんな運用商品で運用するのかがとても大事です。自分でも積極的に情報収集をするようにしましょう。また、少しでもわからない点や、不安な点があった場合は、金融機関の窓口に問い合わせてみるのもよいでしょう。
※当記事は2021年3月現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。