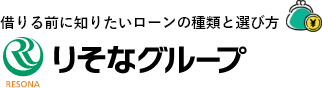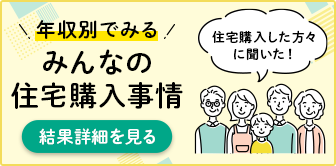住宅ローンの選び方とは?金利や団信といった重要な比較ポイント5つを解説
公開日:2021/01/20
更新日:2024/02/13
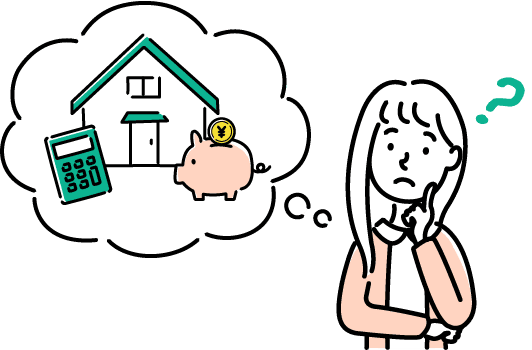
返済金額が大きく、返済期間も長い住宅ローンは、安心して返済していけるかどうかを考えながら選んでいくことが大切です。住宅ローンを決める際、押さえておくべきポイントがいくつかあります。なかでも、金利や団信(団体信用生命保険)といった重要なポイントを理解したうえで比較検討するとスムーズです。
今回は、どういう基準で住宅ローンを選べば良いかわからない方のために、住宅ローン選びで押さえておきたい5つのポイントを解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。
現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。
- ※りそなグループが監修しています
住宅ローンの選び方1:まずは「金利タイプ」を選ぶ
住宅ローンの「金利」と聞くと、「年○%」というように、数字の高低をイメージする人も多いのではないでしょうか。もちろん金利も大切なポイントですが、まずは「金利タイプ」を選ぶことからはじめましょう。
金利は低いほうが総返済額は低くなりますが、金融機関によっては期間限定の特別金利が設定されている場合もあります。長期的な視点で、返済期間と金利体系、その利率を総合的に検討することが重要です。
住宅ローンの金利タイプには、大きく分けて以下の3種類があります。
変動金利型
変動金利型は、市場金利の変化に応じて、返済の途中であっても金利が変動するタイプです。
メリットは、一般的に固定金利よりも低い金利で借入れできることです。借入れ当初よりも金利が低下すれば毎月の返済額が低減します。デメリットは、金利上昇により毎月の返済額が増加する可能性があることです。
通常、定期的に金利が変更され、それに応じて返済額も再計算されます。しかし、変更時に必ず金利が変わるわけではなく、そのままの場合もあります。返済額が確定しないため、金利上昇により返済額が膨れ上がるケースもあります。
全期間固定金利型
全期間固定金利型は、借入期間中の金利があらかじめ決まっていて、完済までの返済額も確定しているタイプです。
変動金利型や固定金利選択型とは異なり、借入期間中ずっと金利が一定しているため、毎月返済額が変わりません。返済額が決まっているので、返済計画を立てやすいというメリットがあります。
しかし、一般的には変動金利型や固定金利選択型よりも、金利が高めになるため、注意が必要です。
固定金利期間選択型
固定金利期間選択型は、借入れ当初の金利と適用期間が決まっており、固定金利の適用期間が終わったあとに自分で金利タイプを再度選ぶタイプです。固定金利期間は、2年・3年・5年・7年・10年・15年などがあります。
全期間固定金利型と変動金利型の両方の特徴を備えており、固定金利期間中は、市場金利の影響を受けることなく一定金額を返済していけるため、返済計画を立てやすい点がメリットです。
しかし、金利上昇リスクを抑えられる一方で、一般的に変動金利型よりも高い金利となることはデメリットといえます。
住宅ローンの選び方2:住宅ローンの「種類」を選ぶ

住宅ローンの借入れ先の種類は、おもに以下の3つに分けられます。
- 民間の金融機関(銀行・信用金庫・ノンバンクなど)が行う「民間ローン(民間融資)」
- 国や自治体などが融資する「公的ローン」
- 住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資する「フラット35」
自分の目的に合った借入れ先を選ぶことが大切です。
民間ローン
民間ローン(民間融資)は、民間の金融機関(銀行・信用金庫・ノンバンクなど)が提供している住宅ローンです。変動金利型、固定金利期間選択型など、金利タイプの選択肢が多いのが特長です。また、金融機関によっては、取引の状況に応じて金利優遇を受けられることもあります。
民間ローンを細分化すると、提携ローンと非提携ローンの2種類があります。提携ローンは、不動産会社と民間金融機関が提携し、住宅の買主・建築主に提供する住宅ローンです。買主・建築主が住宅ローンを検討する際に、不動産会社があらかじめ住宅ローン協定を締結している金融機関との間に入る仕組みです。
提携ローンでは、金利優遇を受けられたり、借入れ手続きや物件の引渡しなどがスムーズに行われたりするなどのメリットがあります。
公的ローン
公的ローンは、国や自治体をはじめとする公的機関が提供している住宅ローンで、おもに財形住宅融資と自治体融資の2つに分類されます。
財形住宅融資は、5年ごとに適用金利を見直す「5年間固定金利制」の住宅ローンです。同じ条件で民間ローンを利用する場合と比べ、金利は低く設定されています。また、保証会社に対する保証料や事務手数料はかかりません。
ただし、利用条件が細かく設定されているため、慎重に検討しましょう。例えば、勤務先の財形貯蓄制度を1年以上継続していること、その貯蓄残高が50万円以上あることなどが挙げられます。
自治体融資とは、勤労者支援の一環として、都道府県や市町村などが行っている制度です。他の金融機関の住宅ローンとは異なり、融資あっせん制度や利子補給制度などのように、住宅ローンを補完する要素が強いといえます。
この制度を利用すれば、利子の一部、あるいは全部を負担してもらえます。自治体が直接負担したり、提携している民間の金融機関が負担したりと、詳細は自治体によって異なるのが特徴です。
【民間&公的共同ローン】フラット35
フラット35は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資する住宅ローンです。フラット35という名のとおり、最長35年間、借入れ時から完済時まで金利が変わらない長期固定金利型となっています。
最長35年と長期間にわたって毎月返済額が変わらないことは、ライフプラン上の資金計画を立てていくうえで大きなメリットです。
借入期間は、必ずしも35年間にする必要はありません。原則15年以上かつ35年以内、または契約時の年齢から80歳になるまでの範囲で借入期間の設定が可能です。
適用される金利は、金融機関によって異なります。借入期間が20年以下の場合と21年以上の場合や、融資率や加入する団体信用生命保険の種類などに応じて変動します。
子育て世帯や省エネルギー性、バリアフリー性、耐震性など、一定の条件を満たした住宅を取得する場合、借入金利が一定期間引下げられる制度もあります。
長期間にわたって返済額が変わらないメリットがある一方で、市場金利の動向によっては、変動金利型や固定金利期間選択型の民間ローンに比べて総返済額が多くなる可能性がある点はデメリットといえます。
住宅ローンの選び方3:万が一に備えて「団体信用生命保険の保障内容」も考慮する
返済中の万が一のことを考えると、住宅ローンに付帯する保障内容は非常に大切です。ここでは、「団体信用生命保険」(団信)について解説します。
保障における団信の意味を理解し、適切に判断をするようにしましょう。
団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを契約した人が死亡した場合や、高度障害状態となった場合、残りのローンが保険金で完済される保険です。また、三大疾病特約・八大疾病特約・ガン保障特約などの特約を取扱っている金融機関もあります。
一般的に、住宅ローンの返済は数十年と長期間です。返済期間中の死亡や高度障害、その他の病気やケガが原因で収入が低減するリスクも十分に考えられます。
オプションの団信を付加しておくことで、ガンや脳梗塞のように大きな病気を患い、収入が低減してしまう場合や、収入がなくなってしまう場合のローン返済に対する不安を軽減できます。
団信に加入する場合は、保障内容に加えて、「どういった状態になれば保険金が支払われるか(ローン残高が完済されるか)」をしっかりと確認しておくことが大切です。
- ガンや心筋梗塞などの病気になったとき、しばらく休んで職場に復帰するようなケースでも保障されるのか
- 要介護状態になった場合には保障されるのか
このようなさまざまなケースを想定しながら、ベストな保障を選ぶようにしましょう。団信は、住宅ローンの契約時のみ加入できる保険です。ローンを借入れた後は、原則、保障内容の変更はできません。
団信の保険料は住宅ローンの金利に含まれているケースが多く、契約者が別途保険料を支払わなくてよいこともあります。通常の生命保険に比べ、保険料負担の面からみても団信のほうが割安になる場合もあります。
住宅ローンの団信の場合、保険に入るきっかけは「自宅購入」です。団信の加入者は健康な人が多いので、保険会社にとっては保険金を支払うリスクが低くなります。そのため、保険料が安くなりやすいのです。
通常の生命保険の場合、保険に入る目的は「健康不安」です。そのため、住宅ローンの団信と同等の保険に加入しようとすると、金利上乗せ相当分の保険料では入れません。団信は、単に団体割引が効くから安いというわけではないことも知っておくといいでしょう。
告知義務・免責事項に注意
団信に加入する際には、健康状態に関する審査を受ける必要があります。過去の傷病歴や現在の健康状態、身体の障害などについて、告知書に正しく記載しなければなりません。もし、告知義務違反となると、保険契約を解除されてしまうケースもあるので注意しましょう。
また、契約前には免責事項(どのような場合に保険金が払われないか)もしっかりと確認することが重要です。万一、審査に通らない場合、団信の加入義務がないフラット35を選ぶ方法もあります。
オプション団信
「団体信用生命保険とは?」の章でオプション団信について触れましたが、住宅ローンを組む上で重要なものなので、改めて紹介します。
オプション団信とは、万が一あったときの保障(団信)に加え、オプションとしてガンなどにかかった時に、住宅ローンの残高が保険金で完済される保険のことです。
住宅ローンの返済中に大きな病気をした場合や、介護が必要な状態になった場合、「医療(介護)費」、「その後の生活費」および「住宅ローン返済のためのお金」が必要になります。
これらの保障をすべて民間の生命保険(医療保険やガン保険、介護保険など)で備えようとすると、保険料負担が大きくなる可能性もあります。
しかし、住宅ローンの返済分は、オプション団信で備えるようにすれば、家計負担の軽減につながります。住宅ローン加入のタイミングで、既存の生命保険や医療保険を見直すのもいいでしょう。
オプション団信には三大疾病、八大疾病、要介護状態などに備えられるものなど、保障の範囲が異なるものがあります。特約内容をきちんと確認し、賢く利用しましょう。
また、住宅ローンをご利用の際には、以下を参考に併せて保険の見直しも行ってみてください。
住宅ローンの選び方4:「諸費用」も含めて選ぶ
住宅ローンを契約する際は、物件価格だけではなく、その他諸経費についても把握しておく必要があります。具体的には、住宅ローンにかかるおもな諸費用として、以下のようなものがあります。
-
- 保証会社事務取扱手数料
- 保証会社と保証委託契約を締結する際にかかる事務手数料です。
-
- 保証料
- 保証会社を利用する際に、保証会社への報酬として支払うものです。
-
- 登記費用
- 登記費用には、住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税と、登記手続きを依頼する司法書士への報酬(手数料)が必要です。
-
- 融資手数料
- 金融機関に支払う手数料です。
-
- 印紙税
- 住宅ローン契約書などを作成するときにかかります。契約書に印紙を貼付して納めます。
-
- 繰上返済手数料
- 一部繰上返済や借換え前の残高を返済する際にかかります。
これらの住宅ローンの借入れ時に必要な諸経費は、住宅ローンを借入れる金融機関や借入金額によっても異なります。ただ、一般的には物件価格の約5~10%程度の金額が必要といわれています。
住宅ローンの諸費用が気になるようであれば、「諸費用ローン」を利用するのも一つの手段です。諸費用ローンは、不動産仲介手数料、保証料、火災保険料、登記料、引越し費用をはじめとした住宅取得に関する諸費用に利用可能です。
りそなをご利用いただく場合は、仲介手数料や登記費用、火災保険料などの諸費用もまとめて住宅ローンとして借入れすることが可能です。
住宅ローンの選び方5:自分に合った「返済方法」を選ぶ
住宅ローンの返済方法は、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。基本的には「元利均等返済」ですが、元金均等返済という返済方法も存在する両者の違いを知り、自分に合った返済方法を選ぶようにしましょう。
元利均等返済
元利均等返済とは、毎月一定の金額を返済する方法です。毎月の返済額のなかには、「元金」と「利息」が含まれており、基本的に元金の返済分と利息の支払い分を合わせた毎月の返済額が完済時まで変わりません。そのため、返済計画を立てやすい点がメリットです。
しかし、返済当初は毎月の返済額のうち利息割合が大きいため、元金が減りづらいのがデメリットです。
元金均等返済
元金均等返済は、元金の返済額が毎月一定で、そこに利息分を上乗せした金額を返済する方法です。利息額は、借入残高に金利をかけて計算するため、元金の減少にともなって支払う利息の額も次第に減っていきます。
利息を早く返済できるため、元利金均等返済よりも総返済額が少なくなる点はメリットです。しかし、最初のうちは返済額が大きくなるため、家計を圧迫する可能性もある点は考慮しておきましょう。
金融機関によっては元金均等返済の取扱いをしていない場合もあります。
※りそなでは元金均等返済は取扱っていません。
住宅ローン申込みの流れ
住宅ローンに申込む際は、以下の流れで進める場合が多いです。
- 1.予算を決める(借入可能額を調べる)
- 2.物件を探す
- 3.ローンの申込み(事前審査)
- 4.条件を比較しローンタイプを決定
- 5.正式審査
- 6.借入
住宅ローンでは、希望する金額を借りられるとは限らず、希望額に届かなかった場合は予算を見直す可能性もあります。そのため、先におおよその借入可能額を調べてから、物件を探すのがおすすめです。借入可能額を調べる際は、住宅ローンのシミュレーションツールを活用しましょう。
住宅ローンを利用する際は、事前審査と正式審査2つの審査に通過する必要があります。審査される目的や必要書類はそれぞれ異なるため、事前に確認しておきましょう。なお、仮審査は物件が決まった段階で行われるのが一般的です。
事前審査通過のお知らせが届いたら、希望に適した条件のローンを選んで申込みます。書類不備などにより融資の実行が間に合わなければ、物件の引き渡しが遅れてしまう ため注意が必要です。
住宅ローンを選ぶ際に気を付けるべき3つのポイント
住宅ローンは返済期間が長く、金額も大きいため、どの住宅ローンが良いかしっかり検討することが大切です。ここでは、住宅ローンを選ぶにあたり、どのようなことに気を付けるべきかを解説します。
中古物件を購入する際はリフォーム費用なども考慮する
中古物件を購入する際は、諸費用(仲介業者の手数料・登記費用・ローン手数料)やリフォーム費用など、新築住宅を購入する際とは異なる費用が発生します。売主から直接購入した場合、仲介手数料は必要ありません。
まとまった出費が厳しい場合は、諸費用を住宅ローンに含めて支払う方法もあります。ただし、住宅ローンに含められるかは金融機関によって異なるため注意が必要です。
なお、りそなでは、これまでに提供していた「諸費用ローン」はなくなり、住宅ローンに含められるようになりました。それぞれ分けて契約する必要がないため、事務手数料を抑えられるなどのメリットがあります。
付帯特典もチェックしておく
金融機関によっては、住宅ローンの利用者に対して特典や優待サービスを提供しています。返済期間は長期にわたるため、返済の負担が軽減される特典を探すのがおすすめです。
りそなの住宅ローンを利用すれば、りそなクラブで10,000ポイントをもらえる、クラブステータスがルビー以上になるなどの特典が受けられます。ステータスが上がることで、ATM手数料がお得になるのが魅力です。
選択に迷ったら専門家に相談する
住宅ローンを上手に選ぶためには、銀行に相談することも大切なポイントです。
例えば、「金利タイプの選び方や返済計画の立て方がわからない」「自分の選択が正しいか確認したい」といった場合は、専門家の意見を聞くことで納得して住宅ローンに申込めます。
住宅ローン相談は、相談先の銀行に口座がなくても受けられます。銀行では住宅ローンの専用窓口を開設して、専門の相談員を配置しているのが一般的であり、無料で何度でも相談に乗ってくれます。
具体的なローンの組み方や手続き方法はもちろんのこと、住宅ローンの基本的な質問、選び方なども相談が可能です。
相談員は実際に、多くの人たちから相談を受けており、住宅ローン利用者のさまざまな不安や疑問を把握しています。
そのため、相談者にとって適切なアドバイスをしてくれるでしょう。定期的に住宅ローン相談会やセミナーを開催している銀行もあるため、参加してみるのもおすすめです。
銀行によっては平日の営業時間だけでなく、休日でも対応している場合があるため、平日に時間が取れない人でも利用しやすいでしょう。
また、対面による相談だけでなく、電話やオンラインでの相談を行っている銀行もあります。
銀行では、住宅ローンを取扱っているため、詳細な手続き方法や具体的なお借入金額まで幅広いアドバイスを受けられます。例えば、以下のような具体的な内容が相談可能です。
- 返済期間は何年間(何歳)まで設定できるか
- いくらまで借入れできるか
- どのような住宅ローンの種類を取扱っているか
- 万が一、返済困難になった場合はどうなるか、など
なお、銀行では新規借入れだけでなく、現在返済中の住宅ローンの借換え相談も行っています。上手に借換えをすることで「より一層低金利のものに借換える」「金利タイプを見直せる」「返済期間を見直せる」などが期待できるでしょう。
実際に、既存の住宅ローンと返済額がどのように変わるかシミュレーションをしてもらうと、その違いが明確になります。また、借換えと同時に団体信用生命保険の保障内容の見直しについても相談するといいですね。
非対面で相談できるのも便利ですが、自分では調べるのが難しい疑問、あるいは口頭のみで伝えるのが難しい疑問に対し、ピンポイントな答えを得られないことも考えられます。住宅ローンは長い取引になるため、何かあった際にすぐ相談できる店舗があるのは大きなメリットです。
まとめ
住宅ローン選びでは、金利タイプや借入れ先の種類、保障内容、諸費用、返済方法など、多くの点を考慮に入れながら、あなたに合ったものを選定することが重要です。
また、住宅ローンは返済額が大きく、返済期間も数十年と長期に及ぶため、信頼できる金融機関を選ぶ必要があります。りそなの住宅ローンには、次のように多くの特長があり、おすすめです。
- 店舗があって、借りる前も借りた後も相談できるのに魅力的な金利
- りそなの各種ローンをお申込みいただくと通常より優遇された金利(各種ローン)で借入可能
- オプション団信が充実 ※関西みらい銀行の団信は商品が異なります。
- 自然災害サポートオプションもある ※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ
- 契約と口座作成も非対面で借入手続きが完了できる
りそななら、大手銀行だからこその安心感のあるサービスで、窓口でプロが手厚くサポートしてくれます。インターネットで手軽に事前審査の申込み、相談予約も可能です。住宅ローンの金利や返済方法など気になることがあれば、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
本記事は2023年3月31日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。