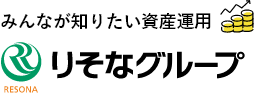投資信託の利回りとは?あなたに合った利回りを見つけるためのヒント
公開日:2022/03/31
更新日:2025/03/04
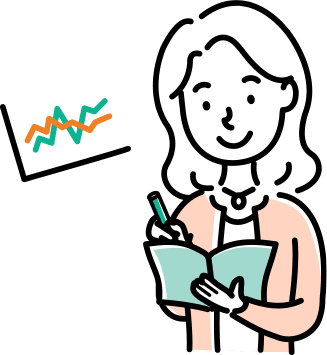
投資信託を選ぶ際や、自分が投資している投資信託の運用実績をみる際に理解しておきたい指標として、利回りや騰落率などがあります。
これから投資信託をはじめる方もすでにはじめている方もこうした考え方を理解しておくと役に立ちますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
- ※りそなグループが監修しています
「利回り」とは?
投資元本に対してどれだけの利益が得られたかを示すもので、通常は年利(%)で表記します。
ここでいう収益は、買い値と売り値の差額から生じる利益や損失(売却益・売却損、キャピタルゲイン・キャピタルロス)と、利息、配当金、分配金など投資している間に得られる利益(インカムゲイン)を合計したものになります。
利回りと混同しやすい資産運用における用語解説
利率との違い
利回りと混同されやすい指標として、利率があります。利率とは、預金額や債券の額面金額に対する1年当たりの利息の割合のことです。
利回りは、前述の通り、利息だけでなく売却損益や分配金などを含めた1年当たり収益の投資元本に対する割合のことで、幅広い金融商品のリターンを表す指標です。これに対して利率は、預金や債券のような利息が支払われる金融商品のみに用いられる指標です。
騰落率との違い
利回りと混同されやすい指標として騰落率があります。騰落率とは、投資信託の基準価額が一定期間内にどの程度値上がり、あるいは値下がりしたかを表す変動率のことです。
利回りは投資から得られる収益の割合を示し、投資の収益性を評価するための指標であるのに対し、騰落率は投資信託や株式など資産価格の変動を示し、投資の価格変動を評価するための指標です。
具体的には基準価額は投資信託の1口あたりの価格を指しており、仮に基準価額1万円の投資信託が1年後、1万500円へ値上がりした場合の騰落率は5%です。
投資信託を取り扱っている金融機関のホームページから、各ファンドの様々な期間の騰落率(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、10年、設定来など)を参照することができます。
投資信託を選ぶ際には、直近の騰落率だけでなく、より長期の騰落率も含めて確認したうえで判断材料として活用しましょう。
パフォーマンスとの違い
利回りと混同されやすい指標としてパフォーマンスがあります。パフォーマンスとは、運用成績のことを指します。
利回りは投資から得られる収益の割合を示し、投資の収益性を評価するための指標であるのに対し、パフォーマンスは投資信託で得た収益が、ベンチマークよりも良かったか悪かったかでパフォーマンスを判断します。
投資信託では、一般的に投資成果を評価する基準(ベンチマーク)として、市場全体の動きを示すインデックス(国内株式であれば、日経平均株価、TOPIXなど)が設定されています。
ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用するタイプをインデックスファンド、ベンチマークを上回る投資成果を目指して運用するタイプをアクティブファンドといいます。
アクティブファンドでは、ベンチマークとの対比で運用実績を評価する方法があります。
例えば、ベンチマークとしてTOPIXを採用している日本株のアクティブファンドのリターンが20%だったとすると、これだけをみれば非常に高いようにみえます。しかし、仮にTOPIXのリターンが25%だとすれば、このファンドはTOPIXのリターンを下回っていますので、ベンチマーク比較での評価は低くなります。
一方、ベンチマークとしてTOPIXを採用している日本株のアクティブファンドのリターンが△10%だったとすると、これだけをみれば運用実績としては芳しくないようにみえます。しかし、仮にTOPIXのリターンが△20%だとすれば、このファンドはTOPIXのリターンを上回っていますので、ベンチマーク比較での評価は高くなります。
トータルリターンとの違い
利回りと混同されやすい指標としてトータルリターンがあります。
トータルリターンとは、一定期間内の投資の損益のことを言います。利回りはパーセンテージの割合で示されますが、トータルリターンは金額で示されます。
「トータルリターン」については「リターン」と表記しているWebサイトもあります。
投資信託の利回り計算例
利回りは、様々な金融商品の運用実績を評価する際に利用できますが、ここでは投資信託を例に見てみます。
- <計算式>
- 利回り(%)={(売却損益+分配金)/運用年数 }/投資元本 ×100
以下の投資例に沿って、利回りを計算してみましょう。
- 【投資例】
-
- 売却損益:4万円
- 分配金:6万円
- 運用年数:2年
- 投資元本:100万円
- 【投資例を使った利回りの計算】
- {(4万円+6万円)/2年}/100万円 ×100 = 利回り5%
このように計算すれば、総合的な運用実績を確認することができます。
投資信託の利回りはどこを見れば確認できる?
投資信託の利回りは、投資信託協会や投資信託会社のホームページ、金融商品の購入画面などで確認できます。ただし、ホームページによって計算方法や表示方法が異なる場合があるため、注意書きなども含めて詳細を確認することが重要です。
投資信託を購入する際は目標利回りを設定しよう
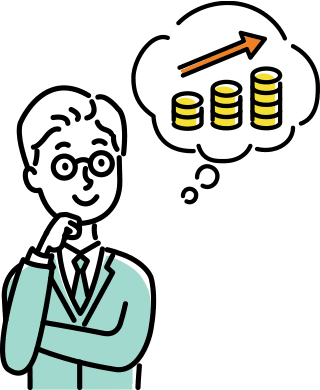
投資信託を購入する際には、目標利回りを設定することが重要です。利回りは過去の運用実績だけでなく、運用の目標としても活用できます。
中長期的な運用を前提としたファンドには目標利回りが提示されているものもあります。自分の目標利回りに近いファンドを選ぶと良いでしょう。
また、投資信託会社などが提供しているシミュレーションを活用し、いつまでにどれくらいの金額が必要かを具体的に決めることで、必要な利回りを把握することができます。
投資信託は利回りが高いほど良いとは限らない
投資信託を選ぶ際、利回りが高いほど良いとは限りません。
目標利回りが高いほどリスクも大きくなるため、自分がどの程度のリスクを許容できるかを考え、自分の目標と照らし合わせながら選ぶことが重要です。
また、利回りは過去の実績であり、将来のリターンを保証するものではありません。
投資信託における
目標利回りの例

次に投資信託の目標利回りの例を見てみます。
りそなが提供している「りそなラップ型ファンド(R246)」では、目標利回り(リターン)が異なる、3つのタイプがあり、ご自身のリスクリターンに合わせた選択をできるところが魅力です。
- りそなラップ型ファンド(安定型)【愛称:R246(安定型)】:目標2%
- りそなラップ型ファンド(安定成長型)【愛称:R246(安定成長型)】:目標4%
- りそなラップ型ファンド(成長型)【愛称:R246(成長型)】:目標6%
特に「りそなラップ型ファンド(安定型)」は安定性を重視しながら運用するため、比較的リスクが低く、投資信託が初めての方にもはじめやすい商品といえます。
利回り以外に投資信託選びで確認すべきポイント
投資信託を選ぶ際には、利回り以外にも確認すべきポイントがあります。
運用成績
投資信託の運用成績は、各運用会社の方針に左右されます。基準価額の推移を確認することで運用成績がわかります。
同じタイプの商品と比較することで、運用方針を把握しやすくなり、投資信託を選ぶ際の判断材料になります。
分配金の有無
投資信託には分配金があるものとないものがあり、支払頻度や割合はそれぞれ異なります。
ただし、分配金は運用資産から支払われるため、分配金がある投資信託が必ずしも優れているわけではありません。
投資信託にかかるコスト
投資信託には、購入時手数料や信託報酬などのコストがかかります。また、解約時に信託財産留保額が発生することもあります。
長期運用の場合、これらのコストが運用成果に影響を与えるため、購入前に確認しておくとよいでしょう。
上記のポイントを確認し、自分に合った投資信託を選ぶことが大切です。
まとめ
利回りとは、投資元本に対する1年あたりの収益の割合を示す指標です。あらかじめ利回りの目標を決めたうえで目標にあったファンドを選びましょう。目標利回りが高いほどその分リスクも大きくなります。自分の目標利回りを決まる際にはどの程度のリスクを受け入れられるのかも考慮する必要があります。
「りそなラップ型ファンド(R246)」なら、運用タイプを目標リターン別に3種類から選べるうえ、コストも比較的低く、初めての方でも利用しやすいという特徴があります。
騰落率とは、投資信託の基準価額が一定期間内にどの程度値上がり、あるいは値下がりしたかを表す変動率のことです。投資信託を選ぶ際には、直近の騰落率だけでなく、より長期の騰落率も含めて確認したうえで判断材料として活用しましょう。
アクティブファンドの運用実績を評価する際には、ベンチマーク比較という手法が用いられます。
投資信託をはじめるにあたって、あるいはすでに保有している場合も、投資信託の運用実績をみる指標について理解しておくと役に立ちます。
また、利回り以外にも、運用成績や分配金の有無、コストなども確認しておくことも大切です。
本記事は2025年3月4日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。
NISAご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。
- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。
- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。