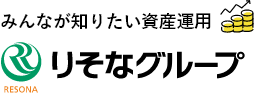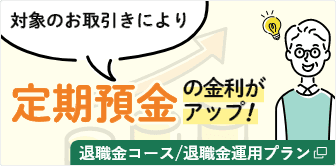退職金の相場はどれくらい?企業規模・業種・勤続年数による違いと老後資金の準備方法
公開日:2021/03/05
更新日:2025/08/06
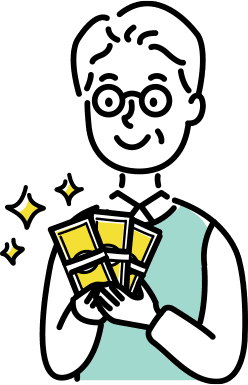
定年が近づいてくると「退職金がどれくらいもらえるのか」気になる方も多いのではないでしょうか。
退職金は老後の生活を支える大切な資金です。しかしその金額は「大企業か」「中小企業か」、また勤続年数が「20年か」「30年か」などによって異なります。
今回は、条件別の退職金の平均相場や退職金の種類、退職金にかかる税金の計算方法、退職金以外に老後資金を準備する方法を解説するので、参考にしてみてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
【大企業・中小企業別】退職金の平均相場
退職金の額は、会社の規模・勤続年数・職種・学歴・退職理由などによって異なります。
まずは大企業と中小企業の平均相場を紹介します。
大企業
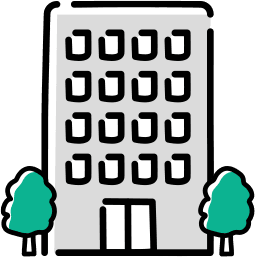
厚生労働省(中央労働委員会)は「令和5年賃金事情等総合調査」で、大企業(※1)における学歴別の平均退職金額を公表しています。
大企業(※1)201社の回答をもとにした同調査によると、大学卒は22歳、高校卒は18歳で入社し、同一企業に定年退職するまで勤務した場合(満勤勤続)の平均退職金額は次のとおりです。
大企業の平均退職金額(男性)
| 大学卒 | 2,139万6,000円 |
|---|---|
| 高校卒 | 2,019万9,000円 |
「令和5年賃金事情等総合調査」厚生労働省(中央労働委員会)
(https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/23/dl/07.pdf)をもとに作成
調査の実施期間:2022年度1年間
- ※1「大企業」についての明確な定義はなく、中小企業以外を指しています。「資本金3億円以上」を大企業とする場合もありますが、同調査では「資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上」としているため、「大企業」として紹介しています。
中小企業
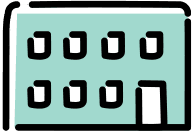
中小企業(※2)の退職金相場は、東京都産業労働局が「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」で公表しています。東京都内の中小企業659社を対象とした調査のうち、「退職金制度あり」と回答した423社について結果を集計したものです。
卒業後すぐに入社し、同一企業に定年で退職するまで勤務した場合(満勤勤続)の「モデル退職金」は次のようになっています。
中小企業の平均退職金額(モデル退職金)
| 大学卒 | 1,149万5,000円 |
|---|---|
| 高校卒 | 974万1,000円 |
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
調査時点:2024年7月31日時点
- ※2中小企業であるかは従業員数と資本金によって決まりますが、その基準は業種によって異なります。たとえば、小売業では資本金が5千万円以下又は常時使用する従業員数が50人以下、製造業では資本金が3億円以下又は常時使用する従業員数が300人以下の会社が該当します。中小企業者の定義について詳しく知りたい人は、中小企業庁のホームページでご確認ください。
上記の2つの調査によると、大企業と中小企業では、学歴別に見ても退職金の差が大きいことがわかります。
また、同じ企業規模でも、学歴によって退職金額が異なります。
具体的な金額の違いを、以下で見てみましょう。
【企業規模別】平均退職金額の差
| 大学卒 (大企業-中小企業) |
990万1,000円 |
|---|---|
| 高校卒 (大企業-中小企業) |
1,045万8,000円 |
【学歴別】平均退職金額の差
| 大企業 (大学卒-高校卒) |
119万7,000円 |
|---|---|
| 中小企業 (大学卒-高校卒) |
175万4,000円 |
【業種別】
退職金の平均相場
退職金額は、業種によっても異なります。前章で紹介した「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」では、業種別のデータも公表されています。
【業種別・学歴別】平均退職金額
横スクロールできます。
| 業種 | 高校卒 | 大学卒 |
|---|---|---|
| 建設業 | 991万4,000円 | 929万6,000円 |
| 製造業 | 1,027万2,000円 | 1,107万6,000円 |
| 運輸業・郵便業 | 866万1,000円 | 938万3,000円 |
| 卸売業・小売業 | 880万7,000円 | 1,239万円 |
| 金融業・保険業 | 1,497万円 | 1,940万4,000円 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | - | 1,054万4,000円 |
業種別に見ると、高校卒・大学卒ともに「金融業・保険業」の平均退職金額が最も高いという結果でした。
また、大学卒のほうが高校卒よりも退職金額が高い業種がある一方、大学卒が高校卒を下回っている「建設業」などの業種もあります。
【勤続年数別】
退職金の平均相場
厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定するなど、働き方が見直されている現在、一つの会社で定年退職まで勤め上げるケースは少なくなっています。勤続年数に応じた退職金の違いも気になるところです。
りそな年金研究所の「企業年金ノート(2025年5月)」には、厚生労働省(中央労働委員会)と東京都の調査をもとに、モデル退職金をまとめたデータが掲載されています。大学を卒業して入社後からの勤続年数に応じたデータなので、モデル退職金の推移をわかりやすく把握できます。
【勤続年数別】モデル退職金・定年退職金の水準
横スクロールできます。
| 勤続年数 (年齢) |
3年 (25歳) |
5年 (27歳) |
10年 (32歳) |
20年 (42歳) |
30年 (52歳) |
定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央労働委員会 (大企業・2021) |
会社都合 | 69万6,000円 | 121万3,000円 | 305万7,000円 | 1,021万6,000円 | 2,054万5,000円 | 2,858万4,000円 |
| 自己都合 | 34万1,000円 | 63万1,000円 | 182万8,000円 | 761万9,000円 | 1,771万8,000円 | - | |
| 東京都 (中小企業・2022) |
会社都合 | 30万4,000円 | 57万4,000円 | 144万8,000円 | 408万1,000円 | 776万2,000円 | 1,149万5,000円 |
| 自己都合 | 21万5,000円 | 43万2,000円 | 112万5,000円 | 346万8,000円 | 750万7,000円 | - | |
出典:りそな年金研究所「企業年金ノート(2025年5月)」
このデータから、勤続年数が長いほど退職金の水準が高くなることがわかります。
ただし、勤続30年を超えたあたりから、金額の伸び幅が小さくなる傾向にあります。
また、以下の2点にも注意が必要です。
- 勤続年数が短期間(3年未満など)の場合、会社によっては退職金が支給されない
- 自己都合退職の場合、退職金額が少なくなる
なかでも、特に気を付けたいのは「自己都合退職の場合、退職金額が少なくなる」という点です。退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2パターンがあります。
「自己都合退職」とは、転職や結婚、病気などを理由に、自分の意思で退職を申し出る場合のことです。
一方「会社都合退職」とは、会社側の事情により退職する場合を指し、定年だけでなく経営破綻や業績不振・事業縮小にともなう整理解雇(リストラ)などがこれに該当します。
退職金の種類は大きく分けて4つ
退職金は、従業員が長年勤め上げた功労に対して企業から支払われるお金で、大きく4つの種類があります。
- 退職一時金制度
- 確定給付企業年金(DB)
- 企業型確定拠出年金(DC)
- 退職金共済
それぞれの退職金制度の特徴を、具体的に整理してみましょう。
退職一時金制度
退職時に、まとまった金額を一時金として支給する仕組みです。
企業が独自に社内で資金を積み立て、勤続年数や役職、退職理由などに応じて支給額や支給時期を退職金規定で定めます。
ただし、退職一時金制度は法律で導入が義務付けられているわけではありません。導入していない企業もあるため、退職金の有無や金額については勤務先に確認してみましょう。
確定給付企業年金(DB)
確定給付企業年金(DB)は、企業が従業員に約束した金額を退職時に支給する制度です。資産の運用責任は企業側が負います。
受取方法は、「一時金としてまとめて受け取る(一時金受取り)」「年金として分割で受け取る(年金受取り)」から選べます。あらかじめ受け取る金額が決まっているため、将来の資金計画が立てやすい点がメリットです。
企業型確定拠出年金(DC)
企業型確定拠出年金(DC)は、企業(または個人)が掛金を拠出し、従業員が自ら運用を行う年金制度です。
自身のリスク許容度に応じて商品や運用方法を決められるため、運用成果によって将来受け取る金額が変動します。資産形成への意識を高めるきっかけにもなるでしょう。
運用益は非課税なので、効率よく老後資金を準備できる点もメリットです。
受取方法は、「一時金受取り」「年金受取り」「一時金受取りと年金受取りの併用」から選べるため、ライフプランに合わせて柔軟に活用できます。
退職金共済
中小企業の場合、長期間にわたって独自に退職金を積み立てるのが難しいケースも少なくありません。退職金共済は、そのような中小企業を支える役割を担っている制度です。
例えば「中小企業退職金共済制度(中退共)」は、企業が掛金を拠出し、資産管理や運用は勤労者退職金共済機構が行うという仕組みになっています。
従業員が退職する際には、共済機構から直接退職金が支払われます。
退職金はいつ・どのように支給される?
退職金は、制度によっては複数の受取方法から選択できる場合もありますが、どのように受け取るかによって退職金にかかる税金の計算方法も変わります。
少しでも手取りを増やすためには、それらの違いを理解することが大切です。
ここでは、退職金の受け取り方と税金のかかり方の違い、受取時期について解説します。
退職金の受取方法は
3パターン
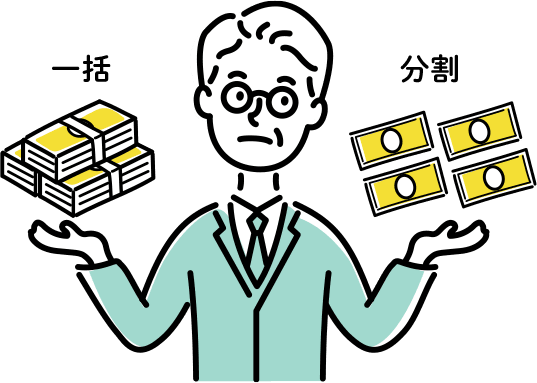
退職金の受取方法は、以下の3パターンがあります。
- 一時金受取り
- 年金受取り
- 「一時金受取り」と「年金受取り」の併用
それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
一時金受取り
一時金受取りとは、退職金を一括で受け取る方法のことです。受取りの際は「退職所得」に分類され、所得税や住民税がかかります。ただし、税金は会社で源泉徴収されるため、従業員が自分で確定申告をする必要はありません。
一時金受取りには「退職所得控除」という所得控除があるため、納めるべき税金は同じ金額の給与所得に比べ大きく軽減されるのが特徴です。退職所得控除は勤続年数によって異なり、勤続年数が長いほど控除額も大きくなります。
年金受取り
年金受取りとは、退職金を分割して受け取る方法のことです。受け取ったお金は「雑所得」に分類され、公的年金と合算した金額に対して所得税や住民税がかかります。
年金受取りは年金を運用し続けることで運用益が見込めるため、一時金受取りよりも受取総額が多くなる点がメリットです。
年金受取りの場合は「公的年金等控除」が適用されますが、控除額が小さいため、一時金で受け取った場合と比較すると、所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
一時金受取りと
年金受取りの併用
一時金受取りと年金受取りを併用する方法もあります。この場合では、一時金の部分に退職金控除、年金部分には公的年金等控除が適用されます。
退職金の一部を住宅ローン返済やリフォーム費用に充てたい場合など、まとまった金額を一時金で受け取ることで退職所得控除を活用しつつ税負担を抑え、残額を年金で受け取ることで退職後の生活費とすることも有効な選択肢です。
一時金受取りと年金受取りを併用する際には、退職金にかかる税金や退職後の社会保険料が変動するため、事前にシミュレーションした上でそれぞれの受取額について慎重に検討しましょう。
ただし、企業によっては一時金受取りと年金受取りの併用に対応していないケースもあるため、あらかじめ勤務先に確認しておきましょう。
退職金はいつ受け取れる?
退職金は、退職と同時に受け取れるわけではありません。働いている企業が退職金をどのように準備しているのかによって、受取りのタイミングは変わります。退職金の原資を自社で管理しているのであれば、比較的早く支給されます。
しかし、外部の金融機関(保険会社・信託銀行・共済など)で運用しながら準備している企業も多い傾向にあります。その場合は退職金支給のための手続きが必要なため、支給まで時間がかかります。
退職金が、会社の規定で定められた期日になっても支給されない場合は、会社に進捗状況の確認をするようにしましょう。
退職金にかかる税金の計算方法とは?
退職金を一時金で受け取る「退職所得」は分離課税として扱われるため、税金はほかの所得と分けて計算されます。計算式は次のとおりです。
退職所得=(収入金額※-退職所得控除額)× 1/2
- ※収入金額は源泉徴収前の金額
なお、退職所得控除額は勤続年数によって変わります。
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
- 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- ※勤続年数が1年に満たない端数は、1年に切り上げて計算
例えば、一般社員が30年勤務し、退職一時金1,700万円を受け取った場合の税金(所得税・住民税・復興特別所得税)の合計は15万1,050円です。
確定給付企業年金(DB)は、企業が従業員に約束した金額を退職時に支給する制度です。資産の運用責任は企業側が負います。
受取方法は、「一時金としてまとめて受け取る(一時金受取り)」「年金として分割で受け取る(年金受取り)」から選べます。あらかじめ受け取る金額が決まっているため、将来の資金計画が立てやすい点がメリットです。
- 退職一時金 1,700万円
- 退職所得控除(30年勤務) 800万円+70万円×(30-20年)=1,500万円
- 退職所得 (1,700万円-1,500万円)× 1/2 = 100万円
上記計算より -
- ①所得税 100万円×税率5% = 5万円
- ②復興特別所得税 5万円×2.1%= 1,050円
- ③住民税 100万円×10%=10万円 ※住民税は所得割のみで計算
また、退職する会社を通して「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を提出すれば、税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告をする必要はありません。
退職金の税負担を抑えつつ、受取りに関する手続きを簡単にするためにも、受取時に申告書の提出を忘れないようにしましょう。
退職金は以前よりも減っている
退職金は、長い老後生活を支える大切な資金のため、計画的に使っていかなければなりません。
例えば、高齢者施設への入居や、病気やケガで通院・入院が増えることもあるでしょう。そのような場合の支出に備えておくことが大切です。
しかし、以前と比較して、退職金の平均額は減っています。下表に、2008年と2018年、2023年の平均退職金額をまとめたので、見てみましょう。
【2008年・2018年・2023年】平均退職金額差
横スクロールできます。
| 2008年 | 2018年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 大学卒 | 2,323万円 | 1,983万円 | 1,896万円 |
| 高校卒 | 2,062万円 | 1,618万円 | 1,682万円 |
「令和5年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/dl/gaikyou.pdf)、
「退職給付(一時金・年金)の支給実態」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/08/3d.html)をもとに作成
2008年と2023年を比較すると、大学卒の平均退職金額は427万円、高校卒の平均退職金額は380万円減少しています。
この減少傾向が続いた場合、今の現役世代が将来もらえる退職金額は、さらに減ることになりかねません。充実した老後生活を送るためには、資産運用を検討するのも一つの手です。
退職金を補うために自分で老後資金を準備する方法
老後の生活を考えるうえで、退職金だけでは老後の生活資金が足りないと感じる方もいるかもしれません。ここでは、退職金を補うために自分で準備できる方法を紹介します。
定年後も働く
定年後も働いていれば、老後の生活資金を補うことができます。ただし、年金を受給しながら働く場合は、「在職老齢年金」に関する制度に注意が必要です。
在職老齢年金とは、60歳以上の老齢厚生年金の受給者のうち、会社などで働いている人を対象に、賃金に応じて老齢厚生年金を調整する仕組みのことです。具体的には、年金月額と賃金の合計が51万円を超える場合、老齢厚生年金の全部もしくは一部が支給停止となります。
定年後も働く場合は、年金と給与のバランスを意識しながら働き方を考えることが大切です。
資産運用する
定年後も働くことは老後資金対策に有効ですが、健康面や体力面から難しい可能性もあります。働く以外の選択肢として、資産運用も検討してみましょう。ここでは、NISA、iDeCo、個人年金保険について解説します。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)とは、毎年一定金額までの投資で得た利益が非課税になる制度です。
通常、投資で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等の売買益や配当金等に対しては税金がかかりません。
また、NISAには、政府の要件を満たした長期積立や分散投資に優れた投資信託を扱う「つみたて投資枠」と、上場株式やREIT、投資信託を扱う「成長投資枠」があります。
つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで使用でき、これら2つの投資枠を併用することで年間360万円まで非課税で投資ができます。
2024年からは非課税保有期間が無期限となったため、生涯にわたって退職金を運用できるのもメリットです。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金づくりを目的とする年金制度です。加入者が掛金を拠出して自ら金融商品を選んで運用を行い、積み立てた資金を60歳以降に、一括または分割で受け取ります。
iDeCoは以下のような税制優遇措置がある点が特徴です。
- 掛金が所得控除の対象となる
- 運用益が非課税となる
- 一括で受け取る場合:退職所得控除の対象となる
- 分割で受け取る場合:公的年金等控除の対象となる
上記のように、iDeCoは「掛金の拠出時」「運用時」「受取り時」の3つの段階で税制優遇を受けられます。
個人年金保険
個人年金保険とは、老後資金に備えるために民間の保険会社によって販売されている保険のことで、一般的に60歳もしくは65歳から個人年金を受け取ることが可能です。受け取り方には、一括で受け取る方法と、年金形式で毎年受け取る方法があります。
個人年金保険は、条件によっては、一般の生命保険料控除(死亡保障など)や介護医療保険料控除とは別枠の個人年金保険料控除として、税法上の優遇を受けられる点がメリットです。
また、個人年金保険は健康状態の告知や医師の診査が不要なケースが多いため、健康状態に不安を抱える方や既往症がある方でも申込みできます。
退職金を活かして資産運用する方法もある
「老後資金の準備ができずに退職を迎えてしまった」場合も、焦る必要はありません。退職金を活かして資産運用することも可能であるからです。
ここでは、退職金を得たあとに運用しやすい金融商品を紹介します。ただ、あくまで一例であり、正解はありません。実際に運用する際には商品や運用資金などご自身の目的や状況に合ったものを慎重に検討しましょう。
定期預金
定期預金とは、銀行などの金融機関が提供する金融商品の一つで、1ヵ月、1年、5年などの期間をあらかじめ指定してお金を預ける商品です。途中で引き出すためには中途解約する必要があり預入時に約束されていた利息を受け取れなくなることがありますが、満期まで保有する場合は普通預金より高い金利で預けておくことができるのが一般的です。
近年は日本銀行の利上げの影響で、定期預金の金利も上昇傾向にあります。利息を多く受け取れるため、金利が上昇する局面では、定期預金を活用するのも有効な選択肢といえます。
また、定期預金は預金保険制度の対象となっており、一定限度額までは元本保証されるため、原則として損失が出ません。老後の生活では病気やケガなどで急な出費が発生するケースもあります。万が一のために、まとまった金額を預金として置いておくことも重要です。
投資信託
投資信託は、投資家の資金を一つの大きな資金としてまとめ、運用のプロが株式や債券などに投資・運用する商品です。運用成果は投資家それぞれの投資金額に応じて分配されます。
投資信託は多様な国に投資でき、さまざまな銘柄を組み入れた商品を購入できるものもあるため、リスク分散しやすいのがメリットです。
先述のとおり、NISAを活用して投資すれば利益は非課税です。2024年以降は非課税保有期間が無制限となり、非課税保有限度額も以前と比較して大幅に増額されているため、退職金の運用を機に始めてみるのも一つの方法です。
りそなでは、退職金を受け取った方向けに、投資信託・ファンドラップと円定期預金を同時に申し込むことで定期預金の金利がお得になるプランを用意しています。
まとめ
退職金をどれくらい受け取れるのかは、会社の規模・勤続年数・職種・学歴・退職理由などで異なります。自分が勤めている会社の規定を確認しましょう。
近年、退職金は減少傾向にありますが、NISAやiDeCoなどを活用して資産運用を行い、自分で老後の生活資金を準備する方法もあります。
退職前から老後の生活を考え、早めに準備をはじめることが大切です。
退職金を受け取ってからでも、定期預金や投資信託などで運用する方法もあります。
しかし、退職金の管理や運用方法に不安がある方もいるかもしれません。そのような場合は、信頼できる金融機関に相談することをおすすめします。
りそなグループでは、退職金を有効に活用するための特別なプランを提供しています。投資商品と円定期預金の同時お預入れにより、一定期間、円定期預金の金利がアップするプランです。
定期預金で確実に資産を守り、利息も受け取りながら、将来を見据えた投資商品での運用もできます。
豊かな老後生活を送るために、このようなプランの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ライフプラン実現のために
いくら必要?
本記事は2025年8月6日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。