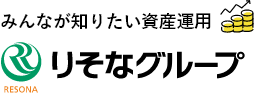退職金はいつ・どれくらいもらえる?受け取り方法や税金のポイント
公開日:2019/04/25
更新日:2024/04/08

退職の予定がある方のなかには、「退職金はいつ、どれくらいもらえるのか?」「退職金にかかる税金はどのように計算されるのか?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
退職金が支払われるタイミングは企業によって異なり、通常は就業規則の退職金規程に記載されています。また、退職金にかかる税金の計算方法は、受け取り方法によって異なります。
老後の資金計画を考える際は、退職金の受け取り時期や税金などを把握し、「受け取った退職金をどのように活用するのか」を事前に考えておくことが大切です。
この記事では、退職金を受け取るタイミングや相場、退職金にかかる税金などについて解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。
現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。
- ※りそなグループが監修しています
退職金がいつ支払われるかは企業による

退職金の支払い時期などは、明確に定められているわけではありません。そのため、いつ支払うのかは企業が自由に決めることができます。ただ、自由ではあるものの、一般的には退職から1~2ヵ月後に支払われることが多いようです。また、企業によっては、退職時の書類確認や承認などで時間がかかり、2ヵ月以上かかる場合もあります。
この退職金がいつもらえるかについては、通常は就業規則の退職金規程に記載されています。就業規則を確認したり、実際に退職をした会社の同僚などに体験談を聞いてみたりするとよいかもしれません。会社側に直接聞けるのであれば、退職金がもらえる時期の目安はある程度正確にわかるでしょう。
まとまった退職金を見込めるなら老後の生活費に充てたり、次の仕事が決まるまでの生活費に充てたりと、家計の計画を立てる上でも退職金がいつもらえるかという情報は必要です。万一、退職金の受け取りまで時間がかかる場合は、手持ちの貯蓄で対応しなければならなくなりますので、退職前にしっかりと計画を立てておくことをおすすめします。
特に、老後の生活費に充てる場合は、退職金で資産運用をしながら増やす方法も考えられるでしょう。具体的な金額をシミュレーションしながら計画してみてはいかがでしょうか。
退職金の相場はいくら?
退職金はいったいどれくらいになるのか、実際にもらえる退職金の金額は非常に気になるところでしょう。退職金の金額は、退職までの勤続年数、勤務時の実績などで異なるのが一般的です。
また、退職金制度は各企業が独自に定めている規則であるため、受け取れる退職金は企業によって異なります。ここでは、退職金の相場として東京都産業労働局の資料を参考に解説します。
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」のモデル退職金によると、卒業後すぐに入社し、普通の能力・成績で勤務した場合、自己都合退職で高校卒の勤続10年(年齢28歳)の退職金は90万7,000円、高専・短大卒の勤続10年(年齢30歳)の退職金は98万7,000円、大学卒の勤続10年(年齢32歳)の退職金は112万1,000円となっています。
また、定年まで勤続する会社都合退職で高校卒の退職金は994万円、高専・短大卒の退職金は983万2,000円、大学卒の退職金は1,091万8,000円となっています。
| 学歴 | 勤続年数 | 自己都合退職 支給額 |
会社都合退職 支給額 |
|---|---|---|---|
| 高校卒 | 10年 | 90万7,000円 | 122万3,000円 |
| 20年 | 272万9,000円 | 328万4,000円 | |
| 定年 | — | 994万円 | |
| 高専・短大卒 | 10年 | 98万7,000円 | 126万9,000円 |
| 20年 | 292万4,000円 | 346万5,000円 | |
| 定年 | — | 983万2,000円 | |
| 大学卒 | 10年 | 112万1,000円 | 149万8,000円 |
| 20年 | 343万1,000円 | 414万7,000円 | |
| 定年 | — | 1,091万8,000円 |
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」Ⅱ.調査結果の概要 8.モデル退職金
大学卒の社員が22歳で入社し、60歳で定年を迎えるとすると、勤続年数は約38年になります。単純に勤務年数でいえば、定年までは10年勤続の3.8倍の年数になりますが、退職金で考えると、10年勤続(会社都合)149万8,000円の約7.3倍の金額になっています。勤務年数が長くなればなるほど、退職金の金額が増えることがわかります。
上記の表は東京都産業労働局のモデル退職金になり、入社時の学歴と勤務年数をみることで、ある程度の目安にはなりますが、通常は企業が独自に退職金制度を設けていますので、正確な金額は就業規則などで確認することをおすすめします。
中小企業の場合「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」があることも
大手企業などは、退職金となる資金を見込んで会社予算の中で確保しており、独自の退職金制度を設けていますが、中小企業の場合は、常に別途の退職金を確保しておくことが難しいものです。そこで、中小企業に向けた「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」という助成制度が用意されています。
中退共制度とは?
中退共制度とは、中小企業の相互共済と国からの援助によって設けられた退職金制度です。企業は毎月の掛金を納付して積立をし、社員が退職したときには中退共から支払われるという仕組みです。
勤務している企業が中退共に加入しているかどうかは、一般的には就業規則に記載されています。中退共の場合、掛金の満額をいくらに設定しているかで、月々の掛金が変わりますが、掛金は企業が全額負担しているため、社員は掛金の満額を知らないケースがあります。定年退職まで勤務したときには、いくらの退職金になる想定なのかは、事前に確認をしておくと安心です。
中退共制度を利用した退職金はいつ支払われる?
中退共制度を利用した退職金は、「支払いの請求を受け付けてから約4週間」が目安となります。「退職日から約4週間」ではなく、「請求されてから約4週間」であることがポイントです。つまり、請求が遅くなればなるほど、退職金受取時期も遅くなるということです。
なお、退職金は退職された月までの掛金が入金されたことが確認されてから支払いの手続きに進むことになります。そのため、会社が退職月分の掛金納付を遅れると、支払いの手続きが遅くなり、2ヵ月以上かかることがあります。
退職金の支払い金額と振込み予定日は企業にも通知されるため、遅れていると何か不備があったのかと企業側に思われる可能性があります。退職金共済手帳を受け取ったら速やかに手続きを進めましょう。
退職金3つの受け取り方法
ここからは、退職金の3つの受け取り方法について見ていきましょう。
一時金受け取り
一時金受け取りとは、退職金を一括で受け取る方法です。一度で現金を手にできるメリットがありますが、使いすぎに注意しなければなりません。
年金受け取り
年金受け取りは、退職金を分割して年金のように受け取る方法です。年金受け取りで手にする退職金の総額は、一時金受け取りよりも多くなります。
これは、まだ受け取っていない年金原資が一定の利率で運用されると仮定した際の運用益部分が上乗せされるためです。
年金受け取りは、退職金を分割して受け取るため、一時金受け取りのように使いすぎるリスクが軽減されます。
一時金受け取りと
年金受け取りの併用
ある程度の一時金を退職時に受け取り、残りの金額は年金方式で受け取る方法です。
例えば、一時金を住宅ローンの返済や新たな事業資金などに活用し、残りの退職金は年金受け取りにして、老後の生活資金に活用するなど、ライフプランに合わせた使い方ができます。
退職金にかかる税金は受け取り方法によって異なる
次に、退職金にかかる税金を受け取り方法別に解説します。
一時金受け取りの場合
一時金で受け取った退職金は「退職所得」として計算され、所得税や住民税などが課されます。退職金に社会保険料はかかりません。退職所得の計算式を見てみましょう。
- 退職所得=(退職金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、以下の計算式で算出されます。
- 勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円として計算)
- 勤続20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数に1年に満たない期間があるときは、端数を切り上げます。例えば、勤続年数が8年5ヵ月の場合、勤続年数は9年として計算します。退職所得が退職所得控除の範囲内であれば、税金はかかりません。
なお、退職所得には、以下のように所得税と住民税、復興特別所得税も課されます。
- 所得税:退職所得×所得税率(※)
- 住民税:課税退職所得額×10%
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%
※退職所得にかかる所得税率は、次のとおりです。
横スクロールできます。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
出典:国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)退職金と税
また、勤続年数が5年以下の従業員は、短期退職手当等に該当するため、「退職金額-退職所得控除額」の300万円を超える部分の金額に対しては1/2を乗じることはできません。
年金受け取りの場合
退職金を年金受け取りにした場合は、「雑所得」として計算します。
雑所得は退職金のほか、確定拠出年金や確定給付企業年金などの企業年金、公的年金などが含まれるため、まずは雑所得の合算金額を求めます。公的年金等にかかる雑所得の計算式を見てみましょう。
- 公的年金等に係る雑所得=年金受け取りの退職金や公的年金などの所得金額-公的年金等控除額
雑所得の公的年金等控除額は、次のとおりです。
横スクロールできます。
| 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | ||
|---|---|---|
| 年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-60万円 | |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額-110万円 | |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 | |
所得税・住民税・復興特別所得税は、一時金受け取りと同様の計算式で求めます。
なお、年金受け取りの場合は、国民健康保険料や国民年金保険料の負担が生じます。そのため、年金受け取りでは、退職金にかかる税金だけでなく、社会保険料の負担を考えておくことが大切です。
一時金受け取りと年金受け取りの併用の場合
一時金受け取りの部分は退職所得、年金受け取りの部分は雑所得の対象です。そのため、退職所得控除と公的年金等控除のどちらも活用できます。
一時金と年金の金額配分は、企業や管理機関の条件によって異なります。一時金と年金の金額配分を決定する際は、条件を確認したうえで、シミュレーションなどを活用して検討しましょう。
退職金を受け取ったら確定申告は必要?
次に、退職金受け取り方法別の確定申告の必要性について解説します。
一時金で受け取る場合
勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、原則として確定申告は必要ありません。これは、書類を提出することで退職金に退職所得控除が適用され、所得税・住民税・復興特別所得税が源泉徴収されるためです。
ただし、寄附金控除や医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする場合は、確定申告書に退職所得の記載が必要です。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の総額から一律20.42%の源泉徴収税が控除されます。源泉徴収税が本来の納税額よりも多い場合は、退職金を受け取った翌年の1月1日から5年以内に還付申告をすることで精算することができます。
年金方式で受け取る場合
その年の公的年金等に係る雑所得が400万円以下、かつ「公的年金等に係る雑所得以外」の所得金額が20万円以下の場合は、所得税・復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。
「公的年金等に係る雑所得以外」には、給与所得、配当所得、一時所得、公的年金等以外の雑所得などが含まれます。
もらえるはずの退職金が
支払われない場合は
労働基準監督署へ
ごくまれに自己都合の退職だからという理由で退職金を支払わなかったり、退職金の金額を減額されたりするケースがあるようです。このように、もしも企業側が退職金の支払いをしなかったり、退職金の支払いが著しく遅れていたりする場合は、最寄りの「労働基準監督署」へ。
労働基準監督署から企業に対して、就業規則に沿った退職金の支払いについて本人のかわりに交渉してくれますので、困ったときには相談してみましょう。
退職金の預け先を考えよう
定年後の収入源は、おもに公的年金になる方が多いでしょう。まとまった退職金を受け取れるのであれば、ゆとりのあるセカンドライフのためにも、少しでも資産を増やせる預け先を選ぶことが大切です。大手銀行の中には、退職金専用の特別金利プランを用意しているところもあります。
60歳で定年退職を迎え、平均余命まで生きるとすれば、男性は23.59年、女性は28.84年分※のお金を準備しておかなければなりません。老後の安心のためにも、資産管理は重要です。
- ※厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」
退職金を増やすために
資産運用をはじめるのも
おすすめ
多くの銀行で退職者向けのサービスを扱っていますが、どこがどう違うのかわからない方、投資初心者の方も多いでしょう。「老後のために資金を増やしたいけど、誰に相談したらいい?」「資産運用に興味はあるけど、不勉強でよくわからない」という方は、お気軽にりそなの窓口にお越しください。
りそなは、半世紀にわたる資産運用実績が認められ、「マーサーMPA(JAPAN)アワード」や「R&Iファンド大賞」など、外部機関からも高い評価を得ていますので、安心してご相談いただけます。
一人一人異なるお金の使い方や老後の暮らしに合わせて、さまざまなニーズにお応えできるようなプランを用意しています。退職金を受け取る前でも、口座がない方でも無料でご相談可能です。老後の不安を払拭するためにも、まずは退職金をどうするか考えることからはじめてみませんか。
まとめ
退職金がもらえるタイミングや金額は、企業によって異なります。今回ご紹介した相場もあくまで目安ですので、会社に直接問合せるのが最も正確でしょう。また、退職金を受け取るには、本人が手続きをするケースもあり、手続きが遅れると退職金の受け取りが数ヵ月も遅れることもありますので、できるだけスムーズに手続きをすすめることが重要です。
退職金の受け取り方法には、「一時金受け取り」「年金受け取り」「一時金受け取りと年金受け取りの併用」の3つがあり、それぞれ税金のかかり方が異なるため、ライフプランに合わせた受け取り方法を考えておくことが大切です。
そして、ある程度まとまった退職金を受け取る場合は、退職金の資産運用を視野にいれて老後の計画を立てましょう。資産運用にはいろいろな方法があります。りそなには退職金の運用に活用できるプランがあり、老後の暮らし方に合わせて資産運用を相談できますので、退職後の生活に備えてしっかりと計画をしましょう。
【りそな銀行・埼玉りそな銀行】
【関西みらい銀行】
何からすればいいかわからない
という方は…

4問で運用方法・商品を
サクッと診断

本記事は2024年4月8日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。