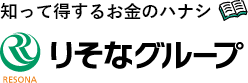子どもの教育資金はいくら必要?幼稚園から大学までの費用相場と貯蓄方法
公開日:2022/04/03
更新日:2025/11/21
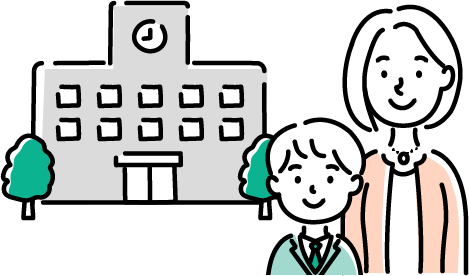
子どもを持つ親にとって気になる教育費。教育資金は、早めに取りかかれば準備しやすいお金です。しかし、進路によって必要になる金額が異なることは知っていても、「どう準備していけばいいのかわからない」という人は多いかもしれません。
教育資金を準備する際は、必要な費用の目安を知り、自分に合った貯蓄方法を検討することが重要です。この記事では、幼稚園から大学までの段階別の教育資金の目安や国から受けられる支援の種類、教育資金の準備方法などについて解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
教育資金はいくらかかる?
幼稚園から大学までの段階別の費用の目安

文部科学省が公表している「令和5年度子供の学習費調査」を参考に、幼稚園から大学までにかかる教育資金について、年間金額の目安を確認していきましょう。
幼稚園でかかる年間の教育費
公立幼稚園では1年間で約18万5,000円、私立幼稚園では約34万7,000円かかっています。以下は、公立幼稚園と私立幼稚園にかかる年間の教育費の内訳です。
| 公立幼稚園 | 私立幼稚園 | |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 6万9,362円 | 15万4,062円 |
| 学校給食費 | 1万5,235円 | 3万5,741円 |
| 学校外活動費 | 10万49円 | 15万7,535円 |
| 学習費総額 | 18万4,646円 | 34万7,338円 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとにりそなグループ作成
公立または私立のどちらに入園するかによって、3年間で最大約48万6,000円の差が出る計算です。
また、学習費には、授業料や入学金に加えて、設備費用、学用品費、PTA会費など、学校生活を送るうえで必要となるさまざまな支出が含まれます。
そのため『幼児教育の無償化』と言っても、実際の負担額がゼロになるわけではありません。制度の対象外となる費用もあるため、総額としてどの程度かかるのかを把握しておくことが大切です。
小学校でかかる年間の教育費
公立小学校では年間の学習費が約33万6,000円なのに対し、私立小学校では約182万8,000円と、公立小学校の約5.4倍にものぼります。
特に「学校教育費」の差が顕著で、私立小学校は公立小学校の約12.9倍です。学習塾や家庭教師といった学校外活動費も私立小学校のほうが高く、家庭の負担が大きいことがわかります。
| 公立小学校 | 私立小学校 | |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 8万1,753円 | 105万4,083円 |
| 学校給食費 | 3万8,405円 | 5万3,601円 |
| 学校外活動費 | 21万6,107円 | 72万428円 |
| 学習費総額 | 33万6,265円 | 182万8,112円 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとにりそなグループ作成
また、小学校に進学するとともに、ランドセルや学習机などの購入費用もかかります。共働きの場合は、学童保育を利用する可能性も考慮して、これらの費用を含めてシミュレーションしておくとよいでしょう。
中学校でかかる年間の教育費
公立中学校では約54万2,000円、私立中学校では約156万円かかっています。在学期間は3年間ですが、公立・私立ともに、補助学習費や習い事などの学校外活動費として年平均40万円ほどかけている家庭が多い傾向です。
| 公立中学校 | 私立中学校 | |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 15万747円 | 112万8,061円 |
| 学校給食費 | 3万5,667円 | 9,317円 |
| 学校外活動費 | 35万6,061円 | 42万2,981円 |
| 学習費総額 | 54万2,475円 | 156万359円 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとにりそなグループ作成
公立の場合、学校教育費そのものは私立ほど多額ではありませんが、中学校在学中には学習塾や家庭教師などに費用がかかるケースがあります。
塾通いの目的は基礎学力の定着や学習習慣の確立などさまざまであり、高校受験のためだけとは限りません。
ただし、多くの生徒にとって高校受験が初めての本格的な受験となるため、結果的に追加の教育費が必要になることも少なくありません。そうした多様な理由による支出をふまえ、余裕をもった準備をしておくと安心です。
高校でかかる年間の教育費
在学期間は3年間で、公立高等学校では約59万8,000円、私立高等学校では約103万円かかっています。高校に進学すると、国公立の中学校までは無償だった教科書代や授業料がかかる点を押さえておきましょう。
| 公立高等学校(全日制) | 私立高等学校(全日制) | |
|---|---|---|
| 学校教育費 | 35万1,452円 | 76万6,490円 |
| 学校外活動費 | 24万6,300円 | 26万3,793円 |
| 学習費総額 | 59万7,752円 | 103万283円 |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとにりそなグループ作成
また、近年ではICT教育の導入などで生徒一人あたり1台タブレットを使い、各家庭で用意しなければならない高校もあります。
大学でかかる年間の教育費
文部科学省ホームページ「国公私立大学の授業料等の推移(令和5年度)」によると、2023年度入学者における国立大学と公立大学の初年度学生納付金は次のとおりです。
| 国立大学 | 公立大学※ | |
|---|---|---|
| 入学金 | 28万2,000円 | 37万4,371円 |
| 授業料 | 53万5,800円 | 53万6,191円 |
| 4年間総額 | 242万5,200円 | 251万9,135円 |
出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」をもとにりそなグループ作成
- ※公立大学の入学金は他地域からの入学者の金額
私立大学の場合、施設設備費の負担があり、授業料同様に毎年度支払う必要があります。
| 授業料 | 入学料 | 施設設備費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 文科系学部 | 82万7,135円 | 22万3,867円 | 14万3,838円 | 119万4,841円 |
| 理科系学部 | 116万2,738円 | 23万4,756円 | 13万2,956円 | 153万451円 |
| 医歯系学部 | 286万3,713円 | 107万7,425円 | 88万566円 | 482万1,704円 |
| その他学部 | 97万7,635円 | 25万1,164円 | 23万1,743円 | 146万542円 |
横スクロールできます。
出典:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」をもとにりそなグループ作成
私立大学では学部系統によって学費に大きな差があり、一般的に文系学部より理系学部、理系学部より医歯系学部のほうが高額になる傾向があります。
大学の給付金に加えて、自宅外から通学する場合には家賃や生活費といった、さまざまな費用も考えておかなければなりません。具体的には、アパートやマンションの家賃、光熱費、食費、日用品費などの生活費が月々発生します。
入居時の敷金・礼金、家具・家電の購入費、引越し費用なども初期費用として必要です。これらの費用は地域によって異なるため、進学先の生活コストを事前に調査しておくとよいでしょう。
【幼稚園~大学】国から受けられる教育資金の支援
大きな金額が必要となる教育費ですが、最近では、幼児教育や高等教育などで、政府による教育費の支援制度が実施されています。国からどのような教育資金の支援が受けられるのかを知り、将来必要となる金額を具体的にイメージすることが大切です。
幼稚園
3歳から5歳の子どもが幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する場合、利用料は原則として無償です。幼稚園については、月額2万5,700円が上限となり、これを上回る場合は保護者が負担します。
ただし、食材料費、行事費、通園送迎費などは自己負担となるため、注意しましょう。なお、0歳から2歳の子どもについては住民税非課税世帯に限り、利用料は無償です。
無償化の条件は、細かく設定されていますので、入園前にしっかりチェックしておきましょう。
小学校~中学校
義務教育期間中、国公立学校では授業料や教材費は無償です。
生活保護を受給している人、またはそれに準ずる程度に経済的に困窮していると認められた場合には就学援助を受けられることがあります。就学援助制度とは、小・中学校への就学にあたり学用品や学校給食、修学旅行費などの支払いが困難な人に対して自治体がこれら費用を支援する制度です。具体的な補助の内容や金額、対象となる所得基準などは、自治体や学年によって異なります。
高校
高等学校等就学支援金制度
所得要件を満たす家庭の高校等へ通う生徒を対象に、授業料に充てる支援金を国が学校に支給することで、教育費負担を軽減し、教育機会の均等を図る制度です。
制度の所得要件を満たさない世帯も対象となる臨時支援金が新たに設けられ、一定の基準額(上限年額11万8,800円)が国公私立共通で支給されます。
高校生等奨学給付金
修学旅行費や教科書などの教材費、PTA会費など、授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金が支給される制度もあります。本給付金は、返済の必要がありません。金額は、生徒一人あたり年間約3万~15万円。生活保護受給世帯および住民税所得割の非課税世帯や、家計が急変して非課税相当になった世帯が対象です。
大学
授業料・入学金の減免
2020年4月からはじまった「高等教育の修学支援新制度」により、一定の要件を満たした大学、短期大学、高等専門学校、専門学校では、授業料や入学金の免除・減額が受けられるようになりました。さらに、返還不要の給付型奨学金も組み合わせることで、経済的な理由で進学をあきらめる学生を支援し、高等教育の無償化を進めています。
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生が対象です。実際には、世帯の子どもの人数や家族構成によって年収目安が変わります。減免される金額は、進学先ごとに定められている授業料免除額を上限に、世帯収入に応じて上限額の満額、3分の2または3分の1などです。なお、支援の継続にあたっては、一定の学修意欲と学修成果をみたす必要があります。
なお、2025年度から多子世帯(扶養する子どもが3人以上)に対しては、所得制限を設けずに入学金と授業料が規定上限まで減額・免除されます。
給付型奨学金
日本学生支援機構奨学金事業は、学業に専念することを目的として、返済不要な奨学金として支援しています。授業料以外の学生生活を送るのに必要な学生生活費へも充当できます。対象となるのは、授業料等の減免制度の収入目安と同様です。給付型奨学金の金額は、進学先や「自宅からの通学か」「自宅外からの通学か」などによって異なります。
2025年度からは多子世帯(扶養する子どもが3人以上)について、授業料や入学金における支援が拡充されました。
児童手当
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している世帯に対して支給される手当金です。金額は、子どもの年齢によって次のように決まっています。
- 3歳未満:月額1万5,000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上:高校生年代まで:月額1万円(第3子以降は3万円)
児童手当の支給は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に行われ、各支給月において前月分までの2ヵ月分がまとめて給付されます。
教育資金の準備方法とメリット・デメリット

教育資金の目安を踏まえたうえで、家族で進路について話し合い、早いうちから準備していきましょう。大切なことは、目標金額を設定しその金額に向けて毎月一定額を確実にためていくことです。一度銀行などに申込めば、あとは自動で口座振り替えされる以下のような商品で先取り貯蓄をしていくのがおすすめです。
積立定期
積立定期は、毎月金額を決めて銀行の定期預金に積み立てしていく方法です。毎月定期的にためていくことで教育資金は確実に積み上がっていきます。元本割れのリスクもないため、確実な資金準備が実現するでしょう。
例えば、大学進学費用に備えて18歳までに500万円ためたい場合、子どもが産まれてすぐから積み立てをはじめると毎月約2万3,150円を積み立てていくことで実現できます。
メリット
積立定期預金の申込みは、「毎月1,000円~」「毎月5,000円以上」など、金融機関によって取扱金額が異なります。途中での増額や臨時で追加預入れすることもできるため、昇給やボーナスなどの臨時収入があったときなど、生活の変動に対応させやすい点はメリットです。
積立定期は銀行預金のため、投資信託などに比べると必要時に必要な額を引出しやすいメリットもあります。子どもの教育費準備のための積立てなので、できれば引出さないに越したことはありません。
しかし、例えば受験費用が思った以上にかかる、あるいは予定外にお金が必要になることもあるため、引出しが容易なのは安心です。安心という面では、元本が確定されていることも魅力となるでしょう。積立定期は、預金保険機構の対象です。
ただし、申込み時の満期設定の仕方によっては、満期前に解約することで期限前解約利率もしくは普通預金の利率が適用されて、予定していたよりも利息の受取りが少なくなる場合があります。商品自体に元本割れリスクはなくても、予定よりも利息が少ないということにならないように注意が必要です。
デメリット
引出ししやすいことは、デメリットにもなり得ます。進学のタイミングなどで、まとまった額が必要となり引出すケースも少なくありません。引出す金額や頻度をきちんと管理しておかないと、もっとも資金が必要とされる大学進学時に確実に資金を確保することが難しくなってしまいます。
また、付与された利息には20.315%(復興特別所得税含む)の税金がかかり、利息の手取り金額は上述した金額より少なくなります。以下で紹介する、他の制度のような税制メリットもありません。
なお、親の口座とお子さまの教育資金用の口座を分けると、管理もしやすくなります。将来のためにお子さまの口座を作っておくと良いでしょう。
NISAを活用した資産形成
教育資金の準備に投資信託を利用する方法もあります。投資信託とは、運用の専門家である投資信託運用会社が多くの投資家から資金を集めてファンド(投資信託)を作り、運用損益を投資家に還元するという金融商品です。
銀行預金のように金利は決められておらず、元本保証もされていませんが、銀行預金よりも高い収益が期待できます。例えば、年利回り1%で運用できる場合、子どもが産まれてからすぐに毎月約2万1,123円を積立てていれば、18歳までに500万円をためることが可能です。年利回り2%なら、積立額は約1万9,251円に下がります。
この際に活用したいのが長期的な資産形成に適した少額投資非課税制度(NISA)です。
NISAの年間の非課税投資枠は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」が240万円、合わせて年間最大360万円までとされています。
年間360万円までの投資に対する配当金や運用益に税金がかかりません。
また非課税で保有できる期間は無期限です。そのため、生涯にわたって1,800万円まで(成長投資枠は1,200万円まで)非課税で保有し続けることができます。途中で投資信託を売却しても1,800万円に到達するまではその分の金額枠の再利用が可能です。
受験や入学費用など中学・高校・大学と進学の過程で必要となる資金を使った場合でも、翌年度以降に再度同じ枠を利用し、資産形成していけます。子どもが独立するまでは、教育資金準備をメインとし、独立後には自分のセカンドライフ資金準備に利用するのもおすすめです。
メリット
NISAは、少額ではじめられるため、投資初心者でも取り組みやすいことがメリットです。また、積立額に応じて「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を使い分けられるメリットもあります。
例えば、毎月の積立金額が10万円未満の場合はつみたて投資枠を活用し、ボーナスなどスポットで余剰資金ができた際に成長投資枠を使う方法も選択肢の一つです。
資産運用には、値下がりリスクもあるため、教育資金づくりの場合はリスクが低めの投資信託を選ぶことも大切でしょう。長期で保有し続けることでリスクの低下につながります。
デメリット
デメリットは、元本が保証されていないことです。また、NISAを利用した資産運用では、売却等の取引により損失が発生した場合、本来できるはずの損益通算や繰越控除ができません。これは、簡単にいうと他の運用で出た利益分と損失分を相殺して、全体的な利益を小さくする仕組みです。
活用できればその分、税金も少なくて済みます。しかし、NISAの場合、このような税制上の恩恵を受けられません。
学資保険
学資保険は、民間生命保険会社が販売する、学費をためる目的の貯蓄と保障を兼ね備えた保険です。子どもを被保険者、親を契約者として契約します。子どもが契約時に設定した年齢を迎えると、「満期保険金」や「お祝い金」として、契約で定めた金額を一時金または年金形式で受取ることが可能です。
なお、保険料払込期間中に契約者が死亡すると、その後の保険料の払込みは必要なくなりますが、保障はそのまま継続されます。そのため、契約時に定めた満期保険金やお祝い金はそのまま受取ることが可能です。
メリット
保険料として契約時に定めた方法で支払いが必要となるため、着実に教育資金をためられるのがメリットです。また、保険料支払時と保険金(お祝い金)受取時の両方で、税金を抑えることにつながります。
まず、支払った保険料の分は生命保険料控除が適用されるため、所得税の負担軽減策になります。さらに、一括で受取る満期保険金は、一時所得とみなされ(契約者と受取人が同一人物の場合)、差益部分(受取金額-既払込保険料)が50万円まで所得税がかかりません。
デメリット
学資保険の満期保険金等の額は、契約時に定められます。そのため、将来的に物価変動(インフレ)があると、受取金の価値が目減りする可能性がある点はデメリットです。また、契約で定められた満期(お祝い金受取り時期)まで原則払出しができず、途中でお金を払出す場合は解約となりかねません。
解約すると元本割れのリスクがあり、(医療保障重視など)商品の特徴によっては解約返戻金が支払った保険料を下回る可能性があります。ちなみに、低金利の現状下では満期まで継続した場合でも返戻率が100%未満となることもあるため、注意が必要です。
満期保険金、およびお祝い金として受取るお金の総額が、払込保険料総額よりも少なくならないか、契約前に保険設計書などでしっかりと確認しておきましょう。他にも、万が一保険会社が経営破たんした場合は、契約で定めた額よりも受取れる保険金が減る可能性があります。
祖父母からの支援「教育資金の一括贈与制度」
教育資金の一括贈与制度は、祖父母や親による30歳未満の子どもや孫へ「教育資金」を非課税で贈与できる制度です。
非課税限度額は、受贈者一人につき1,500万円までとされています。贈与を受けた際に金融機関で一定の手続きのもと、専用の教育資金口座を開設することで、贈与を受けた人に贈与税がかかりません。
口座開設後は、受贈者である子や孫が教育資金であることを証明できる領収書や請求書を提出することで、口座から非課税でお金を引出せます。対象となる教育資金は、入学金や授業料、給食費、修学旅行費など学校に支払う費用が中心です。
それ以外にも通学交通費や学用品の購入、塾、スポーツ、音楽などの習い事にも適用されます。ただし、学習塾・習い事など学校以外への支払いは500万円までです。
なお、本制度の適用は2026年3月31日までとされています。
メリット
メリットは、非課税で贈与を受けられる金額が1,500万円までと大きいことです。あらかじめまとまった額の資金を確保できるため、経済的にためらうことなく進路の選択がしやすくなります。
デメリット
デメリットは、原則として受贈者が30歳になると制度が終了してしまうことです。
制度終了時点で使い切っていない贈与されたお金がある場合、そのお金が贈与税の課税対象となります。贈与税の基礎控除額を超えて残っている場合は、贈与税がかかってしまうため、注意しましょう。
また、受贈者が30歳になるまでに贈与者が死亡した場合、残額が相続税の対象となるケースもあります。贈与者の年齢や、今後の使い道も確認しながら贈与することが必要です。
教育資金をためるために重要なこと
ここまで、教育資金を準備するための方法を見てきました。ここからは、教育資金をためる際のポイントを確認していきましょう。
 1つの方法に集中させず、
1つの方法に集中させず、
金融商品を分けて準備する
利息は期待できないけれど元本が確実な積立定期と、資産の膨らみを期待できるけれども元本割れのリスクもある投資商品には、どちらもメリットとデメリットがあります。準備途中で親に万が一のことがあっても、予定通りに教育資金を準備できる保険商品も同様です。
準備が必要となる資金額や、リスク許容度に合わせ、バランスを調整しながら複数商品に分けて準備していきましょう。例えば、子どもが小さいうちには投資信託の割合を大きめにすることも方法の一つです。また、進学が近づくにつれて資金確保の確実性を高めるために、徐々に定期預金にシフトさせていくという方法もあります。
 少しでも早く資金の
少しでも早く資金の
準備に取りかかる
もっとも大切なのは、少しでも早く準備に取りかかることです。金利が上がるほど、月々の積立額が少なくて済むことは先に説明したとおりですが、物価やローン金利等が上昇するリスクもあります。大切な子どもの教育資金ですから、できるだけリスクを抑えつつ確実に準備していきたいものです。
金利が低めでも長期間かけて準備すればそれだけ複利効果を得られます。児童手当を積立てに充当するなど、教育資金準備の意識をしっかり持って、早くから準備に取りかかるのがよいでしょう。
 必要に応じて教育ローンの
必要に応じて教育ローンの
利用を検討する
金融商品で準備を進めながら、必要に応じて教育ローンの利用を検討することも選択肢の一つです。教育ローンは、授業料や入学金、制服代など教育費用に関するあらゆる用途で利用できます。
そのため、「受験する学校数が増えた」「志望校が変わり多くの資金が必要になった」「遠方の大学に進学することになり仕送りが必要になった」など、予定以上の資金が必要な場面にも対応しやすいことが特徴です。
教育ローンとひとくちにいっても、国による教育ローンと民間金融機関による教育ローンがあり、それぞれに特徴や利用条件に違いがあります。そのため、事前に確認して申込むことが必要です。なお、大学や専門学校と提携した提携教育ローンもありますが、金利が高めのケースがあるため注意しましょう。
まとめ
私立を選ぶと負担は数倍にも膨らむ傾向があり、「公立中心」「私立中心」の進路選択では、教育資金の見込みが大きく異なります。
また、大学進学では進学先の学部や住まいによって、かかる費用の総額には大きな差が出るため注意が必要です。
幼児教育の無償化や高校無償化制度など、教育費に対する国の支援制度もありますが、上限金額が設けられている場合もありますので、ご自身でしっかりと準備しておくことが大切です。
教育資金準備には、積立定期や投資信託、学資保険などを利用する方法があります。それぞれのメリット・デメリットを知り、バランス良くそれぞれの金融商品を利用していきましょう。
自分で教育資金を準備するのと並行し、教育ローンを活用する方法もあります。教育費用に関する幅広い用途に利用できるため、志望校を絞りきれず、いくら準備すればいいかわからない場合にも安心です。教育資金が足りない場合には、りそなの教育ローンも検討してみてはいかがでしょうか。
来店不要
スマホアプリで
最短翌営業日に口座開設
マイナンバーカードを
読み取り本人確認!

運転免許証・在留カードなどの撮影でもOK!
- ※カードがお手元に届くまで、約2週間ほどかかります。
約30分でカード発行
店舗ですぐ!口座開設
印鑑不要・※全店平日17時まで営業
※関西みらい銀行の一部店舗を除きます
- ※即時発行は所定の顔写真つき本人確認資料の場合に限ります。
- ※店舗やお取引内容によっては30分以上お時間をいただくこともございます。お時間の余裕を持っておこしくださいませ。
本記事は2025年11月21日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。