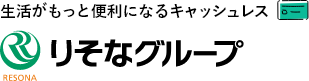会社員でも確定申告するべき?副業は関係ある?申告が必要な人・必要ない人
公開日:2025/02/12

「会社員で確定申告をするべきか」「副業している場合は確定申告が必要なのか」と気になる人もいるのではないでしょうか。
会社員の場合は、会社側が年末調整により正しい所得税額を計算して税務署へ申告するため、基本的に自分で確定申告をする必要はありません。しかし、副業で得た所得が20万円を超えている場合など、ケースによっては確定申告をしなければならないことがあるため、注意が必要です。
本記事では、確定申告の概要に加え、会社員で確定申告が必要な人・確定申告をすることでメリットがある人・確定申告が不要な人についてケース別に解説します。また、クレジットカードを利用して確定申告を効率よく行う方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
- ※りそなグループが監修しています
会社員でも知っておきたい「確定申告」とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間で得た所得に対する税額を確定・納付する手続きを指します。申告時期は、原則として所得があった年の翌年2月16日~3月15日です。
「所得がある人」は原則、確定申告をしなければなりません。ただし、会社員や公務員などの給与所得者は勤務先が年末調整によって正しい所得税額を代わりに税務署へ申告しているため、確定申告が不要なケースがほとんどです。
しかし、会社員でも確定申告が必要な人や、確定申告によって税金の還付を受け取れる人もいます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
会社員で確定申告が必要な人・5つのケース
会社員で確定申告をしなければならないケースを5つ紹介します。
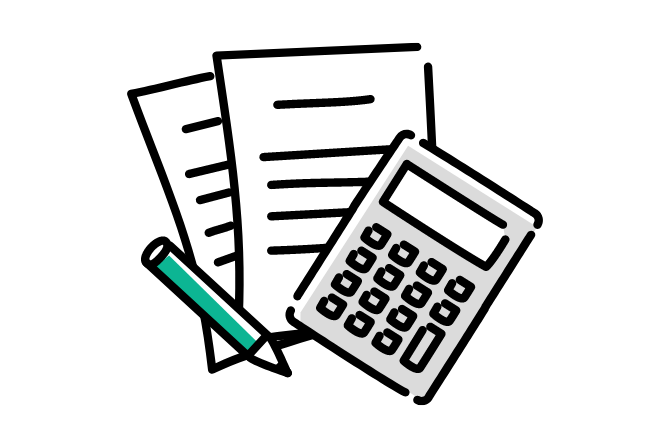
 副業などの所得が20万円を超えている人
副業などの所得が20万円を超えている人
副業など、本業以外の所得(給与所得・退職所得を除く)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。所得とは、副業などで得た収入から経費を差し引いた利益を指します。
また、本業に加えてアルバイトなどで給与所得を2ヵ所以上からもらっている場合も、その給与所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
いずれの場合も本業以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は原則不要ですが、住民税の申告が必要となります。住民税の申告は、居住する自治体に対して毎年3月15日の申告期限までに行います。
なお、確定申告を行うと住民税を原則申告する必要はありません。しかしながら、特定の控除や減免制度を受けるために申告を必要とする場合もあるので、注意が必要です。
 2ヵ所以上から給与をもらい年末調整をしていない給与所得がある人
2ヵ所以上から給与をもらい年末調整をしていない給与所得がある人
2ヵ所以上から給与をもらっていて一部のみ年末調整済みである、あるいはいずれも年末調整をしていない場合は、所得税額が正しく計算されていません。そのため、確定申告を行って正しい所得税額を申告する必要があります。
 保険金の受取りなど高額な収入があった人
保険金の受取りなど高額な収入があった人
生命保険の解約返戻金や満期保険金、競馬の払戻金、福引きの懸賞金などの収入は一時所得に該当します。一時所得は次の式のように計算します。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支払った金額-50万円(特別控除)
上記の計算式より算出した一時所得の金額の1/2を、給与などほかの所得と合算して納める所得税額を求めます。
なお、先述のとおり、会社員は給与所得以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。したがって、上記の計算式で求めた一時所得の金額の1/2が20万円を超えていたときには、忘れずに確定申告を行いましょう。
 給与収入が2,000万円を超えている人
給与収入が2,000万円を超えている人
年間で見たときに給与収入が2,000万円を超える場合は会社側で年末調整できないため、確定申告が必要です。
なお、ここでいう「2,000万円」は、所得ではありません。社会保険料などが控除される前の総支給額で判断される点に注意が必要です。
 年末調整での申告内容にミスがあった人
年末調整での申告内容にミスがあった人
会社側で行った年末調整の申告内容にミスがあり、納税額が過少だった場合は修正申告が必要です。
例えば、「大学生の子どもを扶養家族として申請していたものの、子どものアルバイト収入が扶養控除の範囲を超えていた」場合などが該当します。
年末調整の申告内容にミスがあったときは、気づいた時点で早めに修正申告を行いましょう。
会社員で確定申告をしたほうがよい人・6つのケース
ここまで解説してきたように、特定の条件に該当しなければ会社員は確定申告をする必要はありません。ただし、以下6つのケースに該当する方は、確定申告をすると還付を受けられる場合があります。
 マイホームを購入した人
マイホームを購入した人
住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした場合、規定の要件を満たすと住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除は、年末時点における住宅ローン残高の0.7%が所得税(一部、翌年の住民税)から最大で13年間控除される制度です。控除対象となるローン残高の上限や控除期間は購入するマイホームの性能や入居時期によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
現行の省エネ基準を満たしていない新築住宅でも、2023年末までに建築確認申請を受け、2024年・2025年中に入居する場合は、住宅ローン控除の対象です。ただし、控除の対象となるのは年末時点の住宅ローン残高のうち2,000万円までの部分であり、控除期間も10年間に縮小されます。
なお、住宅ローン控除の手続き方法は初年度と2年目以降で異なる点を押さえておきましょう。会社員でも、住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要です。しかし、2年目以降は年末調整で手続きが完了するため、確定申告をする必要はありません。
 6つ以上の自治体にふるさと納税をした人
6つ以上の自治体にふるさと納税をした人
ふるさと納税は、自治体への寄付額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されます。控除額は家族構成や収入で異なるため、事前確認が必要です。
原則として確定申告を行うと寄付金控除が受けられます。ただし寄付先の自治体が5ヵ所以内の場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると確定申告なしで控除を受けられます。
しかし、寄付先の自治体が6ヵ所を超える場合はふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられません。
また、寄付先の自治体が5ヵ所以内でも、「給与所得以外の所得が20万円を超えている」などほかの理由で確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が無効となる点に注意しましょう。その際は、確定申告でふるさと納税の寄付金控除も併せて申告する必要があります。
 退職した人
退職した人
退職金を受取る際、退職所得控除を受けるには勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。
再就職している場合は、新しい会社の年末調整で納税済みの所得税の過不足分が精算されます。しかし、年の途中で退職して再就職していない場合は年末調整を受けられないため、所得税を納め過ぎている状態に陥りかねません。
この場合、納め過ぎた所得税の還付を受けるには確定申告をしなければなりません。
 10万円以上の医療費を支払った人
10万円以上の医療費を支払った人
1月1日~12月31日の1年間に高額な医療費を支払った場合は、医療費控除を受けられる可能性があります。控除額は次の式から算出され、上限は200万円です。
医療費控除額=支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-10万円(※)
- ※その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%
なお、医療費控除は自分だけでなく、生活をともにしている家族などにかかった医療費も合算して申告可能です。
 年末調整後に家族構成が変化した人
年末調整後に家族構成が変化した人
年末調整後に結婚や離婚、出産などで家族構成が変化した場合は、利用できる控除が増える可能性があります。例えば、次のような控除です。
- 配偶者(特別)控除:納税者本人と配偶者の所得が一定以下の場合に、最大38万円(配偶者の年齢が70歳以上のときは最大48万円)の控除を受けられる。配偶者の所得が48万円を超えている場合でも、納税者本人と配偶者の所得に応じて最大38万円の配偶者特別控除を受けられることがある。
- 扶養控除:扶養対象となる親族がいる場合、扶養控除を受けられる。控除金額は扶養親族の年齢や同居の有無などで異なる。
- ひとり親控除:納税者がひとり親である場合、要件を満たせば35万円の控除を受けられる。
- 寡婦控除:納税者自身が寡婦である場合、要件を満たせば27万円の控除を受けられる。
 株やFXで損失がある人
株やFXで損失がある人
株やFXで損失がある場合は、ほかの証券会社での取引で得た利益との損益通算が可能です。損益通算とは、所得金額を計算するときに利益と損失を相殺することで、確定申告をしなければ適用されません。
一方で、株やFXによる損失は給与所得とは損益通算できない点に注意が必要です。
損益通算しても控除しきれない場合は、翌年以降3年間の利益から繰越控除できます。
会社員で確定申告が必要ない人
上述のとおり、「所得がある人」は基本的に確定申告が必要です。しかし、会社員は勤務先の年末調整で所得税の納税が完了するため、「副業の所得が20万円以上ある」「住宅ローンを組んでマイホームを購入した」などの場合を除き、確定申告をする必要はありません。
もし自分に確定申告が必要かどうかがわからない場合は、国税庁の「税務相談チャットボット」が役立ちます。画面上に表示されるいくつかの質問に答えると確定申告の必要性を判定してもらえるので、ぜひ活用してみてください。
確定申告を忘れた場合はどうなる?
確定申告を忘れると、本来受けられるはずの還付を受けられず、損をしてしまう可能性があります。
それだけではなく、確定申告の義務があるのに行わなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性も否定できません。
確定申告の期限後に申告するケースでは、時期や申告する意思の有無によってペナルティの重さが変わります。税務署の調査で申告忘れが発覚した場合、ペナルティが重くなる可能性があるため、気づいた時点で速やかに期限後申告を行いましょう。
なお、還付申告の場合は、該当年の翌年1月1日から5年間であれば、いつでも行うことが可能です。
会社員の確定申告にはクレジットカードの利用が便利

確定申告の手続きに不慣れだと、経費として計上できる支出の確認に時間を要してしまうことがあります。そのようなときには、クレジットカードの利用が便利です。
副業などにかかる費用をクレジットカードで支払うと、経費の一元化・見える化が可能となり、効率的に確定申告を行えます。
副業用とプライベート用など支出別にクレジットカードを使い分けると、さらに整理しやすくなる点もメリットです。
また、確定申告を行って所得税の追加納税が必要となった場合には、クレジットカードで納められます。自宅にいながら納税できるだけでなく、クレジットカードによってはポイントやマイルがたまるところもメリットです。
ただし、クレジットカードで納税するときには以下の点に注意する必要があります。
- 領収書が発行されない
- 納税額に応じて決済手数料が発生する
- 納税証明書の発行に時間を要する
上記の注意点を理解したうえでクレジットカードを上手に活用すれば、スムーズに確定申告を行えます。
まとめ
「所得のある人」は原則、確定申告が必要ですが、勤務先で年末調整を受けている会社員は不要です。
しかし、副業での所得が20万円を超える場合など、確定申告が必要となるケースもあります。
確定申告を行う必要性があり、効率的に済ませたい場合には、クレジットカードによる経費の一元化・見える化がおすすめです。経費として計上できる支出を一元的に管理できるだけでなく、自宅で納税ができる、ポイントがたまるなどのメリットもあります。
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉は、通常のポイントに加え、1年間のご利用金額に応じて一般カードは最大3,000ポイント、ゴールドカードは最大9,000ポイントの年間ボーナスポイントがもらえる点が特長です。
クレジットカード選びで迷っている人は、ぜひ検討してみてください。
- ※りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉一般カードは、JCB 1,100円(税込)、VISA 1,375円(税込)の年会費がかかります。初年度無料です。
また、ゴールドカードは、JCB 5,500円(税込)、VISA 11,000円(税込)の年会費がかかります。
りそなクレジットカードの
お申込み