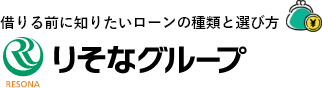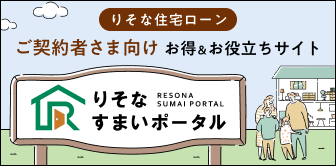耐震リフォームにかかる費用はどれくらい?補助金制度や耐震診断の手順も解説!
公開日:2022/03/07
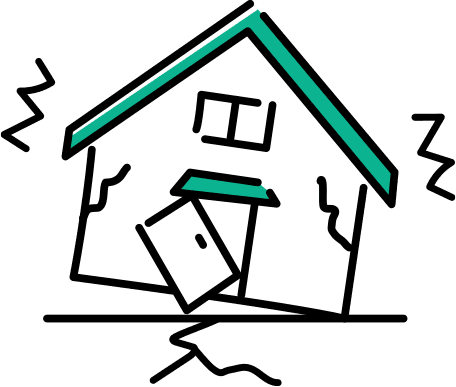
命や財産を守るためにも、住宅の耐震化は非常に大切です。耐震リフォームには当然費用がかかりますが、補助金制度が活用できることをご存じでしょうか。
補助金制度を利用するためには、耐震診断を受けて、耐震リフォームの必要性を認められるなどの条件をクリアすることが必要です。
この記事では、耐震リフォームが必要な家屋の条件や、耐震診断の流れについて紹介します。併せて、耐震リフォームをする場合の補助金制度や、国の支援についても説明するので参考にしてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。
- ※りそなグループが監修しています
耐震リフォームを考える目安とは?

耐震リフォームが必要かどうかは、後述する耐震診断で確認できますが、まずは自分で耐震リフォームを考える目安を把握しておくことが大切です。
目安がわかれば、スムーズな診断依頼やリフォームの申込み、安心した居住が期待できます。ここでは、耐震リフォームを考える目安について説明します。
旧耐震基準で建築された住宅
耐震リフォームを考える目安の一つが「耐震基準」です。耐震基準とは、建築物がどれだけ地震に耐えることのできる構造かを判断する基準を指します。
耐震基準は「旧基準」と「新基準」に分かれており、建築基準法に基づく現行の耐震基準は「新基準」です。新基準は、1981年(昭和56年)6月1日より導入されています。
具体的には、「建築確認申請」が役所で受理されて「確認通知書(副)」が発行された日付が、以下のどちらに該当するかによって決まります。
- 【旧耐震基準】1981年(昭和56年)5月31日以前
- 【新耐震基準】1981年(昭和56年)6月1日以降
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建築物が倒壊せず、破損した場合でも補修することで生活が可能な構造基準とされています。震度6以上の規定はありません。一方で新基準では、震度6強~震度7程度の揺れでも倒壊しないような、新しい構造基準が設定されています。
「確認通知書(副)」が手元にある場合は、発行日を確認してみましょう。自宅が旧基準に該当していれば、耐震リフォームを検討する目安です。
2000年5月以前に建築された木造住宅
耐震基準には、旧耐震基準・新耐震基準のほかに「2000年基準」という基準もあります。2000年(平成12年)6月に建築基準法が改正され、木造住宅に関する耐震基準の変更が行われたのです。
震度6強~7程度の揺れでも倒壊しない、という基準は変わりません。しかし、おもに地盤に応じた基礎設計や、柱頭・柱脚・筋交いの接合方法、偏りのない耐震壁の設置などの点で規定がより強化されています。
新耐震基準に適合する木造住宅でも、2000年6月からの改正基準に適合していない場合には、地震に対する備えが弱い可能性があるため注意が必要です。
家の耐震性に不安を感じたとき
どちらの耐震基準に該当するかわからなくても、家の耐震性に不安要素がある場合は、安全のために耐震リフォームを考えたいものです。
例えば、築年数が古く老朽化していたり、地震以外でも揺れを感じることがあったりするような場合は、耐震リフォームのタイミングといえます。
壁が少ない、地震直後でダメージを受けたなどの理由も不安要素の一つです。さらに、「自宅を売却したい」「中古住宅を購入する」といった際も、耐震リフォームのタイミングといえるでしょう。
なお、耐震性の強化は、購入した中古住宅で安心して暮らすためだけではなく、売却時の価格の下落防止にもつながります。
耐震リフォームを行うための耐震診断や手順は?
家の耐震性に問題を感じた場合は、できるだけ早く耐震診断を受けるのがおすすめです。耐震診断の概要や手順について説明します。
耐震診断とは?
耐震診断とは、既存建築物の耐震性能を評価し、耐震リフォームが必要かどうかを判断するものです。耐震リフォームを行う前には、耐震診断を受ける必要があります。
「耐震改修促進法」に基づく国土交通省告示に、耐震診断の指針が定められていることをご存じでしょうか。
耐震診断ができるのは、国土交通大臣登録耐震診断資格者講習の受講を修了した、耐震診断資格者のみです。たとえ建築士の資格を持っていても、講習の受講を修了していない場合は、耐震診断は行えません。
耐震診断資格を持つ建築のプロに任せれば、新耐震改修促進法に即した耐震診断が行えます。
なお、耐震性能とは地震のエネルギーを吸収できる能力のことで、次の4点を総合的に考慮し、評価されます。
- 建物の強さ(地震力に耐える頑丈さ)
- 建物の粘り(地震力を逃すしなやかさ)
- 建物状況(建物の平面形・断面系・バランス)
- 経年状況(老朽化の度合い)
引用:一般社団法人 建築性能基準推進協会「耐震診断・耐震改修のススメ」
この耐震診断の結果によって、リフォームの要・不要が判定されます。
耐震診断の大まかな流れ
耐震診断の大まかな流れも知っておきましょう。耐震診断は、以下の3つの順で行われます。
- 予備調査
- 現地調査
- 耐震診断結果の評価
予備調査は、現地調査(本調査)を行う際に、診断方法を決定するための調査です。必要な情報を収集したり、設計図書や計算書、増改築などがわかる資料を準備したりします。予備調査にかかる期間は、1~2週間が目安です。
現地調査では、現地で構造躯体や非構造部材、設備機器などの状況を確認し、強度や劣化の状況などの詳細を調査します。
現地調査にかかる期間は3~6週間が目安です。予備調査と現地調査の終了後は、耐震診断結果が出るのを待ちます。
評価結果が出るまでにかかる期間は、建築物の規模や形状によって異なりますが、1~3ヵ月が目安です。
耐震リフォームにかかる費用の目安は?

耐震リフォームが必要でも、費用面で不安があるとリフォームに踏み切れないかもしれません。あらかじめ、耐震リフォームにかかる費用の目安も知っておきましょう。
耐震補強工事の平均施工金額は約163万円
耐震リフォーム費用の目安は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が公表している「木耐協 耐震診断結果 調査データ」(2018年8月21日発表)を参考に紹介します。
当データによると、耐震補強工事を実施した人に対して行った耐震補強工事の平均施工金額は約163万円、耐震補強工事の約52%が工事費用150万円未満です。
なお、調査対象は1950年(昭和25年)~2000年(平成12年)5月までに着工された2階建て以下の木造在来工法の住宅で、この金額は旧・新耐震基準を合わせた全体の平均額です。
旧・新基準別に見ると、平均施工金額は旧耐震基準住宅のほうが約37万円高くなっています。
【耐震補強工事にかかった金額と施工割合】
横スクロールできます。
| 耐震補強工事金額 | 全体 | 旧耐震基準住宅 | 新耐震基準住宅 |
|---|---|---|---|
| 50万円未満 | 11% | 9% | 12% |
| 50~100万円未満 | 17% | 14% | 20% |
| 100~150万円未満 | 24% | 21% | 27% |
| 150~200万円未満 | 15% | 15% | 15% |
| 200~250万円未満 | 13% | 14% | 12% |
| 250~300万円未満 | 8% | 11% | 7% |
| 300万円以上 | 11% | 16% | 7% |
| 平均施工金額 | 163万9,081円 | 182万9,944円 | 145万9,843円 |
| 施工金額中央値 | 140万円 | 155万円 | 125万円 |
出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合「木耐協 耐震診断結果 調査データ」(2018年8月21日発表)
耐震化住宅でも約2割が耐震補強工事を実施
同データによると、耐震診断実施者のうち約2割の人が「耐震に対する安全性がある」と判断された住宅に対して、耐震補強工事を行っています。
2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震など、大型地震の発生で耐震や防災意識が向上していることも、要因の一つといえるかもしれません。
耐震リフォームに補助金制度はある?
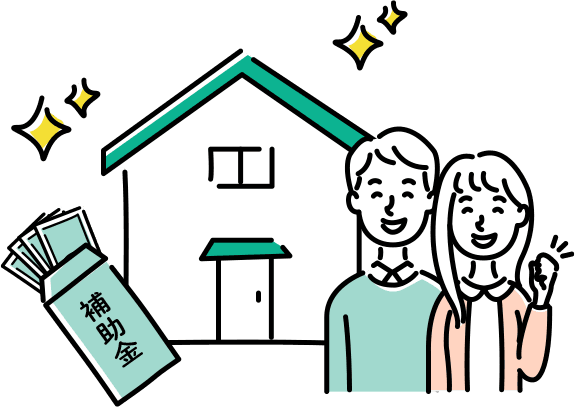
耐震補強工事をした過半数の住宅で、工事費用額が150万円未満に収まっているとはいえ、工事金額にばらつきもあります。
家の耐震状況によっては、より多くの費用が必要になる可能性もあるため、費用面で不安を感じる方もいるかもしれません。ここでは、耐震リフォームをする場合の補助金制度や支援制度について紹介します。
耐震リフォームの補助金制度は自治体が実施
多くの自治体では、建物の倒壊など地震による被害を最小限に抑えることを目的に、耐震診断や耐震リフォーム費用に対する補助金制度を実施しています。
基本的に、どの自治体も工事契約・着工前に耐震診断を受け、自治体からの補助金交付決定を受けることが補助金の支給条件の一つです。
しかし、補助金の対象となる住宅や工事などに関する細かな条件は、自治体によって異なります。
例えば、「補助金の対象を木造住宅のみに限定している」「木造以外の建築物でも補助対象としている」などさまざまです。また、工事費用に対する補助率や補助金の限度額なども、自治体ごとに異なります。
正確な情報は、居住する自治体のホームページなどで事前にチェックしておきましょう。自治体によっては、補助金制度を実施していないところもあります。
まずは、自分の居住する自治体が、耐震リフォームの補助金制度を実施しているか確認することが必要です。
補助金制度の有無は、以下の「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」および「日本建築防災協会」のサイトから確認できます。
なお、耐震リフォームに関する国の補助金制度はありません。
国は税制優遇で耐震リフォームを支援
費用に関する補助金制度はありません。しかし、国は所得税控除と固定資産税の減額という形で耐震リフォーム支援を行っています。
所得税の特例措置
投資型減税といって、対象となるリフォーム工事をした場合、所得税から一定額を控除できる減税特別措置が設けられています。
耐震リフォームに関しては、25万円を上限に「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%」を所得税から控除することが可能です。
2022年度の税制改正で、「対象工事限度額を超過する部分」「その他のリフォーム工事」も、標準的な費用相当額の同額までの5%を所得税額から控除できるようになりました。ただし、減税特例措置を受けるためには、以下のような条件を満たすことが必要です。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された自己の居住用家屋
- 耐震リフォーム後の住宅が新耐震基準に適合している など
固定資産税の特例措置
耐震リフォームをすることで、翌年度の固定資産税が2分の1に減税される特例措置もあります。減税が適用されるおもな条件は、以下のとおりです。
- 1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する住宅
- 工事費用が50万円を超えている
- 耐震リフォーム後の住宅が新耐震基準に適合している など
また、固定資産税の減税を受けるためには、耐震リフォーム工事が完了したあと、3ヵ月以内に都道府県・市区町村へ届け出を行うことが必要です。詳しくは、居住する自治体のホームページなどで事前に確認しましょう。
まとめ
家の耐震性に不安がある場合は、耐震リフォームを実施すると安心です。まずは、耐震診断を受けて、リフォームの必要有無を判定してもらいましょう。
これらの手順で耐震リフォームを行えば、自治体の補助金を受けられる可能性があります。耐震リフォーム費用の平均額は約163万円と高めなので、うまく活用しましょう。
補助金などで賄えない場合は、リフォームローンの利用も一つの方法です。「旧耐震基準の住宅ほどリフォーム費用が高い」というデータもあるため、できるだけ早めにリフォームすることが安全面でも費用面でも安心といえます。
りそなのリフォームローンは、次のような特徴があります。
- 自宅や実家などの耐震や免震工事に適用可能
- 借入可能額上限は1,000万円
- 一括のほかにも3ヵ月以内最大3回までの分割借入れもできる
- 自宅のほか、実家やセカンドハウスの修繕や空き家解体資金など幅広く利用可能。ただし、住宅名義本人が施主となるリフォームに限ります。
まずは、りそなのリフォームローンを検討されてみてはいかがでしょうか。
また、「りそなグループアプリ」の利用で、インターネットで返済状況や残高の確認ができ、管理がしやすい特徴があります。これからリフォームローンを検討される方は、ぜひりそなのリフォームローンをご利用ください。
原則来店不要!
りそなリフォームローンを
Web完結でお申込み!
来店不要で24時間365日
お申込みが可能!
あなたにあったリフォームは?
本記事は2022年3月7日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。