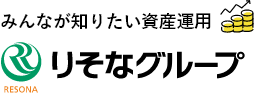定期預金が満期になったらどうする?満期後の選択肢と注意点
公開日:2025/09/09

しばらく使う予定のない定期預金が満期を迎えた場合、「このお金、どうしよう」と悩む方も多いようです。
満期後の資金は「生活防衛資金」「ライフイベントの資金」「余裕資金」の順に分けて考えると、自分に合った選択がしやすくなります。
本記事では、定期預金の基本や満期後の考え方、注意点を中心にわかりやすく解説します。ぜひ満期後の選択肢として参考にしてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
定期預金とは?特徴と
メリット・デメリット
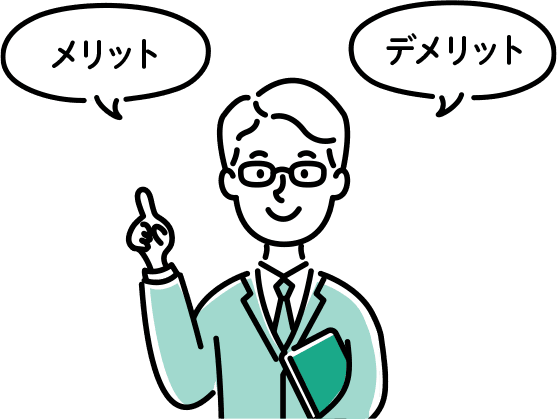
定期預金とは、あらかじめ預入れ期間と金利が設定された預金です。
預入れ期間は金融機関や商品によりますが、基本的に満期日までは引出すことができません。その分、普通預金と比較すると、金利が高めに設定されています。そのため、着実にお金を貯めたい人に向いています。
やむを得ず、満期前に引出す場合は「中途解約」となり、予定された金利よりも低い金利が適用されてしまう点に注意が必要です。
定期預金は、投資信託などの投資運用商品とは異なり、価格変動リスクはありません。元本保証がメリットと言えますが、物価が上がるインフレ局面では、預入れ時に設定された金利で満期をむかえるため、実質的な価値が目減りしてしまう可能性もあります。
定期預金の特徴を理解したうえで、自分の目的やライフプランに合った使い方を考えることが大切です。
定期預金は満期になったら
どうなる?
定期預金は満期を迎えると「自動解約」または「自動継続」どちらかの方法で処理されます。契約時にいずれかを指定するため、満期時の手続きは原則、必要ありません。
「自動解約」では、元本と利息が普通預金に入金されます。一方、「自動継続」は、同じ期間の定期預金へ手続きをすることなく、再度預入れるものです。「自動継続」には、「元利自動継続」と「元金自動継続」の2種類があり、以下の違いがあります。
- 元利自動継続
はじめに預入れた元本と満期時の利息を合算した金額を定期預金に預入れます。 - 元金自動継続
はじめに預入れた元本のみ再び定期預金に預入れ、満期時の利息は普通預金に入金されます。
最近は金利が上がってきているため、自動継続を活用して効率よく資産を増やすのも一つの方法です。
りそなではスマートフォンアプリ1つで定期預金の口座開設から管理まで完結でき、契約時に指定がなければ自動継続として更新されます。
定期預金が満期になったら
考えたいこと
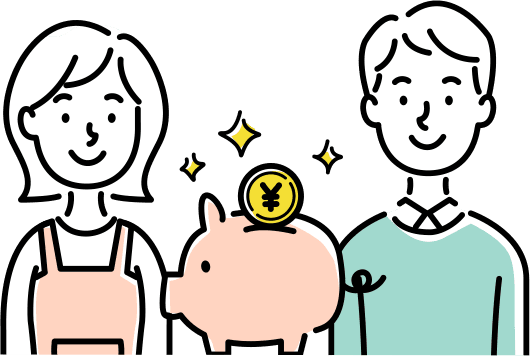
満期を迎える定期預金の使い道に悩む場合は、「生活防衛資金」「ライフイベントの資金」「余裕資金」の3つの順に分けて考えると整理しやすくなります。
定期預金を始めた当時と比べて、ライフスタイルや将来の計画が変わっていることも少なくありません。満期を迎えた今こそ、これからのライフプランを見直しながら、お金の使い道を考えてみましょう。
不測の事態に備える
「生活防衛資金」に追加する
まず優先したいのが、いざというときに備える「生活防衛資金」です。病気やケガ、離職、冠婚葬祭など、予期せぬ出費に対応するための資金で、安心して暮らすための土台ともいえます。
必要な金額の目安は家族構成や生活環境によって異なります。
- 独身や子どもがいない世帯:生活費の3〜6ヵ月分
- 子どもがいる世帯:生活費の6〜12ヵ月分
自営業の方などは、突発的な事業費用にも対応するため、上記より多めに確保しておくと安心です。
「生活防衛資金」は、普通預金口座など流動性の高い口座で管理し、必要時にすぐ引出せるようにしておきましょう。
住宅購入など
「ライフイベントの資金」に
追加する
生活防衛資金をしっかり確保したうえでまだ余裕がある場合には、近い将来に予定しているライフイベントに使うのも一つです。
例えば、住宅購入の頭金や初期費用、教育、車の買い替え、旅行など、目的や時期が想定できるときは、それまでの期間に応じた「定期預金」に預けることが選択肢となります。
また、選択肢としては、「個人向け国債」もあげられます。
個人向け国債は、国が毎月発行している安全性の高い債券です。半年ごとに利子を受取り、満期時には元本が戻ってくる金融商品です。最低でも年0.05%の金利が保証されており、1万円から購入できる点も魅力です。
目的別に資金を準備しておくことで、必要なタイミングで、確実に安心して使うことができるでしょう。
しばらく使う予定のない
「余裕資金」に追加する
生活防衛資金とライフイベントの資金を確保しても、なお余裕がある場合は、老後資金など「余裕資金」として長期的な資産形成を検討してみましょう。
金融商品によって収益性や安全性、流動性などは異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。例えば、以下のような制度・金融商品が活用できます。
- NISA
- 外貨預金
- iDeCo
- 個人年金保険
それぞれ具体的に解説します。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)は、投資の運用益が非課税となる税制優遇制度です。
2024年から新制度に移行し、非課税保有期間や投資上限額などが拡充されて、より柔軟に活用できるようになりました。「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
横スクロールできます。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 (総額) |
合計1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円) |
|
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した 一定の投資信託 (金融庁の基準を満たした商品のみ) |
上場株式 投資信託など |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
投資信託とは、投資家から集めたお金をプロが複数の資産に分散して運用する金融商品です。価格変動リスクおよび元割れのリスクはありますが、長期で積み立てることで、複利の力を活かした資産形成が期待できます。
NISAを利用して購入した投資信託の分配金や運用益は非課税となるため、上手に活用しながら運用していきましょう。必要なときに売却して引出せることもNISAのメリットです。
しかし、資産形成の経験がなく、不安のある方もいるでしょう。
りそなでは、対面でもオンラインでも相談できる環境が整っており、初心者でも安心して始められます。長期積立に適した低コストの投資信託も豊富です。
外貨預金
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、基本的に毎月一定額を積み立て、その掛金を自分で運用しながら将来の年金を準備する「じぶん年金」づくりの制度です。積み立てた資金は年金形式あるいは一時金で受取ります。
掛金は全額所得控除、運用益も非課税、そして受取時も「公的年金等控除」または「退職所得控除」の対象となっており、税負担を抑えながら運用できるのはiDeCoの強みといえます。
一方、iDeCoは原則として60歳まで引出せません。老後の年金を長期でじっくり積み立てたい方に向いている制度です。
個人年金保険
より堅実に老後の準備をしたい場合は、個人年金保険も検討してみてください。
一定期間保険料を支払い、将来、年金形式または一時金として受取る仕組みで、契約時に受取額が確定するため、老後資金を計画的に準備しやすいのが特徴です。契約内容によっては、生命保険料控除により所得税が軽減できる税制優遇も受けられます。
定期預金が満期に
なったときの注意点
定期預金が満期を迎えたあと、継続をせずにそのまま放置することは避けたいものです。
10年以上入出金(異動)なく放置した場合には、「休眠預金」となり民間の公益活動に活用される可能性があります。
休眠預金とは、2009年以降、10年間入出金(異動)のない定期預金や普通預金、当座預金などです。
(※引き続き元の金融機関で引出しは可能)
残高が1万円以上あれば郵送や電子メールで事前通知があります。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。
しかし、住所や電子メールアドレスに変更がある場合は、通知を受取れず休眠預金となる可能性があります。変更時は、忘れずに金融機関へ届け出るようにしましょう。
また、目的のないまま大きなお金を手にすると、気がゆるんで散財する、リスクの高い投資に手を出してしまうケースもあります。
満期を迎えたこの機会に、自分の将来(ライフプラン)について考えたうえで、お金の使い道を決めることが大切です。
まとめ
定期預金の満期は、これからのライフプランを見直す良いタイミングです。
まずは生活防衛資金やライフイベントの備えを優先し、余裕があれば将来に向けた資産形成も検討しましょう。
なかには、金融商品の選択肢が豊富で「どれを選べばいいのかわからない」と迷う方もいるかもしれません。
そんなときは、りそなの「投資をはじめてみよう!スタイル&商品診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、自分に合った投資スタイルや商品がわかります。資産形成の第一歩に、ぜひ活用してみてください。
本記事は2025年9月9日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。