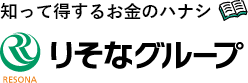【最新データ】共働き家庭の割合は?メリット・デメリットと役割分担のヒント
公開日:2025/10/28
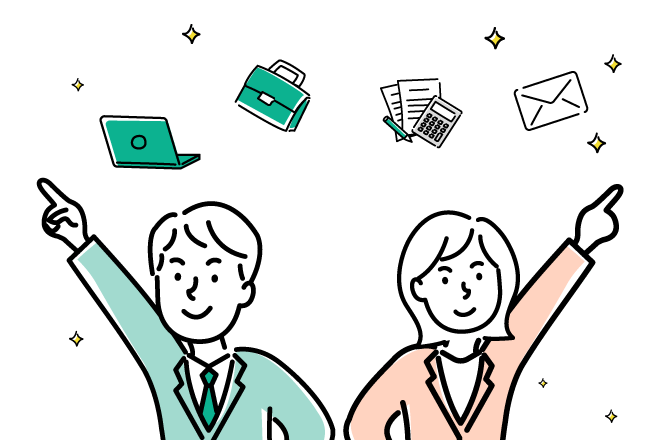
いまや夫婦のライフスタイルとして「共働き」は珍しいものではなくなってきています。
ただ、収入の安定やキャリア継続のために共働きを選ぶ夫婦が増える一方、家事や育児、家計管理の負担に悩む声も少なくありません。
この記事では、共働き家庭の割合や経済状況のほか、共働きを選ぶ理由やそのメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。
- ※りそなグループが監修しています
共働き家庭の割合と現状
まずは、現在の日本における共働き家庭の割合と、過去からの推移について見ていきましょう。
日本における共働き家庭の割合
総務省統計局の「労働力調査(詳細集計)2024年版」の結果をもとにした独立行政法人労働政策研究・研修機構の発表によると、2024年の共働き世帯数は1,300万世帯に達し、専業主婦世帯数(508万世帯)の約2.6倍にものぼっています。
夫婦のいる世帯全体に占める共働き世帯の割合は約71.9%であり、現在の日本社会では多数派を形成しているといえるでしょう。
過去から現在までの推移
1980年代には、専業主婦世帯が全体の6割以上を占めていましたが、1992年には共働き世帯数(914万世帯)が専業主婦世帯数(903万世帯)を初めて上回り、1997年以降は一貫して専業主婦世帯数を上回る状況が続いています。
2000年代を見てみると、共働き世帯数は2000年の942万世帯から、2020年には1,247万世帯へと大きく増加しています。その後も共働き世帯数は増え続けており、2022年は1,262万世帯(専業主婦世帯数は539万世帯)、2023年には1,278万世帯(専業主婦世帯数は517万世帯)となっています。
このように、共働き家庭の数と割合は年々増加しています。
共働き家庭の経済状況
共働き家庭の経済状況は、働き方や家族構成によって異なります。
ここでは、世帯年収や生活費についてのデータを見ていきます。
世帯収入の現状
まずは、共働き世帯の平均年収を見ていきましょう。
総務省の「2024年 家計調査」(実収入)によると、共働き世帯の平均年収は約856万円であるのに対し、夫のみが働く世帯の平均年収は約688万円です。
その差は約168万円で、月収ベースで考えると毎月約14万円の収入差があります。
| 世帯区分 | 平均年収 |
|---|---|
| 共働き世帯 | 約856万円 |
| 夫のみが働いている世帯 | 約688万円 |
次に、子どもの人数別に平均年収を見てみましょう。
共働き世帯では、夫婦のみの世帯が約775万円、子ども1人の世帯が約854万円、子ども2人になると約916万円と少し増加する傾向があります。
夫のみが働く世帯では、夫婦のみが約617万円、子ども1人が約707万円、子ども2人が約778万円と、どちらの世帯も子どもの人数が増えるにつれて世帯年収も増加する傾向があります。
ただし、年収の違いには年功序列の影響も考えられるため、子どもの人数だけで単純に比較するのは注意が必要です。
| 子どもの 人数 |
共働き世帯の平均年収 | 夫のみ働く世帯の平均年収 |
|---|---|---|
| 夫婦のみ | 約775万円 | 約617万円 |
| 子ども1人 | 約854万円 | 約707万円 |
| 子ども2人 | 約916万円 | 約778万円 |
さらに、妻の収入額によっても世帯年収は異なります。
妻の収入が月8万円以上の世帯では平均年収が約972万円に達する一方、月8万円未満(主にパート勤務)の世帯では約756万円です。
| 妻の年収 | 平均年収 |
|---|---|
| 8万円以上 | 約972万円 |
| 8万円未満(主にパート勤務) | 約756万円 |
参照:「2024年 家計調査 (家計収支編) 二人以上の世帯」総務省
東京商工会議所が2024年に実施した「東京在勤若者世代の結婚・出産意識調査」によると、結婚して子どもが産まれた後も結婚相手やパートナーに働いてほしいと考える男性は、都内では51.9%と半数以上にもなっています。今回示した家計調査では、共働き世帯と夫のみ働く世帯の平均年収差は約168万円ですので、子どもの教育費や住宅ローン、老後資金などのことを考慮すると経済面では共働きのほうが良いかもしれません。
生活費の内訳
1ヵ月当たりの平均消費支出は以下のとおりです。
| 世帯区分 | 消費支出 |
|---|---|
| 共働き世帯 | 34万5,762円 |
| 夫のみ働く世帯 | 31万1,043円 |
| 妻の収入が8万円以上の共働き世帯 | 36万3,463円 |
| 妻の収入が8万円未満(主にパート勤務)の共働き世帯 | 33万8,677円 |
参照:「2024年 家計調査 (家計収支編) 二人以上の世帯」総務省
消費支出は、主に食費、住居費、水道光熱費など10の費目に分類されます。
子どもがいる家庭では、これらに加えて学費や習い事などの教育費も必要になるため、将来を見据えた家計管理が大切です。
共働きを選ぶ理由
多くの家庭が共働きを選ぶ背景には、主に以下の3つの理由があります。
 経済的安定の希求
経済的安定の希求
共働きを選ぶ最大の理由は、経済的な安定を求めるためです。
世帯収入が増えることで、住宅ローン返済や老後資金、子どもの教育費など将来に向けた資金に余裕をもつことができます。
一人の収入では限界がありますが、共働きであれば世帯収入を増やすことが可能です。
 キャリアの再開と発展
キャリアの再開と発展
女性のキャリア継続への意欲も、共働きを選ぶ大きな理由です。
近年は育児休業制度が充実し、出産後も継続的なキャリア形成を可能とする環境が整ってきています。
働き方の多様化も進んでおり、フルタイムやパート、在宅勤務など、自分のライフスタイルに合った働き方を選ぶことで、経済的な自立を維持しながら自己実現を目指せます。
 性別役割分担の変化
性別役割分担の変化
内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和6年9月調査)によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について「反対」「どちらかといえば反対」と回答した人の割合は、平成4年では34.0%であるのに対し、令和6年では64.8%になっています。
「男性は仕事、女性は家庭」という従来の価値観が変化し、夫婦が対等なパートナーとして協力する家庭が増えています。「こうあるべき」という固定観念から脱却し、お互いを尊重する考え方が広がっていることも、共働きが選ばれる理由の一つです。
共働きのメリット

共働きには経済面だけでなく、以下のようにさまざまなメリットがあります。
 リスクヘッジ効果がある
リスクヘッジ効果がある
夫婦のどちらかが病気や失業などで働けなくなった場合も、もう一方の収入があれば、世帯収入がゼロになるリスクを避けられます。
収入が完全に途絶えないという安心感は、リスク分散にともなう共働きならではの大きな効果です。
 お互いの収入を生かして
お互いの収入を生かして
ペアローンを組むことが可能
マイホーム購入の際、夫婦それぞれがローンを組むペアローンを利用可能な場合があります。
単独ローンよりも借りられる額が増えるため、物件の選択肢は広がります。
また、物件の環境性能や所得など適用要件をクリアすれば、それぞれが所得税や住民税などの税負担を軽減できる住宅ローン控除を利用することができます。
(住宅ローン控除の内容詳細につきましては、専門家や税務署等にご確認ください)
さらに、夫婦ともに団体信用生命保険に加入できれば、万が一の備えも手厚いでしょう。ぺアローン団体信用生命保険(ペアローン団信)は、ぺアローンで借入れ後、夫婦のいずれかに万一のことがあった場合、どちらも住宅ローン残高がゼロになる団体信用生命保険です。
りそなではお客さまのライフプランに合わせたペアローンと、もしもに備えるペアローン団信をご用意しています。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ
 将来に向けた効率的な
将来に向けた効率的な
資産形成ができる
世帯収入が増え、余裕が生まれることで、計画的な貯蓄が可能になります。
さらに、資金の一部を投資に回すことで、将来に向けた資産形成を効率的に進められるでしょう。
りそなの投資信託は少額からはじめられ、NISAを活用すれば運用益が非課税になります。お客さまの目的に合わせた豊富なラインアップをご用意しています。
共働きのデメリット
共働きには多くのメリットがある一方で、特有の課題もあります。
 家計管理が難しい
家計管理が難しい
夫婦がそれぞれお金を管理していると、家庭全体の資産状況が把握しづらくなります。
また、収入があるという安心感から財布の紐が緩み、浪費につながることもあるでしょう。
共働き世帯であっても、家計の管理について2人で話し合い、どのような方法が自分たちにとって最適かを決めておきましょう。いずれにしても、お互いの状況を共有することが大切です。
 お互いのコミュニケーション機会が減ってしまう
お互いのコミュニケーション機会が減ってしまう
忙しい日常のなかで夫婦の会話が減ると、すれ違いが生じやすくなります。
コミュニケーションの不足は、家事や育児の分担が偏る原因にもなりかねません。
日頃の不満が蓄積され、取り返しのつかないことにならないように、スケジュールの共有だけでなく、日常の楽しい出来事や悩みなどを話す時間を意識的に設けて、積極的にコミュニケーションを取りましょう。
 子どもがいる場合の緊急時の対応が難しい
子どもがいる場合の緊急時の対応が難しい
子どもの急な体調不良など、緊急の送り迎えや看病などへの対応は大きな課題です。
いざという時に混乱しないよう、事前に夫婦で役割分担のルールを決めておきましょう。
「この日は休めない」といった予定も日頃から共有しておくことが大切です。
共働きの注意点と工夫
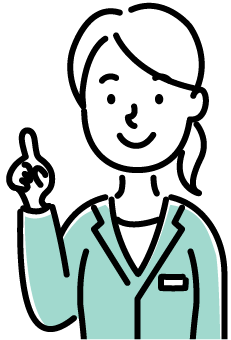
最後に、共働き生活を円滑に進めるための具体的な工夫をご紹介します。
家事や育児の分担
共働き家庭において、家事や育児の分担は避けて通れないテーマです。家事分担表の作成や外部サービスの活用によって、負担のバランス調整や軽減がしやすくなります。
役割分担を明確にしよう
家事や育児などの分担を明確にすることで、お互いが無理することなく負担を軽減し、時間の有効活用につながります。
子どもにも年齢に応じた簡単な手伝いを任せられれば、家族全体で協力する意識が高まるでしょう。
家事分担表を作成してみよう
家事をリストアップし、誰が担当するかを割り当てた家事分担表の作成することもおすすめです。
冷蔵庫などの見やすい場所に貼り、お互いの役割を確認できるようにしましょう。定期的に見直し、状況に応じて適宜調整することも成功の秘訣です。
外部サービスを上手く活用しよう
夫婦だけですべてを抱え込まず、外部の力を借りることも大切です。
共働き家庭が活用できる主な外部サービスには、以下のものがあります。
- 家事代行サービス
- ベビーシッター
- ネットスーパーや宅配サービス
これらは、仕事で疲れている夫婦にとっては強い味方です。上手く活用して、家事や育児から来るストレスを少しでも軽減しましょう。
時短家電を活用する
ロボット型掃除機や食器洗い乾燥機、乾燥機付き全自動洗濯機などの時短家電は、家事の負担を軽減してくれます。家事に費やす時間を家族のために有効に使いたいものです。
購入のための初期費用はかかりますが、日々の時間と労力を節約できるため、導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
家計管理をしっかりと行う
収入が多いからこそ、支出の管理は重要です。外食や贅沢が増えすぎないよう、家計管理を徹底しましょう。
りそなグループアプリなら、銀行口座やクレジットカードの情報を一元管理できます。収支が自動でグラフ化されるため、家計の状況が一目でわかります。
夫婦で共有すれば、お金の流れを簡単に可視化でき、計画的な家計管理をサポートしてくれるでしょう。
まとめ
この記事では、共働き家庭の割合や経済状況、共働きを選ぶ理由やそのメリット・デメリット等について詳しく解説しました。
日本において、共働き世帯は着実に増えているのが現状です。
共働きには経済的な安定やキャリア形成、リスクヘッジなど多くのメリットがある一方で、家事や育児の分担やコミュニケーション不足といった課題もあり注意が必要です。
大切なのは、夫婦でしっかりと話し合い、お互いの価値観を尊重しながら協力体制を築くことです。
家事分担表の作成や時短家電の活用、外部サービス、家計管理アプリなどを積極的に活用し、無理なく続けられるスタイルを見つけていきましょう。
- ダウンロードはこちら(無料)
本記事は2025年10月28日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。