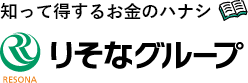二人暮らしの生活費や家賃、食費の内訳と節約術等
公開日:2025/10/28
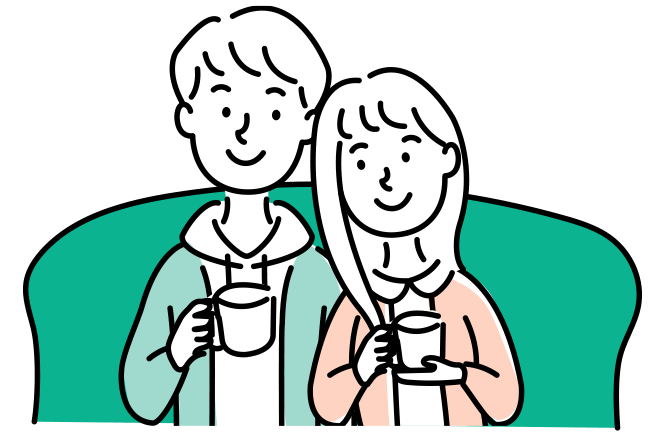
二人暮らしをスタートさせる際に、多くの人が気になるのは生活費でしょう。家賃や食費、光熱費、その他の生活費が具体的にどれくらいかかるのかを知ることで、経済的な不安を軽減してよりスムーズな生活を送り、計画的な貯蓄を行うことが可能です。この記事では、二人暮らしにかかる主な生活費の内訳や、節約のための具体的な方法等について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
生活費項目の内訳を詳しく知ろう
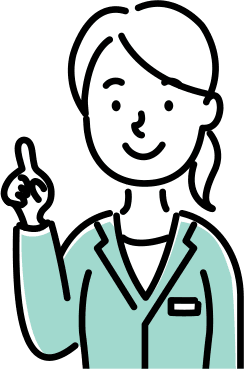
二人暮らしの生活費を把握するためには、固定費と変動費の内容を理解することが重要です。
固定費とは
固定費とは、毎月ほぼ一定額の支払いが発生する費用のことで、代表的な項目としては家賃や水道光熱費、保険料、通信費、サブスクリプション料金などが挙げられます。家賃は地域や住む場所によって大きく異なり、住宅選びは生活の基盤となるため、慎重に検討しましょう。また、水道光熱費も季節や生活スタイルによって異なりますが、おおむね一定の範囲内で推移することが多いです。保険料も固定費の一つであり、生命保険や医療保険、火災保険などが含まれます。これらは突発的なリスクに備えるためには必要な支出です。
変動費とは
変動費とは、月ごとに金額が変わり一定ではない支出のことです。代表的な変動費には、食費、趣味・娯楽費、日用品・被服費、医療費、交通費・交際費などがあります。まず、食費ですが、例えば、外食を頻繁に利用すると増える傾向にあります。他方で、自炊を心がけることで節約可能な部分でもあります。次に、娯楽費ですが、映画やコンサート、旅行などの費用が含まれます。また、日常的に使用する日用品費については、例えば、洗剤やトイレットペーパー、化粧品などの消耗品が該当します。
| おもな生活費 | |
|---|---|
| 固定費 | 住居費(家賃等) |
| 水道光熱費 | |
| 保険料 | |
| 通信費 | |
| サブスクリプション料金 | |
| 変動費 | 食費 |
| 趣味・娯楽費 | |
| 日用品・被服費 | |
| 医療費 | |
| 交通費・交際費 | |
二人暮らしの生活費の
平均額(月額)は?
二人暮らしにおける生活費項目は、家賃、食費、光熱費、通信費など多岐にわたります。ここでは代表的な3つの生活費の平均額(月額)について解説します。
家賃の平均
家賃は二人暮らしの生活費の中でも大きな割合を占めます。
例えば、LIFULL HOME'Sの「東京都の家賃相場情報」をもとに、東京都23区の1LDK・2K・2DK/マンション・アパート・一戸建ての相場を見てみると、港区では28.70万円、足立区では13.38万円となっています(2025年10月3日時点)。
また、住む場所によって通勤や生活にかかるコストも変わるため、これらも考慮する必要があります。例えば、都心部に住むことで通勤時間や交通費を抑えることが可能ですが、家賃が高くなる場合があります。他方、郊外に住むことで家賃は節約できますが、通勤時間や交通費が多く発生することがあります。
食費の平均
二人暮らしの食費の平均額は約7万5,000円です。外食や出前・デリバリーやオーガニック食品を選ぶ場合はより高額になる可能性があります。
水道光熱費の平均
水道光熱費の平均額は約2万1,000円です。これには電気代、ガス代、水道代が含まれますが、季節や住環境によって変動します。
例えば、夏場のエアコン使用や冬場の暖房使用によって、春・秋に比し電気代が増えることが予想されます。水道料金は、浴室の使用頻度や洗濯の回数によっても変動します。
出典:「2024年 家計調査(家計収支編)」(総務省統計局)
また、上記以外にも家具・家事用品、衣服代、交通費、娯楽費などさまざまな生活費がかかることも押さえておきましょう。
生活費の分担方法
二人暮らしをはじめる際に重要なポイントの一つが生活費の分担方法です。それぞれに合った適切な分担方法を決めることで、日常的な金銭トラブルを避けることができます。
全ての生活費を折半する
全ての生活費を折半する方法は、二人の負担が均等になり、公平感があります。例えば、毎月の生活費が総額20万円の場合、一人あたり10万円を負担することになるため、収入の差に関わらず双方が平等な立場で負担を分け合うことができます。ただし、収入差が大きい場合、この方法が不公平に感じられることもあるため、パートナーと十分に話し合ったうえで決めることが重要です。
収入に応じて負担額を決める
収入に応じて負担額を決める方法もあります。例えば、収入が高い方が家賃や食費の大部分を負担し、収入が低い方が通信費や光熱費を負担するといった方法です。このようにして生活費のバランスを取ることにより、お互いが無理なく生活を維持することが可能です。ただし、こちらも収入差によって不公平さを感じる可能性があるため、お互いに十分話し合ったうえで決めましょう。
その他の分担方法
生活費の分担方法には、他にもさまざまな方法があり、例えば費用の項目ごとに分担する方法が挙げられます。具体的には、家賃は一方が全額負担し、食費や光熱費はもう一方が負担するといったやり方です。また、特定の生活費を交代で負担する方法もあります。例えば、ある月は一方が食費を負担し、翌月はもう一方が負担するといった方法です。
生活費の管理方法
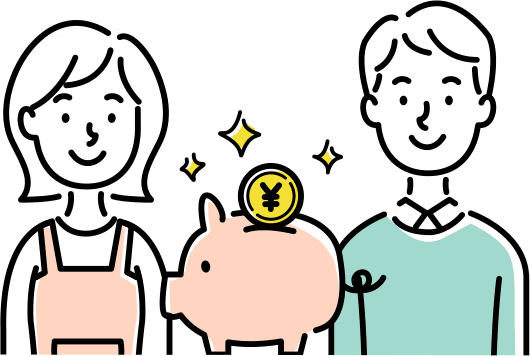
二人暮らしをはじめると、生活費の管理が重要な課題となります。生活費を効率的に管理する方法を探ることで、経済的な不安を軽減し、スムーズな共同生活を実現することができます。ここからはどのような管理方法があるのかを紹介します。
家計管理用の口座を作って
管理する
二人暮らしの生活費を管理するために、家計管理用の口座をどちらかの名義で作り、二人で管理するという方法があります。双方が一定額を家計管理用口座へ入金し、家賃や光熱費などを共通口座から支払うことで、毎月の支出額を簡単に追跡・管理することができます。また、口座残高を互いに定期的に確認することで、無駄な支出を抑えやすくなります。
さらに、この方法は金銭トラブルを防ぐ上でも有効です。二人で協力しながら生活費を管理することで、透明性が高まり、お互いの負担や役割分担を明確にすることができます。
ただし、口座に関する手続きは口座名義人が行う必要があるため、どちらの名義にするかは、今後のライフプランなどをよく話し合って決めることが大切です。
別々の口座で管理する
別々の口座を利用し各自が管理をするという方法もあります。
別々の口座で管理する場合、各自が自分の固定費や変動費をそれぞれの口座から支払うことができます。例えば、家賃は一方が担当し、光熱費や食費はもう一方が担当するなどの役割分担を決めることが可能です。
この方法はプライバシー確保の点でも有効です。プライバシーを守りつつも、互いに協力しながら生活費を分担できます。生活費の一部を共有しつつも、個別の趣味や嗜好にかかる費用は各自の口座で管理することで、お互いの自由も確保できます。
ただし、デメリットとしてお互いの支出が見えにくい点が挙げられます。定期的にコミュニケーションを取り、支出状況を共有することで、効率的な家計管理を目指しましょう。
節約方法と工夫
二人暮らしの生活費を抑えるために、日常生活の中で簡単に実践できる節約方法と工夫を知ることは非常に重要です。以下では、食費や光熱費、通信費など主要な費目ごとに具体的な節約術を解説します。
食費の節約術
食費の節約には、まず計画的な買い物が欠かせません。買い物をする日を決めるなど不必要な買い物を避けることで、無駄遣いを減らすことができます。特に特売日やセール情報を活用することで、食材のコストを抑えることが可能です。
また、自炊を心掛けることで、外食や出前・デリバリーなどの費用を抑えることができます。自炊は、コストパフォーマンスが高いだけでなく健康にも良いため、一石二鳥です。平日はなかなか自炊ができない場合、週末にまとめて料理を作り、冷凍保存するという方法もあります。
さらに、食材の無駄を減らすために、食材の保存方法を工夫することも重要です。その他、傷みやすい食材は早めに使い切るようにして冷蔵庫の整理を定期的に行うことで冷蔵庫内の食材を把握でき、無駄な買い物を避けることができるでしょう。
水道光熱費の節約術
水道光熱費の節約は、日々のちょっとした工夫からはじまります。まず、冬場は断熱シートや厚手のカーテンを用いることで部屋の温度を保つことが効果的です。また、湯たんぽを使うことで、暖房を控えることが可能です。湯たんぽは一度温めれば長時間温かさを保てるため、電気代の節約に有効です。
さらに、シャワーの時間を短くすることで水道代とガス代を節約できます。お湯の温度を低めに設定することも有効な手段です。シャワーの使用時間を5分ほど短くするだけでも、年間を通じて節約効果が期待できるでしょう。
その他、不要な家電の電源をこまめに切る、LED電球に替えるなどの小さな工夫も節約につながります。
通信費の節約術
通信費の節約は、まず現在の契約内容を見直すことからはじめると良いでしょう。携帯電話やインターネットなど、不要な契約やオプションがあれば解約することで、月々の費用を大幅に削減することができます。
携帯電話に関しては、大手キャリアから格安SIMへの変更も検討すると、通信費をさらに抑えることが可能です。特に、データ通信量が少ない場合や、自宅のWi-Fiを有効活用する場合、低料金のプランでも十分に満足できる通信環境を維持できます。
インターネットも、プロバイダーを比較し、より安価なサービスに変更するのも一つの方法です。
その他の節約術は以下の記事を参考にしてみてください
結婚を考えているなら
結婚を考えているカップルの場合は、各種費用や準備が必要です。結婚生活への移行時に注意が必要なポイントを確認しましょう。
結婚の準備に向けて必要な費用
結婚式の費用は、衣装代、写真撮影、招待状作成など多岐にわたり、リクルートのブライダル総研「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」の調査によると平均総額は343.9万円といわれています。ただし、同調査ではご祝儀の平均が約161.3万円であるため、それを差し引いた額が実質的な自己負担額になります。親族の方からの援助があれば、さらに抑えられるでしょう。
場合によっては、ウェディングプランナーを活用したり、割引サービスを利用したりすることも検討すべきポイントです。
結婚後の生活にかかる費用
新婚生活に向けて転居する場合、賃貸物件については敷金・礼金も必要です。その他、家具や家電の購入費用も必要になるでしょう。これらの費用は意外と高額で、例えば冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を新調する場合、合計で数十万円は見込んだほうがよいでしょう。
これらの費用を計画的に準備するためには、まずは自分たちの経済状況をしっかり把握し、無理のない範囲で予算を立てることが大切です。
まとめ
生活費の内訳を把握することは非常に重要です。家賃や水道光熱費などの固定費を正確に把握し、日々の変動費を管理することで、生活費の全体像を理解できます。地域ごとの物価や家賃の違いもしっかりと考慮しましょう。
また、節約術や生活費の管理方法を取り入れれば、経済的な不安を軽減することが可能です。
さらに、結婚を考えている場合は、将来のライフイベントに向けた準備も視野に入れるとよいかもしれません。生活費の管理ひいては貯蓄の重要性を理解し、実践可能な貯蓄計画を立てることは、将来の安定した生活を築くことにつながります。これらのポイントを参考に、自分たちのニーズに合った生活費管理を実践してみてはいかがでしょうか。
りそなの口座なら、銀行取引に応じてポイントがたまります。二人の家計管理用口座を開設するなら、りそなを検討しませんか。
来店不要
スマホアプリで
最短翌営業日に口座開設
マイナンバーカードを
読み取り本人確認!

運転免許証・在留カードなどの撮影でもOK!
- ダウンロードはこちら(無料)
※カードがお手元に届くまで、
約2週間ほどかかります。
既に口座をお持ちの方は
こちらのアプリがおすすめ!
約30分でカード発行
店舗ですぐ!口座開設
印鑑不要・※全店平日17時まで営業
※関西みらい銀行の一部店舗を除きます
- ※即時発行は所定の顔写真つき本人確認資料の場合に限ります。
- ※店舗やお取引内容によっては30分以上お時間をいただくこともございます。お時間の余裕を持っておこしくださいませ。
本記事は2025年10月28日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。