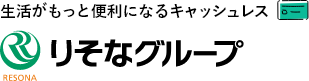マイナンバーカードの作り方を解説!メリットやポイント還元も紹介
公開日:2020/07/28
更新日:2022/06/14
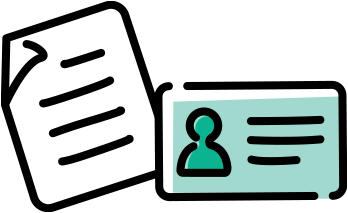
「マイナンバーカードを持っている」人はまだ少ないかもしれません。マイナンバーカードには身分証明書になるだけでなく、役所に足を運ぶことなく近隣のコンビニエンスストアで公的証明書を手に入れることができるなどのメリットがあります。
さらに、マイナンバーカードとキャッシュレス決済サービスを紐づけて、ポイント還元が受けられるキャンペーンも行われる予定です。機能やキャンペーンなど、持っていると何かと便利なマイナンバーカード。今回は、マイナンバーカードの作り方や、そのために必要な手続きなどについて解説します。
- 私が書きました
-
- 主なキャリア
-
ねこのて合同会社 代表。大手メーカーで経理、中小企業の役員として勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとして独立。金融機関での経歴がないからこそ、お客様にとってのメリットを最大化するプランを提案することができることを強みとする。保険だけ、投資だけに片寄ることなく、今の生活も将来の生活も可能性に満ちたものにするようアドバイスすることを心がける。
- ※りそなグループが監修しています
マイナンバーカードを発行する6つのメリット
マイナンバーカードは、本人の顔写真とICチップによる電子証明書などの機能が搭載されたカードです。発行することで受けられるメリットは主に6つあります。
1.身分証明書になる
マイナンバーカードには、氏名や性別、住所、生年月日、顔写真などが記載されており、公的な身分証明書として使うことができます。運転免許証を取得していない人や、返納した人にとっては、マイナンバーカードは身分証明書として重宝するでしょう。
ちなみに初めて発行する場合、費用はかかりません。
また、15歳以上であれば、自分で発行の申請ができます。15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親など)の代行で申請は可能です。
2.オンラインで確定申告ができる
マイナンバーカードを取得している場合、税務署のe-Taxに利用登録すると、自宅にいながら確定申告の処理を完了することができます。確定申告期間中、税務署の窓口は混雑する傾向があります。平日に時間が取れず税務署に出向くのが難しい人にとって、e-Taxは便利です。
なお、2020年7月現在、マイナンバーカードがなくても「ID・パスワード方式」でe-Taxをすることができます。しかし、ID・パスワード方式は「マイナンバーカードが普及するまで」の暫定的な対応なので、いずれ利用できなくなります。今のうちからマイナンバーカードでe-Taxができるようにしておくほうがよいでしょう。
3.コンビニエンスストアで公的証明書を取得できる(※一部自治体は不可)
住居の契約や自動車の購入・売却をするときなどは、住民票や印鑑登録証明書などの添付が必要になります。これらの書類は、自治体によっては平日の役所を訪れなければ取得できません。しかし、マイナンバーカードがあれば、夜間や休日でも、6時30分~23時までの時間内であればコンビニエンスストアで取得することができます。ただし、すべての市区町村・コンビニエンスストアで取扱われているわけではないため、お住まいの場所で利用可能かどうかは、以下のサイトでご確認ください。
4.マイナポータル(オンライン機能)で行政サービスが受けられる
マイナンバーカードを取得すると、政府のオンラインサービス「マイナポータル」を利用できます。住んでいる自治体での子育てや、介護などの行政サービスの、オンライン申請が可能です。申請できるものには、認可保育所の入所申込みや児童手当の申請、要介護・要支援の認定申請、税金や公共料金のオンライン決済などさまざまです。
5.スムーズに証券取引ができる
投資をする場合、口座開設や住所・氏名の変更にあたってマイナンバーが必要です。2015年12月31日以前に口座開設をした方でも、2022年以降は、株式・投資信託などの売却代金や配当金などを受け取る際に、マイナンバーを金融機関に提出しなければなりません。
金融機関へのマイナンバー届出の際は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなどが必要になります。住民票の写しの場合は運転免許証などの本人確認書類もあわせて必要となりますが、マイナンバーカードがあれば1枚だけで手続きが進み、便利です。
マイナンバーカードの作り方は?「発行に必要なもの」もあわせて解説
マイナンバーカード作成は難しくありません。ここでは、申請からカードの受取までの流れを説明します。
発行に必要なものは2つ
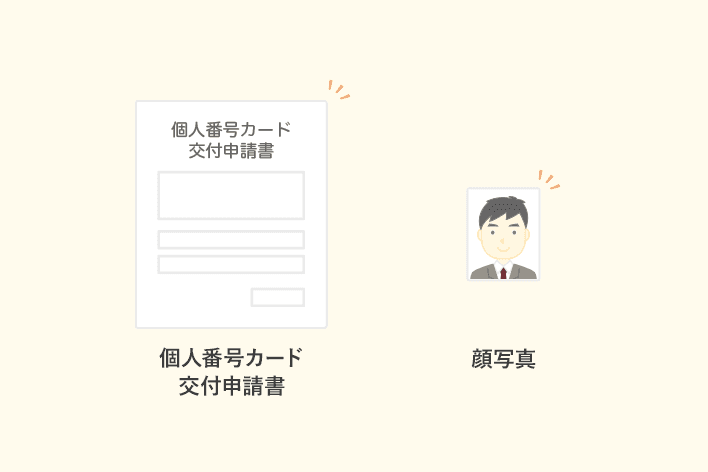
マイナンバーカード発行申請で準備するものは、「個人番号カード交付申請書」とカードに載せる「顔写真」の2つです。手続きでは、23桁の半角数字「申請書ID」も必要になり、こちらは個人番号カード交付申請書に書かれています。
個人番号カード交付申請書は、マイナンバーの通知カードの下部にあります。通知カードとは、マイナンバーが決定された2015年10月以降に届けられた、マイナンバーが記載された紙製のカードです。個人番号カード交付申請書がない場合は、再交付手続きを行いましょう。総務省のマイナンバーカード総合サイトで交付申請書をダウンロードすることもできますが、こちらは申請書IDが書かれていない手書きの用紙で、郵送での手続きにしか対応していないので注意してください。
マイナンバーカードの申請方法は4つ
マイナンバーカードの交付申請は、4種類の方法から選ぶことができます。それぞれについて、簡単に説明します。
パソコンで申請
パソコンで申請する場合、交付申請用のWebサイトにアクセスします。氏名とメールアドレスを登録したら、交付申請書に書かれている23桁の申請書IDを入力します。その後、登録したメールアドレスに申請用のアドレスが届くので、アクセスしてからデジタルカメラで撮影した顔写真を登録してください。最後に、生年月日などの必要事項を入力すれば完了です。
スマートフォンで申請
スマートフォンで申請する場合は、交付申請書にあるQRコードを読み取って交付申請用Webサイトにアクセスし、メールアドレスと名前を登録します。QRコードには申請書IDの情報が含まれているので、申請書IDの入力は省略できます。登録したメールアドレスに申請用のアドレスが届くので、アクセスしてからスマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録してください。最後に、生年月日などの必要事項を入力すれば完了です。
証明写真機で申請
マイナンバーカードの交付申請は、一部の証明写真機からも可能です。メニュー画面で「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。そのあとは画面の案内に従い、必要事項の入力と顔写真の撮影をしてデータを送信すれば完了です。詳しい内容は、マイナンバーカード総合サイトから証明写真機のサイトを確認してください。
郵送で申請
郵送で申請する場合は、通知カードに付属している「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入して郵送します。料金受取人払いの封筒素材が公式サイトからダウンロードできるので、切手代はかかりません。(差出有効期限2022年5月31日)。
マイナンバーカードの受取方法は2つ
マイナンバーカードは1ヵ月程度で完成し、「窓口受取」か「郵送受取」のどちらかで受取ることができます。原則は窓口での本人受取りです。
窓口で受取る
申請から1ヵ月ほどすると、住民票のある市区町村から「交付通知書」が届きます。マイナンバーカードを受け取るには、この交付通知書の他に本人確認書類もしくは写真付きの住民基本台帳カード、通知カード(2020年5月までに交付されている人)を持参し、交付通知書に記載されている交付場所で受取ります。その際、暗証番号の設定が必要です。
郵送で受取る
マイナンバーカードを郵送で受取ることができるのは、交付申請を窓口で行い、本人確認と暗証番号の設定を行った場合のみとしている自治体がほとんどです。「Webで申請、郵送で受取り」など、役所の窓口に一度も行くことなくマインバーカードを作成することはできません。
まとめ
キャッシュレス決済がますます身近になる中、口座開設もよりスムーズに行えるようになっています。
口座開設アプリを使えば、マイナンバーカードを読み取り本人確認するだけで普通預金口座の開設がかんたんに完結。
はじめての方でも、スマホひとつで日々のお金の管理を始められます。
来店不要
スマホアプリで
最短翌営業日に口座開設
マイナンバーカードを
読み取り本人確認!

運転免許証・在留カードなどの撮影でもOK!
- ※カードがお手元に届くまで、約2週間ほどかかります。
本記事は2020年7月時点の情報に基づいて執筆者(ファイナンシャルプランナー)独自の調査によって作成しております。将来の相場や市場環境、制度の改正などを保証する情報ではありません。